大島幸久の『何でも観てみよう。劇場へ!』
現代演劇情の世界
水谷豊が帰ってきた NEW! 
水谷豊(70)が舞台に帰ってきた。なんとなんと約23年ぶり。映像分野で大成功した彼が、恐らく意を決したのだろう。シス・カンパニー公演『帰ってきたマイ・ブラザー』の東京公演(世田谷パブリックシアター)である。
観劇の第一の目的は、その長いブランクだ。舞台は3度目という。最初は昭和19年(1944)、14歳の時。劇団・雲の『ドン・ジュアン』に客演、山崎努が演じた主人公の召使・ラ・ヴィオット役。二度目は平成12年(2000)、『陽のあたる教室』の音楽教師の役。ピアノの生演奏もしたという。この間、少年時代から壮年期へ。実に56年間のブランクを経て舞台に出演していたのだ。プログラムで轟夕紀夫氏が詳細しているが、大学受験を控えて俳優業を一度、足を洗っていたのが2年間。水谷豊という俳優は自己変革に努力を惜しまない意欲、決断、勇気を備えているのが分かる。
さて、復帰舞台だが、40年ぶりに再会した兄弟4人が、かつてのコーラスグループ「ブラザー4」を再結成して、たった1曲の大ヒット曲「マイブラザー」をもってコンサートを開くストーリー。マギーの脚本、小林顕作の演出が面白く見せた。
長男の若村ハジメが水谷、次男・信二が段田安則、三男・裕三が高橋克実、末弟の四男・四郎は堤真一。よくまあ、これだけの多忙なタレントを集めたものだ、とプロデューサーには感心した。
水谷は開演からいきなり登場した。リードボーカルであり、総領息子だから、弟たちを巻き込むやっかいな性格。『相棒』とは全く異なる役柄なのだが、出ずっぱり、大量の台詞、それもスピード感のある芝居を演じ抜いた。声は良く通るし、バアさんの物まね、両腕の肘を張ったキザな格好しいの仕種など、まるで喜劇俳優じゃないか。
舞台は2023年の春、という現在の設定、場所は神奈川・浦賀。辺鄙といえる場所でのコンサートなのが展開の“壺”であり、いい味付けになっている。水谷自身は上から四番目の末っ子とか。しかし、長男の役はピッタリだった。
「僕は何かをやらずに考えているよりも、やって結論を出すのが好きなんです」「去年古希を迎えたんですが、いつまで俳優をできるかわからないけれど、舞台をやらずに悔いを残すのは嫌だなと思ったんですね」、とプログラムに書いていた。
当方は個人的にはショーケン(萩原健一)と共演したテレビドラマ「傷だらけの天使」(1974~75)で彼を発見したのだが、現在の「相棒」は再放送まで見ている。
また、娘さんの趣里のファンなのである。舞台で異色を放つ個性派女優。なんとも可愛い。父親として舞台姿を見せたかったのでは、と勝手に推測している。とにもかくにも楽しそうに演技をしていた水谷豊。これを機会にもうブランクなしでチェホフなら「かもめ」とか「ワーニャ叔父さん」などで親子共演も考えて欲しい。演劇界にワンピースが増えた、と思う。
(令和5年5月11日)
『笑の大学』の内野聖陽と瀬戸康史 
三谷幸喜・作・演出『笑の大学』は内野聖陽、瀬戸康史の二人芝居。笑いの要素が満載の三谷作品でも一、二と言える傑作である。四半世紀ぶりに復活した再演だが、俳優2人の怪演、熱演、そして三谷自身が乗り出した演出によって久しぶりに演劇の醍醐味を堪能した。演劇大賞ものだ。
昭和15年の舞台背景は、戦後色が濃厚の時代。内野が演じるのが警視庁検閲係の向坂睦男。一方の瀬戸は劇団・笑の大学の座付作家・椿一。向坂は椿の書いた喜劇に難癖を付け、書き直しをしない限り上演を許可しない。非常時に笑い、喜劇とは何事か!という権力側の論理だ。
椿は初日が迫る中、あの手この手を繰り出しながら物語の設定を変更し、場面・台詞を直していく。その攻防戦が、愉快なのだ。なぜだろう。
強要しながらもアイデアを提供、手直しが済むとさらに意外な要求で追い詰める向坂。7日間に渡る闘いの中、劇中劇で「金色夜叉」の熱海の海岸で貫一、お宮に仕立てたり、内野が禿げ頭のカツラになれば瀬戸は女装して女形になる。思わず身をのけ反る面白い場面だった。
向坂は動物好きで飼育しているカラスの巣箱を椿はプレゼントしたり、そのカラスが逃げてしまい、落胆した夫婦にジュウシマツを贈るのだが向坂が籠の中の小鳥に「ピーちゃん!」と声をかける愉快さ。そんな場面は、三谷が内野の体内に埋蔵していた喜劇センスを引き出したのだ。
楽しそうに演技を続けた瀬戸、喜劇の素養を発揮した内野。井上ひさしさん泣き今、三谷の新作が待たれるばかりである。
(令和5年2月23日)
不思議な世界の趣里ちゃん 
神奈川芸術劇場で上演された城山羊の会による『温暖化の秋』(11月27日まで)に、趣里(32)を見に出かけた。会を主宰する山内ケンジの作・演出。趣里は、随分と以前にその舞台を見知ってから密かに注目し続けている女優だ。調べてみたら2015年、赤坂レッドシアターでの地人会新社『クライムス・オブ・ザ・ハート』で、強烈な印象を残したのを思い出した。
今回、彼女は「ねるり」という奇妙な名前を持つ若いが、「気持ち悪い」と周囲から言われている女性だ。「当たりだ!」。彼女に嵌まる役柄じゃないか。
交際中の添島コウ(橋本淳)と公園広場のような場所で、たわいのない会話を続ける。と、中年夫婦、危険な関係と思える男女のカップルと出会わせ、すれ違いの話を延々と続ける。「ねるり」は激しい気性のようだ。カップルの女性、カンザキサキがかつてコウと付き合っていて、サキは「婚約した仲」だと明かした辺りから趣里の演技が劇的に変化した。「ねるり」の心が一気に“温暖化”するのである。
実は、サキは嘘つきなのだが、怒り、戸惑い、不信感。趣里は相手たちの話や対話を耳にしている時、その反応、つまり受け取り方が何とも言えない巧さ。目だけの動き、下唇を噛む…といった表情、細かい身体表現の多彩さによって、「ねるりを描いた。
コウに別れを突きつけ、ロープで首を吊る。死んでしまった、と皆が騒ぐ(しかし、私は信じなかったが)。そして、やっぱり蘇生する。「ゲホッ!」。物凄い咳をして回復したその迫力の声はどうだ。
蘇生してくれた田中(じろう)という妻子ある男にやたらとキスをされ、気の毒なおかっば頭の「ねるり」ちゃん。それでも最後は男に付いて行った。不思議な物語の、不思議な女性が面白い趣里ちゃんでした。
(令和4年11月17日)
大竹しのぶの占い 
大竹しのぶが杉村春子の名演で有名な『女の一生』に初めて取り組んだのが2020年10月の新橋演舞場だった。その時期、新型コロナウイルスの感染症が拡大し、観客の入場を50%に制限。今年10月の新橋演舞場から始まり南座まで続く今回の再演は出演者にとって一段と身が引き締まる公演だ。
主演の大竹、そして演出と夫君になる伸太郎役の段田安則が取材会に出席した。
杉村が通算947回演じ抜いた代表作。大竹は初演の経験から話を始めた。「杉村先生がやり続けたいと思われたのを、戯曲と向き合って分かった。以前、テレビ番組のお仕事で1回だけお会いしたことがあって、“あなたの時代はいいわね。空襲の警報が鳴っている(時代下が)私の時代だったのよ”とお話しが出来たのが思い出」と懐かしがった。
そして、一人の女性として、人間として孤独の世界を生きた主人公布引けいと自分を重ねた。「私は二十歳、ハタチで父を亡くし、これ以上の悲しさはもうないと思ったのに、三十で夫を、そして母も亡くしました。一人になって寂しさを今、感じています」。
『女の一生』という名作は、時代は違っていても女の運命、生き方を主題にしている。「誰が選んでくれたのでもない。自分で選んで歩き出した道ですもの」。この名台詞が象徴している。
取材会の前日に放送されたNHK大河ドラマ「鎌倉殿の13人」で老女ババアに扮した彼女が笹竹を操って水占いをしていたのを見ており、私はこう質問した。
「これからの日本の女性はどのように生きるのでしょう? 占って下さい」。すると、こう言葉を返してくれた。
「男もそうですが、女にしかないものが絶対あると思うんです。大事なのは自分の心に嘘なく、意見を持って欲しい。それをはっきり言っていく人になって欲しいと思います。これで、オッケ~?」と、私に笑うように答えたのである。
燦然と輝く不朽の名作『女の一生』は、段田が語ったように「影の部分、嫌な部分を書いている」。大竹は16歳の姿で登場し、56歳までを演じる。結ばれたいと思った人ではない相手と結婚し、子供を設け、夫を先に亡くす中、自分を押し通した女性を、大竹はどう掘り下げるのだろう。
(令和4年10月3日)
100歳になったアニー 
ミュージカル『アニー』が1986年の初演から上演37年目になった。東京・初台の新国立劇場で開幕したが、昨年の東京公演が初日が千秋楽となり、コロナ禍の影響で気の毒な形。あの日のカーテンコールで無念の報告をした出演者の表情は忘れられない。
今回は新たな出発である。
まず、主な出演者が代わった。アニーを養子に迎える大富豪ウォーバックスが初参加の葛山信吾、ルースターが財木琢磨、リリーの島ゆいかも初登場だ。一方、2001年から常連のドレーク役・鹿志村篤臣が健在なのが嬉しかった。ちなみに、初演からの私のベスト配役はウォーバックスが目黒祐樹、ハニガンは夏木マリ、グレースは岩崎良美、ルーズベルト大統領が永井秀明、ルースターが尾藤イサオです。
次に、ダンスキッズが復活、オーケストラ演奏が生演奏になった。
重要なポイントは短縮特別バージョンであることだ。もちろんコロナ禍での上演であり、安全・安心がその理由。カットされた主な場面は、孤児院を抜け出してやって来た橋の下のスラム街、映画館での鑑賞、ラジオ出演で出ていた色気たっぷりの3人娘、ルーズベルト大統領と閣僚の前で歌う「トゥモロー」…。これらは当時の時代の空気や、登場人物の人間関係の対比といった物語を多彩に描くのに大切だった。
『アニー』を見ながらいつも私が涙を堪えるのに必死なのが二つある。もし両親と再会出来たらとアニーが歌う「強く抱きしめて」の歌詞、「分かったいたんだ。可愛がってくれたのに迎えに来れないのは」の台詞。
良い子の皆さんには、家族の愛情、温もり、楽しさ、大切さを思い出し、貧しくても明るく元気に生活して「トゥモロー」、明日を信じて生きましょう、ね。そのテーマをより提示するためにも、上演40周年には、本来版、決定版の公演が出来るのを願って止まない。
(令和4年5月3日)
鹿賀丈史と市村正親の絆 
ミュージカル『ラ・カージュ・オ・フォール』が3月から、日生劇場などで上演される。日本初演から7演目、2018年以来4年ぶりである。1月25日、主演の鹿賀丈史(71)、市村正親(72)が出席し、製作発表会見が開かれた。
ゲイクラブ「ラ・カージュ・オ・フォール」の経営者ジョルジュが賀鹿、その看板ダンサー、ザザことアルバンが市村。男性同士の2人は事実上の夫婦として長く生活、ジョルジュには一人息子ジャンがおり、アルバンは母親代わりとして手塩にかけてきたが、その息子が結婚宣言したことで物語はテンヤワンヤになる。会見での2人は劇団四季時代からの盟友であり、既に4回演じてきた代表作に自信に満ちた答弁だった。
「私もいい年になりましたが、鬘を被っている時じゃないと地毛でやらしてもらいます。他人への思いやりがふんだんに散りばめられた素晴らしいミュージカル。ゲイクラブを2人で経営し、わがままな妻でもそこがかわいい。かけがえのない人だな、と思う」と鹿賀。「44、5歳で出会ったこの作品。30年前は非常に元気で美しく華やかでした。丈史は(四季時代)、いい声で『ジーザス・クライスト・スーパースター』など常に舞台に先端に立っていた。自分は小蠅のように周りを生きてきた。憧れの丈史がいたからここまて来れた。愛と喜びと感動を与えられたらと思う」と市村。
2人はそれぞれの長所を褒め合い、丁々発止のやり取り。賀鹿は「芝居をしていない時も、自分は(社会に)何ができるかを考えている」と語ったが、ミュージカル界のトップに立ち続けているスター同士は「愛の貴重さ」を伝える代表作に熱弁を振るっていた。
(令和4年2月8日)
村井國夫に魅せられた! 
東京は江東区の亀戸カメリアホールで上演されたトム・プロジェクトの短期公演『芸人と兵隊』(1月19日~21日)で、老練な俳優村井國夫に魅せられた。
昭和16年、中国の戦地で戦う日本兵に笑いを届ける芸人一行の苦闘物語だ。村井の桂銀作は妻の花畑良子(柴田理恵)と夫婦漫才、弟子の春田左近(カゴシマジロー)・春田右近(向井康起)の漫才コンビ、落語家の柳家亀鶴(高橋洋介)、ダンサー霧島桜子(森川由樹)と共に前線近くまで回り、およそ9か月もの長旅で芸を披露する。
村井は呼吸の合った漫才の語り口、弟子を叱るソフトな感じ、笑いが取れないネタの工夫といった場面など芝居が実に自然。しかし、それ以上に恐れ入ったのが、煙草を吸う細かい仕種、戦闘の最中に命を落とした妻の骨壺を抱きしめる場面、東京に戻った寄席小屋で一人だけの漫談に初めて立ち、無念の思いを語るシーンが絶妙だった。漫才師という芸人は、彼の仁ではないと思うのだが、全身から伝わる空気、風情が何とも言えない。手練の舞台俳優ではあるが、いよいよ演技の奥地に踏み込んだ、いぶし銀の味がたまらないのだ。役を作るのではなく、役に生きる。嬉しいベテラン俳優だ。
(令和4年1月24日)
わが青春のセリフ 
シアタークリエで見たミュージカル『GREASE(グリース)』で良かったのは「一」に振り付け、「二」に俳優。その一番目は脇役だがパディを演じた濱平奈津美、二番目が主演の三浦宏規、そして「三」が屋比久知奈だった。
1950年代のアメリカ。若者の男はポマードでピカピカに撫でつけたリーゼントの頭髪、ブルージーンズ(デニム)を履いて皮ジャンパー(バイクジャケット)というスタイル。女といえばそれぞれが個性的でユニークな髪形。彼らが躍る群舞はパンチがあり迫力いっぱい。今の日本の若者とは大違いの元気一杯の振りを見せた。藤林美沙、青山航士二人の振付が抜群だったのも理由に挙げる。
俳優では、パディ役の濱平は全4役だったが、どれも他の女優陣の中でもダンスが際立った。自分なりの個性を出していたのである。
主役ダニーの三浦は不良グループのリーダー。“フラット・トップ”とかいうトサカ頭、白い肌がカッコいい。付き合っているサンディについて仲間に「ただの友達さ、それ以上でもそれ以下でもない」の台詞にドキリとした。実は私、大昔、「好きでも嫌いでもない。ただ興味があるだけ」なんぞと、キザな告白をしたのを思い出したからだ。
サンディの屋比久知奈。品行方正、お嬢さんといった前半の芝居より、後半、ガラリと一変する弾けたファッションになって、俄然、面白くなった。
ところで青春期、恋する女は強い。何をするか分からない。見当も付かない。それに引き換え、男はだらしがない。臆病になるんだねえ。ブルージーンズに皮ジャンパー。青春を思い出させるミュージカルでした。
(令和3年11月29日)
『キャッツ』、私のベスト5 
劇団四季のミュージカル『キャッツ』を4月23日に見た。5回目の東京公演の千秋楽が6月20日で、その前に関係者らを招待したのである。
四季のミュージカルには思い出深い作品がいくつもあるのだが、『キャッツ』は特に忘れることが出来ない。初演が昭和58年(1983)11月11日、東京・西新宿キャッツシアターだった。その記念すべき上演に当たり劇団はニューヨーク・ブロードウェイでの公演にマスコミを同行させて観劇ツアーを行った。
ビックリしたのは空路、特別専用機で乗り込んだことだった。あの時代、新劇の劇団では快挙というか暴挙というかの初の企画。現在だって、考えられない。共同主催のフジテレビと組み、ロングラン公演への意気込みは凄かった。
初めて目のあたりにしたブロードウェイ版は客席にまでネコたちが入り込み、ラム・タム・タガー役の男優が素晴らしく恰好良く、『メモリー』が素敵だったことーといった事を今でも覚えている。
何回見ただろう。東京での各公演で複数回、観劇してきたから10回は越えている。名曲オンパレードの中で、時折口ずさむ曲がある。
やっはりナンバー1は、『メモリー』で決まりだ。熟考を重ねても、これを選んだ。志村幸美、前田美波里…。皆良かった。今回、グリザベラに注目して追ったが、出番が少ないという記憶は間違い。場所を変えて何回も登場していたのに気付いた。「月明かりの中、美しく去った、思い出よ、帰れ!」。年を経た人ほど胸が締め付けられる名曲である。
二番目は「アクト2」に出る「ガス・劇場・猫」。大好きな場面だ。アスパラガスが「見せようか?」と、若き日の自慢の芝居を披露する、そしてグロールタイガーに変身し、海賊と闘うシーン。「今の芝居もいいけれど、比べものにはならないね]と、栄光の時代を回想するのが、いい。これも年寄りを泣かせる場面なのだ。『メモリー』でのメスねこ・グリザベラ、オスねこ・ガスとの対比なって巧い仕掛けじゃないか。でも、大好きなのはグリドルボーン。「グロールタイガー、私に心奪われ…」。男を騙す可愛く色気たっぷりの演技。女は男を騙すのが当たり前、男は女に騙されるふりが楽しみ。光枝明彦のガス、保坂知寿のグリドルボーンというコンビは最高でした。『メモリー』とダブル1位にしたい程だ。
三番目は「オールドデュトロミー・長老猫」。彼を尊敬するねこたちが「彼と共に生きる幸せ」と歌う。人生は短い。老若男女とも、共に歩んでくれる人を思う大切さを教えてくれる。
第4位は「スキャンブルシャンクス・鉄道猫」。寝台列車に乗り、乗客サービスに徹する鉄道大好きねこ。「モーニングティーは薄め?」と呼びかけると「濃いめ」と答える若いメスねこ。走る列車、それが一瞬でバラになり、また再構築される。スリリングでたのしい一場面である。
そして、最後は「マンゴジュリーとランプルティーザ・小泥棒」だ。中央競馬の競走馬に『キャッツ』に登場するねこの名前を付けた馬主さんがいたが、よほどにファンなのだろう。間違いかも知れないが、この2匹のどちらかを名乗った馬がいたような。とにかく、ダンスに見応えがある場面ふんだんの作品の中でも、2匹が躍るダンスは圧巻だ。
以上、ベスト5。
しかし、東京公演は3回目と4回目の間が10年。4回目と今回の5回目の間隔が14年あった。次回は? 私はもう見られないだろう。
「メモリー、仰ぎ見て月を~」と、年老いた芝居ねこの私は、口ずさんでいる。
(令和3年5月5日)
南沢奈央にご注目を! 
南沢奈央という若手女優が気になっていた。NHKの土曜ドラマ『蛍火』で準ヒロインを演じ、その新鮮な印象が記憶に残っていたからだ。
清原果耶が扮した主人公・菜々が父の仇を討つ物語。南沢の役は菜々の恋敵、武家の娘・雪江。風早市之進を一途に恋慕うのだが、会えて言えば意地悪な一面を持つ。若い娘には必ず潜んでいる盲目的な恋心がそうさせる。彼女はその必死を目と口元と声で表現した。色白で、両方の黒目が大きいのが特徴。ただ、映像むきの女優と見ていた。
南沢が神奈川芸術劇場での『アーリントン』に出演した(1月16日~31日)。早速、出向いた。劇場入口で、一人の男性を劇場スタッフから紹介された。彼女の父親だった。プロダクションから離れ、個人事務所に所属したのだが、父親はその代表だという。いかにも好人物。立ち話によると娘さんは舞台が好きなのだという。道理で、たった二人芝居(3人目はダンサー)に出演するのもよほど舞台が好きなのだろう。
『アーリントン』はラブストーリー。南沢が演じたアイーラは密室の待合室で自分の番号が呼ばれるのを待ち、隣部屋に居る若い男が自分を呼び出すのだが、最初は噛み合わない会話が続く。
何より良かったのは台詞がしっかり客席に届いたことだ。舞台での発声が出来ていた。想像したより細身の姿態でも運動選手のように引き締まった体つき。服を脱ぎ、ブラジャーとパンティになって演じる場面もあった。武家娘とは大違いの大胆な役柄。
2019年、同じ白井晃・演出『恐るべき子供たち』と比べて、はるかに成長していた南沢。次ぎのステップ・アップが楽しみになった。
(令和3年1月29日)
松村式ミニキーナ 
休館していた座・高円寺の再開第1作である劇団カムカムミニキーナの『猿女(さるめ)のリレー』を7月8日に見た。劇団の旗揚げ30周年の第1弾でもあった。
作・演出の松村武ら5人が1990年に旗揚げした劇団。よくぞ30年、活動を続けてきたものだ。偉い!
今作は松村の渾身の新作となった。松村は比良坂書店という古書店の主人だが、娘の浮美世を追いかけてきた遣麿による火事で、わずか1冊の本だけ残して焼失してしまう。立ち読み男の高階、娘も死んだ。その1冊を巡って神代の時代の俳優(わざおぎ)の子孫たち、つまり猿女が現代までのいくつもの時代に闘いと芝居を繰り広げるという破天荒な物語である。
松村はその中に、演技をするとは何か、俳優はなぜ演技するのか、演ずる舞台(ステージ)との関係をあらゆる手法を使った演出力でグイグイと押し込んでいった。
リレーとは30年間積み重ねてきた自身と劇団の歩み、日本人が始めた演ずることの歴史の背景や闘争を今、受け止めて、次に進むことを考えることだ。
男優では富岡晃一郎、山崎樹範には八嶋智人を超えて欲しい期待を感じたし、女優陣では藤田記子、野口かおるにもっともっと個性を伸ばす演技の可能性を追求して欲しい。
そして、松村。彼の演技をずっと見続けた。自ら椅子を移動させ、幕の開閉をし、出番がない時は舞台両袖に座って芝居に目を光らせていた。この情熱こそ30年間継続させた座長のチカラであった。
(令和2年7月21日)
白鸚の見果てぬ夢 
私は白鸚を名優だと考えている。それも特別な存在だと思ってきた。それは今も変わらない。歌舞伎役者として、また、現代劇でも一流である。世界でも類がない唯一無二、空前絶後の俳優なのである。
私は『ラ・マンチャの男』はこれまで見てきた中のベスト1ミュージカル(ちなみに2位は『オペラ座の怪人』、3位は『ファタスティクス』に挙げている。名作中の名作である。
その白鸚が4年ぶりに『ラ・マンチャの男』に取り組む。市川染五郎を名乗っていた当時26歳の1969(昭和44年)年に初演してから50周年。9月7日の大阪公演を皮切りに宮城、愛知を経て10月4日に帝国劇場が開幕する。8月10日には喜寿である77歳を迎え、通算上演回数は1300回を越える大記録となる予定だ。
6月に開かれた制作発表記者会見で白鸚は大いに語った。その後の2次会見でも胸の内を語り尽くしていた。今回の記念公演には「遍歴の旅はクライマックスへ-」というキャッチフレーズが付けられていたから、もしやラストステージかといかぶる向きもいたが、一般のファンも参加した会見は白鸚の一人舞台のようでもあった。
印象に残ったエピソードの語録を紹介する。
主題歌「見果てぬ夢」を歌う時、「父の初代白鸚と菊田一夫の二人へのレクイエムだといつも思っています」。これは父と菊田が出会い東宝入りしたことによって『ラ・マンチャの男』に出演できたからだ。菊田は初演前の22歳と若い染五郎にこう話しかけたというのだ。
「日本にミュージカルが根づくまでミュージカルを続けよう」。その後、ブロードウェイから上演話が来た。『スカーレット』で日本初の上演を狙っていた菊田は「おめでとう」と握手の手を差し出したが、「その目は嫉妬と怒りのような目でした」と笑った。
歌舞伎とミュージカルの二筋道を走り続けてきた点が何といっても興味深い。
「両方やっている思いはない。いい芝居だからやっているんです」。これは蜷川幸雄演出で『ロミオとジュリエット』を演じる時、蜷川も「シェイクスピアではなく、いい芝居だからやるんだよね」と話し合ったのを思い出したそうだ。
また、「両手両足を引っぱられて生木を割かれる思いでもある」と語った。さらに例えた白鸚らしい表現に感心した。それは『勧進帳』の弁慶と『ラ・マンチャの男』のドン・キ・ホーテはどちらが重い?と私が質問した答えだった。どちらとは断言しないのは折り込み済みだった。
「両方、二人とも杖を持っている。槍と金剛杖。二人とも旅をしているんです。遍歴と逃避の旅をしているのです」。キ・ホーテが槍、弁慶が金剛杖。私は追い打ちをかけるように迫ったのである。
会見で「クライマックスも、閉じることもありません。来る所まで来た。もう後戻りはできないという感じですかね」と、今回、77歳にしても続ける意思を示していた発言についてだ。私は「会見で米寿の88歳でもやるとお話になりましたが…」と嘘、冗談をぶつけたのである。
白鸚は答えた。「命があれば120までやっているかも。いつの日にかお客様の中の脳裏の中に、あんな俳優がいたなと残されていてくれればいい…」。『ラ・マンチャの男』も『勧進帳』の旅も続け抜く白鸚の見果てぬ夢は計り知れない。
(令和元年7月9日)
『女の一生』を見ると… NEW! 
森本薫・作『女の一生』は菊田一夫による『放浪記』と並ぶ日本の現代劇の傑作戯曲だが、文学座が全国公演中の舞台(新宿・サザンシアター)を見ると、内包された現在の演劇への問い掛けをつくづく思い知らされるのだ。
名女優の名演を生んだ作品を誰が継承していくのだろう。現在、歴史に残るような素晴らしい戯曲はなぜ誕生しないのか。名作を劇団による上演とそれ以外の公演を比較した場合、その成果の相違は何か。これだけではないのだが、『女の一生』を見ると、常に思い浮かぶのである。
山本郁子が演じた布引けいを見たのは2度目。前回より格段に成長していた。第1幕から終幕の5場まで終始、安定した演技を続け、少女から老年へと移り行く時代の中での運命の揺れを演じ続けていた。部分的にはどうしても杉村春子の絶品を重ねてしまうから、批判的となる。細かい指摘は止めよう。
義母しずの赤司まり子、義理の叔父章介の石川武がしっかり脇を固めた。夫の伸太郎の大滝寛、初恋の人・栄二の上川路啓志たち一家の俳優もまずまずの合格点をあげる演技だった。劇団のチームワーク、アンサンブルの成果だ。
傑作戯曲、名女優の名演などは滅多に生まれるものではない。名女優の財産演目の継承は重要であり、一方、並大抵ではない。
(平成30年11月1日)
『生きる』の成果と課題 
市村正親と鹿賀丈史がダブルキャストのミュージカル『生きる』(東京・ACTシアター)の成果と課題を考えた。
我が国のミュージカルと言えばブロードウェイ、ロンドン産の翻訳作品が主力。近年は韓国などの参入を加えて多彩化した。一方で国産のオリジナルは昭和三部作を始めとする劇団四季が先頭に立ち、音楽座、ミュージカル座も名作を産んでいるものの、まだ途上。
『生きる』はその現状に一石を投じた。
黒沢明監督による名作映画の初の舞台化、それもミュージカル化は画期的だ。名もない一般の庶民が主人公であり、しかも胃ガンで余命半年と見られる老人の物語というのも常識外と言えよう。ミュージカル界を牽引する市村と鹿賀を主演に置いたとはいえ冒険には違いない。
企画・制作がホリプロというプロダクションであるのも注目したい。劇団でもなく興行会社でもない大手プロダクションの挑戦である。この点を大いに認めたい。
2回歌われる有名な「ゴンドラの唄」。特に2幕ラストの場面はこれ以上の感動はない。1幕の幕切れの「二度目の誕生日」は人生をどう生きるか、日々の生き方に無駄はないのかという主題を強く訴えた。
「ボ~ッと生きてんじゃねえよ!」。
映画「生きる」の上映から66年。スマホに浮かれるノ~天気な国民への警告は今こそ重要なテーマであることを伝えた。
課題もある。
息子夫婦が父の渡辺勤治の重病をなぜ気付かなかったのか。本人が言わなかっただけでは説明が付かない。息子が病院に押し込んでしまうというのも分かりにくい。脚本を現代の中で練り直してはどうだろう。踊りの場面も馴染めない演出だった。市民課職員、町の主婦たちの演技陣、小田切とよの女優…。再演では一新してもいいだろう。
映画と同様にモノクロの印象を与えた舞台全体は好感を持った。世界で通用するオリジナルミュージカル創出への本格化。『生きる』はそれを教えてくれた。
(平成30年10月9日)
ラサール石井に乾杯! 
東池袋のあうるすぽっとで上演された『死神の精度』ほど、近頃刺激を受けた舞台はなかった。ラサール石井が素晴らしいのである。
脚本・演出・和田憲明、上方部から派遣された「死神」調査員の千葉が萩原聖人、その彼に7日間観察され「死」を実行される対象者の藤田がラサール。藤田はヤクザ。登場した瞬間からもうラサールはこれまでのタレントでも演出家でも、また俳優での仕事とは無縁のように生まれ変わっていた、と見えた。舞台俳優そのもの。こんな演技が出来るのか、そう、実感した。
多くの人間を殺してきた過去を背負い、新たなターゲットを狙っている不気味さ、世話をしている若いヤクザの阿久津を支配する傲慢さ、台詞にピタリ嵌まった一つ一つの細かい仕種。
8月30日に見たが、台詞を忘れたり、役名を間違えたりしたが、もうどうでもいい。舞台には藤田という男だけがいた演技。それもこれも演出の和田のおかげだろう。二人が計算し尽くした役作りの成果だろう。最優秀男優賞もの、最優秀演出家賞ものだった。
(平成30年9月3日)
桜の下にて我死なん 
東京・下北沢の本多劇場で5月3日~13日に上演された加藤健一事務所『煙が目にしみる』はカトケンが女性、特に老婆を演じるのに興味を寄せるのみならず、人の死、死に方、死後の世界、さらに残された人々の想いを考えさせる(あるいは考えてほしい)ウエルメイド喜劇だった。
人は必ず生を終える。義経も信長も秀吉、家康も龍馬ら偉人、英雄も、シェイクスピア、ダビンチ、モーツァルト(と、個人的な好みの人物を挙げた)も満月に向かって駆け上がって(と、シラノ・ド・ベルジュラックの台詞をちょいと…)行った。死は避けられない。それを思い起こさせる芝居だった。堤康之の今作は歴史に名を残さない極く一般の平凡な庶民だか、物語の進行によって徐々に見る者に「自分も宇宙から消え去るのだ」と想起させる。
天宮良が演じた野々村浩介は妻、子供2人を残した中年男の死。新井康弘の北見栄治は若い愛人のような女性を忘れられずに逝った。その2人が幕開け、葬儀の日に顔を会わせる。あの世ではきっと無数の死者と出会うのかもしれない。死ぬ時期、死後の世界は誰一人分からないのだ。
残された家族の中でカトケンが演じた野々村桂だけは、その2人の姿が見える。息子の浩介だけではなく、赤の他人の北見さえ分かる不思議な73歳のバアさんだ。
浩介が妻の礼子に向かって生前の礼を言う。この終盤の場面が泣かせる。感動を呼ぶだろう。カトケンの出番は多くはない。ボケが進んでいるらしい(のかどうか)。他人の私生活に踏み込む気持ち悪い性分。参列した誰一人、死者が見えないのだが、愛する人を心から強く想えば生前の懐かしい姿、思い出が現れてくれる-。その姿が見えたのはやはり母だからか。野々村桂バアさんが一番、亡き人を想っていたのだろう。
舞台の背景には満開の大きな桜。死者の肉体が煙となって上がっていく。目に染みるのは煙り、そして桜。願わくば満開の桜の下にて我死なん。劇場を出る時、我が家族よ、友人たちよ、姿を見せろ!と星空を見上げた。
【写真】「煙が目にしみる」。左から山本郁子、吉田芽吹、久留飛雄己、伊原農、加藤健一。撮影・石川純
(平成30年5月24日)
蒼井優と生瀬勝久の演技は? 
新国立劇場小劇場の特設ステージで上演されたジャン・アヌイ作『アンチゴーヌ』が傑作だった。
殊勲甲の第一は栗山民也の演出、その第二はアンチゴーヌの蒼井優、その三はクレオンの生瀬勝久である。
舞台を四方に囲んだ客席、その舞台はまるで廊下のように長く伸びた長方形。装置は椅子のみ。それは見る者に想像力をかきたて、台詞劇であることを明示している。栗山演出は俳優の台詞一つ一つに明確な意味を持つように語らせる。シンプルな舞台で緊張感のある演技を求めたのである。
蒼井のアンチゴーヌは「私は清らかよ」とうそぶきつつも、男のベッドへ行く少女である。姉と話し合う時は強く、きつく台詞を吐き、この姉を嫌っているように演じる。鬼のような顔つきになる。男に馬乗りとなり、局部同士を合わせるように抱き合う。そんな演技の蒼井はまるで相手と話していないようなしゃべり方をする。この摑みどころのないアンチゴーヌ像を造り上げた。
生瀬のクレオンに注視した。
これまで演じてきた生瀬の役柄とは一線を画す人物なのである。
アンゴチーヌと二人だけの長い台詞の応酬がある。この時の生瀬が印象的なのだ。なぜって、その顔、その顔つき、表情がステキなのだ。王としての怒り、悩み、孤独に生きる王の心情。それがギョロつく眼に集中される。従って顔には強烈な心境が浮き彫りになったのである。こんな生瀬を見たことがない。
世界は不条理に満ちている。生き抜いて欲しい人間が殺され、死んで欲しい人物がぬくぬくと生き続けている。それは古代も現代にも違いはない。なぜ、悪でもない、罪深くもない人が苦しまねばいけないのか。神は答えてくれない。それを考えさせる舞台であった。
(平成30年1月22日)
岡本健一の新たな一面を見た 
演劇人・岡本健一の私的なイメージは、怒れる男、闘う男、牙を向いて相手に迫るといった役柄から生まれてきたと思う。小柄なハンサムボーイ、素敵な声質を持っている。調べてみると1985年にデビューのようで芸能界はもう32年目らしい。ベテラン俳優と言える。
三軒茶屋のシアタートラムで上演中の『クライムズ・オブ・ザ・ハート~心の罪』での彼の役は若手弁護士バーネット・ロイドだった。弁護士とは珍しいと思いきや、やはりひと癖ある人物を演じた。これが実に自然に見えたのである。
長女レニーが那須佐代子、次女メグが安田成美、三女ベイブが伊勢佳世。さらにこの三姉妹の従姉妹チックが渚あき。戯曲の作者ベス・ヘンリー、演出が小川絵梨子というオンナの匂いがプンプンの舞台である。その中でバーネットは、夫ザッカリーを銃撃したベイブの弁護をする一方、実は自分の父親を追い込んだザッカリーへの復讐を狙う男でもあるのだ。
岡本は復習の心中を明かす場面で激しい怒りを全身で表現するが、知的で温厚な弁護士を〝頭かな演技〟で演じた。静かとは人物を作り過ぎず、大げさに演じず、リアルな芝居という意味と考えて欲しい。岡本君、こんな演技もやるんだ!。
レニーの家を度々訪問し、スーツ姿でアタッシュケースを手にして玄関を出ていく。その繰り返しの芝居にピタッと嵌まっていたのである。健ちゃん、やるじゃないか!。
(平成29年9月15日)
エンターテイナー井上芳雄 
井上芳雄という俳優について考えた。というより再評価したいと思った。8月8、9日に東京芸術劇場プレイハウスで上演された『星の王子様』を見ての衝動だ。
この公演はストレートプレイでもなく、イベントでもなく、ミュージカルでもない。しかし、歌があり、芝居があり、朗読もあった。構成舞台とでも表現出来ようか。
井上は朗読からスタートした。飛行士としての朗読は実に正攻法。その後は6つの星の住人を演じていった。王様、うぬぼれ男、のんべえ、ビジネスマン、点燈夫、そして地理学者。この6役を衣装を素早く変えて次々と演じたが、その中で盛んな拍手を浴びたのが、うぬぼれ男だった。全身が金ピカの衣装、バカでかい金色の帽子。その前にやった王様から大変身したのである。膨大な台詞量をこなしながらワンマンショーのようだった。
長身で甘いマスク、のびやかな歌声。〝ミュージカル界のプリンス〟と呼称される井上だが、しかし、彼は単なる演劇人ではないと痛感したのである。それは問題意識や社会性を持つ演劇人であることだ。
たった俳優が3人、そして上演期間がトータルで3日間。そんな公演にも積極的に取り組む-。『夜と霧』も同様だったが、人権問題や差別、戦争の悲劇、弱者への寄り添いといった主題の作品の出演に意欲的。大劇場でのミュージカル主演の一方、小規模の公演にも出る。そのスタンスがいいのではないか。11・12月には『ダディ・ロング・レッグス』の出演が決まっている。エンターテイナー井上芳雄の光る才能のオンパレードに益々、期待したい。
(平成29年8月28日)
大竹しのぶは“まじょ”だったのです 
大竹しのぶは“まじょ”である。魔女ではない。芝居の「間」がいい“間女”である。
その彼女が還暦に当たって演じたいと考えて取り組んでいるのが新橋演舞場でのミュージカル『にんじん』〈27日まで。大阪・松竹座・9月1日~10日〉の主人公フランソワ。14歳の少年だ。
大竹しのぶは名女優である。映画、テレビ、舞台で多くの代表作を作り上げ、演じた役柄の幅広さ、巧みな演技術で長く観客を楽しませてきた。名優の条件である。『にんじん』は彼女が22歳の時の1979年に初演した作品。22歳で14歳の少年を演じた時、そして60歳で同じ役を再演した。果して14歳に見えるのか? そんな事は問題ではない。彼女が「にんじん」と呼ばれる少年を演じるのを見ればよいのである。
姉と兄がいる末っ子のフランソワは髪の毛が真っ赤でそばかすだらけ。母親が「にんじん」と呼ぶから家族もそう呼ぶ。何というひどい家族だ。両親の愛情を求めても応えてくれない。自分は本当の子供ではないのでは。首を吊ったり、バケツの中の水に顔を突っ込んで自殺まで考える少年だ。
「ボクはニンジンだ」と歌う時の哀しみ、母の声に全身で怯える姿、バケツの水を母から頭にかけられた恐怖。しのぶは2幕の冒頭での森の場面で歌う「世界一寂しい少年」が素晴らしい。絶望感、孤独感に溢れる。鏡を見て浮かべる百面相のような色々な表情、そして銀貨を盗んだと母に疑われた表情、台詞、仕草による「間」の演技を見て欲しい。
さて、蛇足を-。
「大竹しのぶお好み御膳」という献立があるので紹介しよう。
①八寸(にんじんといんげんの肉巻き。無花果と茄子のサラダ・にんじんドレッシングがけ。生ハムとブロッコリー。フィンガーシュリンプのサクサク醤油ココナッツ添え)②焼物(パテドカンパーニュとキャロットラペ。鮭とアスパラのミモザ焼・茗荷添え)③御造り(鯛・サーモンの海鮮カルパッチョ・特製にんじんソース掛け)④御飯(蟹と錦糸卵の祝祭ちらしごはん・にんじんさつま揚げ添え)⑤吸い物。
舞台である南フランスの田舎の風が伝わる料理だ。
(平成29年8月7日)
演出家・福士誠治、合格! 
「初めての挑戦です。演出家・福士誠治、発進いたします!」。公演チラシに元気の良い挨拶文を載せた俳優福士誠治の演出家デビュー作『幽霊でもよかけん、会いたかとよ』(作・金沢和樹)を見て、「演出家、合格!」という太鼓判を押したいと思った。
下北沢の小さな小さな劇場、駅前劇場で8日間、わずか12回の公演。ギッシリ超満員でも恐らく持ち出しになるだろう。人情噺が大好きという福士が脚本の金沢にリクエストした家族の物語。亡くなった母の四十九日を前に、父が寝言で繰り返す「幽霊でもいいから、会いたい」を兄と妹が実現させる-。シンプルで分かりやすいが、誰でも願う本音。
18歳から役者を始め、33歳になって演出を決意して、自身も舞台に立った福士の夢が丸ごと詰まったと思わせる芝居だった。優しい心を持つ彼の世界だった。
父を演じたのが渡辺哲、兄が駿河太郎、妹が貫地谷しほり。この他、伊嵜充則、大竹浩一、清水俊、金沢和樹、いのさわようじ、そして電気屋を演じた福士。出演者をすべて書いたのは、それぞれのキャラクター、個性を十分に引き出し、それをドタバタ喜劇の方向ながらギリギリの地点で羽目を外さない演出の目が通っていたからだ。
プログラムを読むと、稽古場の雰囲気作り、懇切丁寧、演出家と俳優が言いたいことを言い合う稽古だったと皆が福士の演出を認めていた。その通りの舞台だった。
母は幽霊だと信じ込ませるため愛犬を演じた駿河、母の役にもなった貫地谷を始め、舞台で腕達者の俳優がイキイキと演じていた。福士もノリにノッたコメディアンのような芝居を見せた。アイデア豊富な演技、場面の連続だが、恐らく出演者のアドリブを丸々採用したのだろう。
開演時の告知は福士も自身。開演前まで流れた坂本九の歌声。それも全曲、九ちゃんの歌である。当方は懐かしくて嬉しくて、聞き入ってしまった。しかし、なぜ九ちゃんオンリーかと考えていたところ、やはり劇中で母が九ちゃんの大ファンだったという設定だった。
決断力があり、仕どころを作って俳優を自由に動かし、面白いホームドラマに仕上げた。機会があれば再度挑戦したいという福士の演出。福士君、次ぎはチェホフだ。
(平成28年12月29日)
『ノートルダムの鐘』の感動とは? 
劇団四季の新作ミュージカル『ノートルダムの鐘』は間違いなく今年のベスト1ミュージカルだ。驚き、感動で胸が熱くなった。何回、涙が溢れたろう。その全ては主人公カジモドにある。
「美」と「醜」の概念とは何だろう。美しいとは何を指すのか。また、醜いとは何か。原作者のヴィクトル・ユゴーはなぜカジモドという名前を与えたのだろうか。「出来そこない」などの意味がある名を-。舞台を見つめながら脳裏を過った。
カジモトは生まれながらに体が不自由だった。背中は曲がり、足を引きずる歩行は正常ではない。人は平等にこの世に送り出される訳ではない。美しく生まれる者もいれば、皆が長身であるはずもない。宿命があるなら、それを背負って生きねばならない。1幕1場。「陽ざしの中へ」をカジモドは歌う。夢が叶うなら、一日でも街で暮らしたい。大聖堂の鐘楼で生きてきた鐘衝き男。この鐘楼が彼の宇宙だった。そこから出て、青空の下、陽光を浴びて人々の中で空気を思い切り吸い込みたい。世界を知りたいという彼の夢、希望はほんのささやかなものだ。この場面は感動させずにはおかない。
見どころはたくさんある。しかし、宿命の中で生き、叫び、愛を求めるカジモドを直視するだけで、名作と分かるだろう。その主人公を演じた海宝直人を褒めて褒めても足りない。『オペラ座の怪人』といい『美女と野獣』といい『ウイキッド』といい、四季は泣かせる主人公をまた生み出した。
(平成28年12月20日)
ケラの新作『キネマと恋人』 
ケラリーノ・サンドロヴィッチ(以下略してケラ)と中津留章仁の舞台作品を観劇する場合、覚悟が求められる、と私は覚悟している。上演時間が長い。集中力を欠くと、脳味噌にシワが寄るようだ。頭がクラクラする。理由は高齢だから。
ケラの新作『キネマと恋人』(シアタートラム)。休憩15分を挟んで3時間15分。制作側は“ファンタジックコメディー”に仕立てているとしていたが、私としては“ドタバタ・ナンセンスコメディー”に思えた(レッテルを付けるのは過去の職業柄で身に付いた方法論)。
夫の暴力に耐え、飯炊き女房の生活から一時逃れるため、映画館に通って夢を見る女を演じたのが緒川たまき、レストランで働きながら男に捨てられても次の男に走る女がともさかりえ。この姉妹に絡むのが妻夫木聡の映画俳優。他に村岡希美、三上市郎、佐藤哲ら芸達者な脇役陣が豪華。ウディ・アレンの映画『カイロの紫のバラ』に影響された、そして下敷きにした作品と書けば映画通なら想像できるだろう。
小劇場でこれだけの著名俳優と多くの俳優を巧みに演出した舞台。さぞかしお金がかかって赤字にならないか、と余計な勘繰りをしながら見た。
笑って楽しんでいた観客と違って私は一度も笑えなかった。30分は短縮できる、と計算しながら見た点もある。ケラにすれば絶対に欠かせないだろう場面のカットなどで短縮できると見えたからだ。巧みな演出と書いたがストップモーション演技、演じながらセットを素早く変化させる俳優、スタッフ、奇想天外なストーリー。いつも注目している緒川の摑みどころがない色気、妻夫木の優等生で清潔感がある芝居。しかし才気走ったケラの演出がなければ(ありえないが)、笑いは縮小しただろう。
一つだけ気付いた。いや、納得したのは俳優陣が皆、ケラの世界を楽しんでいたことだ。イキイキとしていた。後で思えば、ただ楽しめばいいのだった。
(平成28年11月23日)
美しさで映える檀、鮮やかな初舞台の剛力 
久しぶりに大劇場での本格的な商業演劇が楽しめた。11月4日に明治座で開幕した『祇園の姉妹(きょうだい)』(27日千秋楽)は実に初物尽くし。いくつかのその要素が相乗効果を生み出して、五感を刺激する舞台となった。
初物の第一の成果が主役の俳優だ。時は昭和十一年、場所が京都は祇園。梅吉、おもちゃという芸妓の姉妹が寄り添って生きている。姉の梅吉を演じるのか檀れい。宝塚歌劇の出身だから舞台経験は豊富なのだが、明治座へは初出演。妹・おもちゃは剛力彩芽。テレビドラマなどで注目された旬の人気女優だが舞台出演が初めてである。檀は舞台活動が25年目、剛力は女優デビューから5年目。このベテランと新進の共演が不思議に思えるくらい、溶け合っていた。
第二は丹野郁弓の演出だ。いわゆる新劇の三大劇団の一つ、劇団民芸の大黒柱。その彼女にとって大劇場での演出、商業演劇の名作の演出は初体験だった。
第三は松平健、山本陽子が重要な役で参加した公演になった成果だ。ともに舞台経験が豊富であり、大劇場で座長として主演を長く続けてきた大物俳優が脇に回った。これほど豪華な配役は初めてではないか。
檀は宝塚時代から美しい娘役だった。その美貌は歴代のトップクラスと言っていい。芸妓を演じる最初の出から幕切れまで、惚れ惚れとする綺麗な顔だちと表情、一幕で4回、二幕で2回披露した魅力的な着物姿はそれだけでも目を奪われた。特に裾引きの和服になると色気が沸き上がる。京阪の旦那衆が座敷に呼びたいと思わせる。明治座の広い舞台に映える女優だと認めたい。
姉の梅吉という女は古風な芸妓である。金では転ばない。好きな男には一途。自分は小学校止まりでも可愛い妹には進学させた。やはり芸妓だった亡き母の遺志を継いでいるのだろうか。「あんさん」と叫びながら花道を走り去る場面がある。倒産した木綿問屋の主人、新兵衛に恋の一途。姿を消してしまった男が忘れられない切ない恋心を声に込めていた。骨董屋の聚楽堂に体を迫られる場面がある。着物の裾を直しながら逃げ回る芝居では蛇から逃れるような、いかにも嫌だという顔で演じた。芯が強い女性になるのだった。
初舞台だという剛力には感心した。驚いた。一幕一場、梅吉の家。さあて、初舞台の最初の出番である。新兵衛の店、古沢商会が倒産したと仲居が飛び込んできた。「朝っぱらからなんの騒ぎですねん」。おもちゃの剛力は浴衣の寝巻姿。大あくびの口元を押さえながら出た剛力の初々しく、可愛く、そして跳ねっ返りの乙女が現れた衝撃。歌舞伎でも現代演劇でも同じなのだか、一番初めの出が大切なのは、その瞬間に役柄の性根を表現しなければならないからだ。京都弁の剛力は第一声から台詞の活舌がいい。大舞台の隅々まで届くような合格点。ここに感心した。
妹のおもちゃはお金こそ全てだと言い切る勘定高い少女である。嘘は平気。男を騙す商売が芸妓だと強弁する。一幕二場。言い寄る男の手を襟元に入れさせる場面がある。思い切った仕種だが、剛力は「男なんてこんな生き物よ」といった分かったような忍び笑いを見せた。体を張って生き抜くしたたかな一面を演じた。二幕一場。おもちゃは一幕で4回、二幕で2回、和装を披露し、この場でワンピースになった。その姿でハイヒールを履いて歩く場面があるが、履き慣れないので不器用にピョコピョコと急ぎ足。笑いを取る芝居が生き生きとしていた。将来が楽しみな若手舞台俳優の誕生と言っていい。
まるで水と油の姉妹。二幕三場が最高の見せ場だった。二人が今の状態、行く末を巡って悪態を付く。口喧嘩になる。長い台詞のやり取りが小気味いいのだった。
丹野の演出も褒めたい。幕開けからテンポが良い間合い、姉妹の性根を明示する役柄のメリハリがあって飽きさせない一場。幕前の芝居には花売りなど昭和初期の風俗を次々と出して、時代にこだわったのが効果的となった。キメ細かい姉妹の仕種も徹底したのだろう。これまでの役柄とは程遠い優男を演じた松平、亭主に去られても凛とした京女の意地を見せた山本。確かな役作りでこの二人が出ると舞台が引き締まり、奥深くなった。
商業演劇とは企業商品と見なした演劇の形態とされるが、目を奪う檀の美しさ、鮮やかな初舞台となった剛力は前進あるのみ、少なくなった女優が座長格の舞台の復権。収穫は少なくない。
(平成28年11月13日)
「ガラスの仮面」の一路真輝 
一路真輝と小西遼生がアフタートークにも出た9月19日の新橋演舞場『ガラスの仮面』を見て、チームワークがいいカンパニーであること、青山劇場での一昨年公演を上回る良い出来だったことが分かった。トークの中で二人が話した稽古の時の裏話が面白く、本公演にその稽古の成果が伺えたからだ。
月影千草の役の一路は伝説の作品「紅天女」を演じる場面がある。能面を付けて天女の美しい着物、打ち掛けの姿で舞う。二人のヒロイン、北島マヤと姫川亜弓が熱望する役柄だ。漫画のファンは見逃せないところだ。
クールな秘書、水城冴子を演じた〝コチマチ〟こと東風万智子は前回公演でも魅了されたが、歩く演技がステキ。まるでファッションモデルのように姿勢が素晴らしい。格好いい。
そして桜小路優の浜中文一。関西ジャニーズJrのメンバーだ。貴公子のような日本人離れしたマスク。フランス人かイタリア人か。欧米俳優とさえ見える二枚目だ。演技の骨格が出来てきたし、台詞回しをもっと鍛えれば、舞台俳優としてさらに期待できる。
姫川亜弓を演じたマイコは芝居がステップアップした。演じ分けの切り換えなど、大したものだ。
最後は貫地谷しほり。特にいいのがオーディションの場面で、与えられたテーマをいくつも演じる巧みさ。これこそ「紅天女」を完璧にやれるのは北島マヤだと納得させる。憧れる月影千草への愛、隠そうとして隠し切れない速水真澄への思い、ライバル亜弓への闘争心。「必要なのは自信と闘争心」。千草の台詞を体現していた。
(平成28年9月26日)
井之上隆志は名優なのだ 
知る人ぞ知る俳優だが、井之上隆志というバイプレーヤーは実に達者だなあ。巧い!そして面白いんだなあ。
池袋のシアターウエストで見た劇団道学先生による「丸芸芸能社の落日」(6月5日まで)で、彼の実力に改めて舌を巻いたのでした。
宮崎県の地方都市で映画館を経営する社長、丸山という役。「ただの老いぼれさ」などと吐くのだが、登場した瞬間からその存在感の濃さが目立つ。やや濁った声質で話す台詞は小気味が良く、テンポがあり、はっきりと聞き取れる発声術は際立っていた。
孫娘にプレゼントしたギターを弾く場面が驚きの一言。初めて見る人は目を回しただろう。情感が溢れる歌声、両足でリズムを取る仕種。こんな老人がこんなに上手に弾くのかと思わせる。
無料パンフレットに主催者で共演者の青山勝が「ますます熟成した葡萄酒のような滋味あふれる芸を存分に味わってください」と書いていた。小劇団の舞台で鍛え抜いてきた芸の持ち主。55歳。故中村勘三郎が目を付けたのがよく分かる。井上ひさし氏が花王おさむは名優なのだ-と書いたことがある。その伝で言うと、井之上隆志は名優なのだ。9月の「雪まろげ」での彼が待ち遠しい。
(平成28年6月2日)
寛美27回忌追善興行 
昭和中期の爆笑王、喜劇王と言えば映画の渥美清、演劇では藤山寛美に行き着くが、その寛美は平成2年5月21日に生涯の幕を閉じた。
新橋演舞場ではこの7月に「藤山寛美27回忌追善」と銘打ち「松竹新喜劇爆笑七月公演」を開催する。注目点は寛美の孫、藤山扇治郎が祖父の当たり役に挑む4演目だ。
5月30日に行われた懇親会。劇団の代表である渋谷天外が扇治郎の芝居についての表現がズバリ、的を射ていた。
「ワクワク、ドキドキ、どうなるんだろうと見ていた。スリルとサスペンスの芝居になるんです」。危なくて見ていられない…。「アホから入るな、心から入れ!」と指導した演技が、舞台に立つたびに「勝手にボケていきました。(祖父の)ビデオなども何度も見ているのでしょうね。(祖父のDNAが)しみ込んでいるんでしょう」
さて、ここであえて三つの助言をしよう。
もっともっと祖父のマネをしよう。マネでいいじゃないか。そっくりのマネが出来れば上出来だ。実は、そうたやすく出来るものではないからだ。
寛美の娘、扇治郎にとって叔母である藤山直美の芸を盗め。しっかりと観察して、物にしてくれ。
そして最後。劇団では天外を始め高田次郎、小島慶四郎ら大先輩の先生がいる。一方で、やるべきは映画、テレビ、あるいは舞台での喜劇を勉強することだ。映画監督や舞台の演出家に接する機会を自ら求めていくのである。
祖父も叔母も天才肌の役者。扇治郎には地道な努力こそ唯一、成功への道。まだ29歳、いや、もう29歳。足の裏まで演じて笑わせた祖父のように、見ていてワクワク、ドキドキするような芝居をしよう。
(平成28年6月2日)
蜷川幸雄と青山達三 
新国立劇場の『パーマ屋スミレ』で青山達三(たつみ)という老俳優を気にして見ていた。役柄は三姉妹の父親・高山(高)洪吉(コ・ホンギル)。次女の南果歩、その夫の千葉哲也ら主役陣の演技が注目されるところだが、当方は同時に青山にも集中した。。
観劇は初日の5月17日。この日は12日に永眠した演出家蜷川幸雄さんの通夜が15日に営まれ、翌16日が告別式。つまり青山は〝戦友〟の弔いを終えての初日であった。
劇団青俳出身の彼はその後、現代人劇場に加わった。蜷川さんと同時代を同じ道を歩みながら舞台俳優と演出家として戦ってきた仲間という訳だ。
青山が演じた父親の役は台詞が少なく、演技も多くはない。しかしながら、舞台に出ている時間は長いのである。東京オリンピックの翌年の1965年から始まる物語は、舞台が九州の炭鉱町で美容院を営んでいた次女一家を描く。
出番は開幕の前から。布団に絡まっている彼の禿げ頭だけが客席から見える。幕が開いても寝床からしばらく出てこない。ようやく起き上がっても無言で椅子に座ったり、時に動き回る。また時に広げた両手を高く上げて「万歳(まんせい)!」と大声で叫ぶ。
感心したのは娘たちの台詞をただ聞いているだけの芝居だ。家族の苦しみを一番理解している父親だからこそ、話さず、沈黙しても一家の長であり、家族を愛していることが分かる。派手な喧嘩をする姉妹、笑いを取る演出。青山には笑いは来ないし、目立たない存在。しかし、私には分かった。「蜷川さんが必ず見ていてくれる」。役柄を生き抜く演技をしなければ、笑われる、怒鳴られる-。
カーテンコールが、また、いい。静かで丁寧で気持ちが込められて頭を下げ続けた。
青山達三は蜷川演出の申し子である事を示していた。
(平成28年5月24日)
涙なくして見られない 
やっと見応えのある舞台に出会えた。世田谷パブリックシアター『イニシュマン島のビリー』だ。今年のこれまでのベスト3に入る作品だ。
劇中に映画を見る場面があり、ヘレンの台詞に「クソみたいな映画だ」と、いらつくのだが、その伝で言えばクソみたいな芝居が多い中、当方にとって一服の清涼剤になった。
私は一切笑わなかった。というより、笑えなかった。むしろ切なく、哀しく、涙さえ出た。主人公ビリーの生涯だ。生まれつき手足が不自由で、「びっこのビリー」と呼ばれ続ける青年。
両親に見離されても、必死に生きてきた。「びっこと呼ばないで」「ビリーと呼んで」と願っても島の住人は呼び方を変えない。悪意はない住人たちだが、やはり差別に聞こえてしまう。
ビリーにだって夢はある。演じた古川雄輝はハンデを背負ったナーバスな青年がピタリ嵌まった。
その他、お手柄はいくつもある。
登場人物の考え、性格、性分を浮き立たせ、それぞれの関係性をキッチリ描き分けた森新太郎の演出。次に技量、構成バランスが絶妙に組み合った出演者全員。オバさん役の峯村リエ、平田敦子がビリーに寄せる情愛、暴力的な少女ヘレンを演じた鈴木杏はこれ以上ない適役。鮮やかといいうか、生き生きと躍動した。山西惇は、巧い。面白い。憎い位だ。単なる情報屋ではなく、その場所でこう生きるしかないという男であった。そしてビリー。「神はなぜ私にこのような試練を与えたのか」。そう叫びたいのだ。
ブラックユーモアと暴力。マーチン・マクドナーのダークコメディとされるが、笑う場面など一つもなかった。笑っている観客が可哀相に思えた。
(平成28年4月12日)
カトケンの老人 
加藤健一事務所の前回公演『滝沢家の内乱』で老いた滝沢馬琴を演じたカトケンだが、昨年12月の『女学生とムッシュ・アンリ』(サザンシアター)ではフランスの老人に扮していた。
そのアンリじいさんは嫁が気に入らない頑固ジジイである。〝嫁と姑(しゅうとめ)〟と言うように女同士のいさかいが一般的なのだが、こちらは〝嫁と姑(しゅうと)〟。息子ポール(斉藤直樹)とヴァレリー(加藤忍)という嫁を離婚させたいアンじいリさん。そこへ女子大生コンスタンス(瀬戸早紀)が同居人募集に応じてやって来る。
人は年をとると、頑固で自分本位になるものだ。夫に先立てられようと、妻を亡くしても、自由にさせて欲しい、一人にして欲しいのである。何が孤独だ、不自由だ。居場所がどうなんだ。そういう老人だっているのである。
亡き妻が愛したピアノに触れようとしたコンスタンスをどやしつけるアンリじいさん。カトケンのその罵声が凄まじい。人生を伴にした楽しかった夫婦生活を汚して欲しくない。
ピアノのキーを、怪我をした左手のギブスの中に、あるいは植木鉢の中などに隠してしまう。 その一つ一つの演技が老人の苛立ち、いたずら心、その反面、閉ざしてきた心中を浮き出していた。
コンスタンスの瀬戸が弾くピアノの生演奏が巧い。15年ぶりに弾いたとは思えないのは稽古の賜物だろう。ただ、張り上げる高い声の台詞は老人には耳が痛い。高齢化社会に突入している我が国で、老人問題を描くのは分かる。それにしても、老人役が続いたカトケンにはやはり爆笑喜劇の方が似合う。。
(平成28年2月1日)
仲間由紀恵で復活した『放浪記』 
平成二十七年十月十四日、『放浪記』が復活した。森光子が演じた同二十一年五月二十九日の千秋楽以来である。
主役林芙美子が仲間由紀恵。出演俳優は全員初役。一新されたのである。6年を経て名作中の名作が日の目を見たことになる。なぜ復活出来たか。女優仲間由紀恵がいたからに他ならない。
「ただいま!」。第一幕、本郷の下宿・大和館。芙美子が薄暗い一間に戻って来た第一声。弾んでいた。『放浪記』の復活、そして仲間芙美子の誕生を告げる「ただ今、戻って来ました」と聞こえた。この第一幕から森光子版との相違を私的に列挙してみた。
一幕の幕切れ。伊達春彦に捨てられた芙美子の森は暗闇の中で横たわり、蓑虫のように体を足を縮め、悲しみ、悔しさを全身で震わせて演じた。仲間の場合、押し入れの中から泣き声が聞こえてきた。泣き顔などの表情、体の演技は見せないのである。観客は想像するのだが、一つの行き方だろう。
次ぎは二幕一場。カフェーの女給の場面だ。森はここも良く知られたように、どじょうすくいを見せた。上手の端から「あら、エッサッサ!」と出ると、下手に踊り込んでいく勢いが何とも言えない味。仲間も変わらない。若さがあり、元気一杯の軽妙さだった。
三幕・尾道の家。特に家の外の浜辺。ここは森が渾身の演技を放った名場面だ。初恋の人、香取恭助との仲を断ち切る女心。石段を上がる一歩一歩に神経が行き届いた演技。芙美子という女の悲しい運命が立ち昇った。仲間にはその石段が登場しない。見たかった。
そして四幕二場・渋谷の木賃宿。語り種となった森のでんぐり返し。仲間は側転、続いて飛び上がって喜ぶ連続技。G難度だろうか。いわゆるケレン味を打ち出した喜びの爆発である。
最後はカーテンコール。開幕2日目は直立し、一礼する挨拶だった。実にシンプル。物足りないと思う人もいるだろうが、これもこれで良い。
他で良かったもの。若村麻由美の日夏京子、若杉宏二の上野山光晴、古川けいの女将・くら、梅原妙美の隣人・村野やす子。新しく船出した『放浪記』は、改めて名作中の名作だと再確認したのだった。
(平成27年11月8日)
女優が魅力的な『グッドバイ』 
太宰治の原作をケラリーノ・サンドロヴィッチが脚本・演出した『グッドバイ』を世田谷・パブリックシアターで見た。
主演の仲村トオルが演じた田島周二が太宰とおぼしき人物。「行進」と称した、愛人と別れるための旅を続けるのだが、七人の女優が出演する。その中の四人がステキなのだった。
最初に小池栄子。抜群の存在感。ただただ感心した。かつぎ屋の永井キヌ子という役は田島から依頼されて嘘の女房になりすまし、愛人回りに同行する。すごい美人だから、愛人は諦めるだろうというのだが、行進の途中、怪力で大食いの彼女は食べまくり、田島に散財させる。食べるその速度、コンテストでも優勝しそうな大量の食べ物をパクつく豪快さ。パワフルな女性が実に自然な演技で、こんなに巧い女優だったとは。
次は池谷のぶえ。6役を演じ分けた。田島と本妻・静江との間の娘・幸子、老婆、正ちゃんという男性、ホステス、易者…。兼ねた役が一番多いのにどれも好演。あえて挙げるなら、まだ子供の幸子はスカートの中のパンツ丸出しで親の会話に鋭く反応する芝居や、脳味噌がちょっぴり足りないような正ちゃん。戦後の昭和には街々に居たが、例えば「男はつらいよ」で佐藤蛾次郎が扮した源公に似たタイプだ。これが巧い。
三番目が緒川たまき。彼女の場合は4役の中で女医の大櫛加代に魅入った。もともと美しい声の持ち主だが、歯切れの良い台詞回し、白衣を着た抜群のスタイルは知的。こんな愛人が欲しい、と男は思うのである。
四人目が水野美紀。彼女も4役の中で、妻の静江がいい。女優陣ではピカ一の美形。田島との別れ、田島の知人である文士の連行(山崎一)と再婚する。別れ話をする場面での大声など、品良く艶やかな女を怒らせると恐いぞと思わせる。
小野寺修二が振り付けた幕開きでは反り身のスローモーション演技をそれぞれが見せ、危うさと決意を示す。そして、戦後の昭和23年当時、そこには逞しく生き抜こうとするオンナたちが居たのである。
【写真】撮影:引地信彦
(平成27年10月1日)
カトケンの馬琴 
カトケンの振り子は笑いの右に揺れればシリアスの左にも揺れる。振り幅が広い。要するに芸幅が広い俳優である。
2011年以来の再演となった加藤健一事務所『滝沢家の内乱』は二人芝居。加藤健一が滝沢馬琴、加藤忍が息子・宗伯の妻お路。大作「南総里見八犬伝」を脱稿するまでの15年間の一家の生活ぶりが物語だ。
馬琴が籠の中のカナリアに餌を与える幕開きの場面がまず面白い、と見えた人は少ないかもしれない。餌を与えるまでの間(ま)、その表情。筆一本で家族を支える当主の苦労と一瞬の安らぎを演じる巧さに気付いて欲しい。食事の場面はカトケンの本領発揮だ。
固い、苦い、酸っぱい、温かい-と文句たらたらの老け役に当方は心の中で手を叩いた。焼いた鰯が固い、年をとると酸っぱいのに敏感になる。温い味噌汁など食えるか。少ない楽しみの一つの食膳に苛立つ老人の本音である。
そんな右に揺れた笑いに対し、満天の星空の下、屋根の上に登って己の今を想う馬琴の芝居。大宇宙の下で這いずり回る人間という生き物の虚しさ、何かを残して消え去りたいと願う大作家の姿を浮き出す。これが左に揺れたシリアスな芝居だ。
カトケンは左右の真ん中で演じていた。
お路の加藤忍がこれまた、巧い。嫁となったばかりだから滝沢家のしきたりに戸惑う。反発する。病身の夫が亡くなり、こうるさい姑もあの世に旅立った。視力が衰えた馬琴に口述筆記を申し入れ、漢字を覚えながら成長していく変化が明確に分かる演技だった。
実力のある俳優の二人芝居。前回を上回る良質の演劇がそこにあった。
【写真】左より加藤健一、加藤忍(撮影:石川純)
(平成27年9月2日)
仲間由紀恵の覚悟 
森光子の代表作であり、我が国の演劇史上で最高作品の一つである「放浪記」の制作発表が8月16日に開かれた。
森光子と言えば林扶美子と谺が返る決定版の主役に挑む仲間由紀恵にまず拍手を送る。辞退しても一向におかしくない難役。2017回を演じた森の魂が乗り移っている林扶美子だ。
「この度、林扶美子という大役を頂戴しました仲間由紀恵です」。最初の挨拶に覚悟が込められていた。もぎ取ったとか与えられたとかの意味合いではなく、頂戴したという謙虚さがむしろ炎のような覚悟に見えたのである。
勇気ある決断だろう。
「長年大事にされてきた『放浪記』という大変な作品の出演のお話をいただいた時、光栄、緊張、不安といろんな思いで大変でしたが、今はワクワクとした気持ちも出てきました。森さんの意志を受け継ぎ、汚さぬよう、そして役者としてまた一歩成長出来ればと思っています」。これが二代目扶美子への決断理由だった。
杉村春子と言えば「女の一生」といわれた名舞台も今だ杉村と並び、超える舞台は生まれていない。当然だ。不世出の名女優の名舞台を超えるのは容易ではない。仲間にしてもそれは百も承知の上だろう。
渋谷の木賃宿で演じられた名場面の「でんぐり返し」を入れるかは稽古の中で決めるという。演出の北村文典が「やるなら四回転半」と目が回るようなギャグを放ったが、是非ともでんぐり返るべきだ。森光子は私に「一に本、二に本、三、四がなくて五に本」と、脚本こそすべてだと言った。仲間の勇気と覚悟があれば、きっと見事な場面が再現出来るはずだ。
(平成27年8月17日)
負けるな、ジジイ3人組 
演劇の興行とい言う視点で注目したいのが、男優3人の主演による商業演劇の成果、もう一つが男優の現代劇での実力の評価だろう。
その舞台が「三匹のおっさん」。9月4日開幕の明治座から始まり、中日劇場、新歌舞伎座、博多座、さらに広島、高松の12月1日までの長期公演だ。
主演は年齢順に並べると柔道の達人を演じる西郷輝彦(68)、剣道の達人松平健(61)、機械いじりの天才、中村梅雀(59)。大ヒットとなった小説の初舞台化、人気を集めたテレビ化で知られるが、還暦・定年を迎えた、かつての悪ガキ3人組が自警団を結成し、町内の事件を片づける物語だ。
7月27日の制作発表。
「ナマの方が面白かったといわれる作品にしたい。空気のような夫婦、家族の絆を思い知らされる話もあります」とは松平。
「団塊の世代の気持ちを分かっている作家(田村孝裕)。テレとプライドを持って、行ったり来たりの物語」とは西郷。
「還暦を迎えた世代への応援歌」と話した梅雀は、8月21日に出産予定の初子となる女の子の誕生を初公表した。
女優の座長公演にしても、男優主演の舞台にしても今は大劇場での興行が激減する中、果たして男優3人の主演舞台は珍しい。今回の俳優3人が共演するのは初めてというが、明治座の冒険は演劇界全体で注目される。
3人の舞台経験に文句を付けようがないが稽古期間を含めると4か月に及ぶ仕事になる。松平と西郷は普段からウオーキングを続けているという。梅雀は地方公演に出た時、熊の肉とか馬刺しを食べた効果が第一子誕生への呼び水になったそうだ。
心・技・体、三拍子揃った時、おっさんの舞台は愉快になるに違いない。
(平成27年7月29日)
唯一無二の幸四郎 
松本幸四郎のミュージカル「ラ・マンチャの男」が3年ぶりに上演される。9月の大阪、松本公演を経て、東京・帝劇の初日が10月4日。一般のファンも参加した7月2日の制作発表に出向いた。歌舞伎とミュージカルの作品を最高水準の演技で演じ切れる主演俳優は日本はおろか、世界中で唯一、幸四郎だけだ。しかも、ブロードウェイミュージカルの最高傑作「ラ・マンチャの男」の主役ドン・キホーテなのである。
初演から47年目。公演中には73歳となる〝老優〟の若々しい舞台が蘇る訳である。
会見での幸四郎語録を噛みしめてみよう。
「皆様のおかげでまた『ラ・マンチャの男』の灯が灯りました」
「73歳という年になる公演。普通なら同級生と一緒にゴルフやゲートボールをやっている年。しかし幸四郎は稽古場で汗を流しています」
「原動力は、皆さんに支えられてきたことの一言です。この作品に勇気付けられてきたのが正直なところです。父、母が死んだ時も『見果てぬ夢』を歌っていました」
「最近思うことは、手に職を付けること。職人にならなくちゃいけないということです」
「歌舞伎の役者は何でもやる必要はないけれども何でも出来なければいけない。俳優も同じだと思います。きっと、そこそこではなく、トコトンやってきたんでしょうね」
「人に感動と勇気を与える仕事をしているんだ、幸四郎!-と思ってやっています」
公演チラシに「ブロードウェイ・ミュージカル日本上陸から50年。未だこの幸四郎の『ラ・マンチャの男』を超えるミュージカルはない」(演劇評論家・安達英一)という一文が載っている。私の大先輩、安達さんは今年3月19日
、他界した。カラオケで英語で「インポッシブル・ドリーム」を歌うのが自慢だった。
会見でその歌唱力を披露する幸四郎と重なるのを覚えながら、当方もあるべき姿のためにちょいと闘うとしようかと、狂気の気分を味わったのである。
(平成27年7月13日)
魅了する藤原紀香 
抜群のナイスボディだけではなく、歌と踊りにと、たっぷり魅力を振りまく藤原紀香。ブロードウェイ・ミュージカルの傑作「南太平洋」が東京・北千住のシアター1010から開幕した。
第2次世界大戦のさなか、南太平洋のとある島の海軍基地。彼女が演じるのはその基地に派遣された看護婦ネリー。詳細は4月2日のこのコーナーで紹介しているので割愛するが、第1幕で6曲、2幕で4曲と、名曲「魅惑の宵」などを歌った紀香。ソフトな声音、伸びやかで歌詞の本質を伝える歌唱力は予想を超える出来だった。
水兵服は初々しく、水着でシャワーを浴びたり、ビーチウエアで舞台を走り回ると目のやり場に困るような生々しい色気。その舞台は彼女の歌唱ショーであり、ファッションショーであり、つまり紀香の魅力を詰め込んでいた。
フランスの農園主エミールを演じた別所哲也は定評のある歌声を披露し、設営部隊のルーサー役の太川陽介は女装したダンスを見せてお笑いを受け持つ。
1950年度のトニー賞9部門で受賞した作品は古き良き名作ではあるが、作曲リーチャード・ロジャース、作詞オスカー・ハマースタインⅡ世という名コンビの名曲が心地良く、それを堂々と歌い切る紀香の才能と度胸は並ではない。
(平成27年7月13日)
清々しい沢口靖子の「台所太平記」 
東京・浜町の明治座で上演中の「喜劇・台所太平記」(6月4日~同26日)は主演・沢口靖子のキュートで清廉な芝居に加えて、戦後の昭和の懐かしい原風景が見られる上質な喜劇になった。
今年は文豪谷崎潤一郎の没後50年。その谷崎の原作だが、晩年の谷崎家で働いた女中さんたち、今で言うお手伝いさんと谷崎一家が織りなすホームドラマでもある。
時代は昭和33年秋から38年春。沢口が演じる初江は鹿児島の貧しい漁村に生まれ、仕事を求めて谷崎家の押しかけ女中に成功する。意地悪な先輩たちに揉まれながら勉学に励み、やがて谷崎家から嫁に出る。幸せを見つける中、自我を確立していく成長物語と言えよう。
沢口の癖のない素直な演技が清々しい一方、谷崎の傑作「細雪」の舞台化で馴染みの高橋惠子、南野陽子、川崎麻世、永吉京子が脇を固め、谷崎を演じる古谷一行とともにチームワークの良さで舞台が弾んでいる。
そして女中部屋に置かれた白黒テレビの前に集まる人々、東京タワー、ミッチーブーム、フラフープといった昭和30年代のキーワードが続々と登場するのは懐かしい限りだ。
ちなみに筆者はプログラムに「食べる名人、谷崎潤一郎」という一文を寄せている。観劇の際、一読いただけると嬉しい。
(平成27年6月15日)
「アラジン」の魔法力 
劇団四季の大型ミュージカル「アラジン」が四季劇場・海で5月24日開幕した。
ディズニーとの提携5作目。久しぶりの新作であり、浅利慶太氏の名前がスタッフとしてプログラムに載らない驚きの公演。四季にとって新たな第一歩の始まりである。
見どころはいくつもあった。
幕開きのナンバー「アラビアン・ナイト」は魔人ジーニー中心に実に10分間と長い場面。男性9人のラインダンスや女性6人のエロティックなダンスなどが組合わせられ、ジーニーが魔法のランプを出す前、浅草・雷門の赤提灯を使うギャグもあった。。
ランプが置かれた魔法の洞窟の場面は圧巻。金色に輝く洞窟には宝石が溢れ、白煙とともにジーニーがランプの中から浮き上がる仕掛けは意表を突く。魔法の絨毯に乗ったヒロインのジャスミンと主人公アラジンが宙を走るファンタジーには心躍る。
初日終演後のパーティーで日本版独自の演出が明らかになった。①洞窟の金色は石川・金沢にある細工技術を活用した②両手に嵌められたジーニーの手錠が一瞬に解かれる手法③アラジンが窃盗を止めるのは亡き母への思い。大好きな母の自慢の息子になる誓いだった。オリジナルを加えた効果は親近感に繋がった。
アラジンの島村幸大、ジャスミンの岡本瑞恵の歌、踊り、演技に合格点を出せるが、さらに魅力を付けて欲しい。強烈な個性だ。その点、ジーニーの瀧山久志は一人で舞台をさらった。「アラビアン・ナイト]から弾ける躍動、ランプの中に閉じ込められて自由を失った悲しみ。抜群の存在感だった。
向こう1年間の予約は埋まりつつあるが膨大な制作費を回収出来るか。「ライオン・キング」を超えるか。四季の試金石が始まった。
(平成27年6月2日)
いつも明日を見つめる「アニー」 
ミュージカル「アニー」。幕開けの場面はいつも泣いてしまう。孤児7人のベッド。静寂の中、既に「メイビー」の曲が流れている。と、アニーが歌い出す。一番小さいモリーを抱き、[強く抱きしめて]。アニーは両親に捨てられたのには絶対に理由があると思っている。他の孤児も同じ気持ち、それをアニーは歌うのだった。
意地悪そうに見える6人の孤児だが、一人一人は皆が個性を持っている。その証拠にこの作品の子供の頭文字を全て変えている。A、M、J…。
ミュージカルで必ず泣いてしまう場面があるのは少ないものだ。この「アニー」の冒頭と、もう一つは「オペラ座の怪人」だ。ファントムが求めるのは、愛。醜く生まれた自分の不幸、不運。父の、母の愛を受けなかった人生。それでも恋しい人、また愛を求めて歌う「ファントム・オブ・ジ・オペラ」。愛情を求めるのは子供も大人もない。
さて、30年目を迎えたミュージカル「アニー」。閉場となった青山劇場から新国立劇場に会場は変更されたが、発進するテーマは不変だ。
初演は1986年。その翌年の第2回・1987年、ニューヨークのコッチ市長のオフィスで「トゥモロー」をアニー役二人は歌った。菅野志桜里と西部里菜、そしてグレース役の鳥居かほりがキャンペーンで訪米。その時、同行取材したのだった。
当時、ニューヨークは「アイ・ラブ・ニューヨーク」のPR作戦の真っ最中だった。大声で「トゥモロー」を歌う子供二人を見ながらコッチ市長の満面の笑みは忘れられない。
初演前、マスコミを集めた発表懇親会が開かれた。ある大手新聞社のベテラン記者は「今の時代、孤児を主役としたミュージカルが成功するだろうか」と否定的な質問をしたのも思い出す。アニー役のオーディションに大多数が応募。選ばれたキッズ役には猛特訓をして第1回は大成功だった。
親を思う子供の心、愛情を求めてやまない気持、そして世界で貧困に苦しむ子供が存在する現実。30年前と一向に変わらない世界である。子供には常に幸せであって欲しい。「アニー」はこれからも長く続いてもらいたい。
(平成27年6月1日)
加藤健一と風間杜夫のバトル 
加藤健一事務所が3年ぶりに「バカのカベ・フランス風」を再演した。本多劇場の4月24日を皮切りに6月30日までの旅公演を打ち抜くロングランだ。
加藤のフランソワ、風間杜夫のピエール。初演での2人の共演は確か30年ぶりではなかったか。つかこうへい演劇でのバトルを強烈に覚えている世代にとっては胸がジーンと高鳴る思いだったものの、正直言って今回の再演ほど笑える喜劇ではなかったと記憶している。あの大震災からの傷が胸を痛めていたからだろう。
初日を見た限り、カトケンワールドに久しぶりに大笑いが戻って来たと思えた。
加藤と風間の実力を再認識したからである。2人の演技は巧い。抜群に巧い。
選び抜いたバカ者をパーティに招いて笑い者、食い者にするという悪趣味なピエールと、へまばかりをする変わり者でマッチ棒細工が趣味の国税庁に勤めるフランソワ。ともすれば単なるドタバタ喜劇だけに終わりそうな物語だが、2人の芝居が数倍の笑いを生み出すのである。
福島、宮城を始めとする陸奥の悲惨さを我々は忘れていない、と思う。一方、そろそろ笑いを取り戻してもいいだろう、と感じる人もいる。
加藤と風間の演技は舞台で人間喜劇を演じ、それを見て笑ってもらいたい-その一心だった。一切の妥協はなかった。その証拠に人間は愚かな生き物であり、愚かであるからこそ人間なのだというメッセージさえ映し出していた。
ギックリ腰になった風間がギクシャク、ヒョコヒョコと登場した冒頭や、倒れた風間の背中に思い切りのしかかった加藤の絶妙の演技など見どころは多い。しかし、喜劇としては決して演じていない2人の実力者。初演をはるかに超えた〝闘う俳優〟がそこに居た。
(平成27年4月27日)
ボディだけではないぞ、紀香の才能 
ミュージカル「南太平洋」の制作発表(3月31日)で主演の藤原紀香をじっくりと観察した。
今夏、全国12都市で上演される巡回公演、役柄は従軍看護婦ネリー海軍少尉。「ぜひネリーと言われた時、とてもプレッシャーがあったけれどやっぱり素敵で魅力的で、もう一度脚本を読んだんです。ときめき、ワクワクしながら普段行けない地域へミュージカル、舞台、生の楽しさを伝えていきたい」。最初の挨拶から嬉しさ満面だった。
質疑応答では私がしたかった質問を小藤田千恵子さんが投げてくれた。ミュージカルの舞台についてだ。
「まだヒヨっ子で、毎日、色々な作品で自分を高めていく修行のような。声が出るかどうかから目が覚める一種、恐怖から始まる一日なんですね。舞台に出ると震えるような感覚、潮の満ち引きを感じます。他では感じられないものがあり、大好き。やるたびに試されている、裸で見られている厳しい場所です。舞台では出る役者のもので、度胸だけでなく鍛えられるお仕事だと思っています」。実に謙虚で、巧い表現力、熱い思いではないか。それは歌、踊り、演技によって作品や役柄を伝える難解さを充分に理解しているからだろう。
「歌の個人レッスンを始めています。この作品の見どころは歌だと思う。私が思っている気持を歌詞に反応してもらった。歌っているとネリーになっているんです」
海軍の制服、看護婦の白衣、海辺でビーチウエア、サマードレス、ダボダボの水兵服。水着姿はどうなるのか。
「1950年代を調べるとデザインはプリントとか可愛い。お腹は出ていないけど短パン。ストライプもあるし、花柄もある。その中から純白の華やかなストライプになると思います。シャンプーしながら出てきます」。
島へ行った経験についてはこうだ。
「ある太平洋の島で鞍を載せていない裸の馬に水着で乗って泳いだことがあります。右手でたてがみをつかみ、左で体を抱くようにして泳いだ経験。それがとても素敵でもう一度行ってみたい」。
島の女メリーで共演し、声楽指導も担当する、ちあきしんの説明で紀香の才能が少しだけ理解した気がする。「普通、声や音程から入る人が大半ですが彼女は自分の表現したい気持ちから入る。それが素晴らしいんです」。紀香にとって「キャバレー」以来約3年ぶりのミュージカル。才色兼備の43歳とは驚き桃の木、山椒の木だ。
(平成27年4月2日)
宮沢りえの笑い 
ケラリーノ・サンドロヴィッチ演出「三人姉妹」の登場人物はよく笑う。
食材で論争すれば、生活に苛立ち、他人を怒り、愚痴り、100年後200年後の人々の生活を想像して哲学もする。長女オーリガ(余貴美子)、次女マーシャ(宮沢りえ)、三女イリーナ(蒼井優)だけでなく皆が話の渦に巻き込まれながら、笑うのである。
陸軍中尉トゥーゼンバフ(近藤公園)は大尉ソリューヌイ(今井朋彦)の辛辣な哲学を聞くと、気味の悪い笑いだ。長男アンドレイ(赤掘雅秋)も暗い笑いがある。皆で食事をする場面では陸軍中佐ヴェルシーニン(堤真一)が高笑いをしている。
そして次女マーシャだ。ヴェルシーニンから愛の告白を受けた時と哲学じみた話を聞く時など都合3回、それぞれ違う笑い声を出すのだ。
プログラムで宮沢りえは話していた。
演出のケラから「聞いたことのないような笑い声で笑ってください」。どう書けばいいのか。愛の告白を受けた時の笑い声など、聞いたことがなかった。
小道具も重要な役割をしていた。
1幕の最後。西洋駒がクルクルと回って、回り切って倒れていく中で幕になる。次が本だ。
マーシャの夫クルイギン(山崎一)がプレゼントした50年史をヴェルシーニンは無視する。マーシャは小説を読む。アンドレイは床に叩き付ける。本が効果的に演出されているのだ。
正攻法で押し抜いたケラの演出。しかし、登場人物は皆、面白い。少し、奇怪しい。それが笑いと本とでも描かれたのだった。
(平成27年3月2日)
ありのままにィ! 
日生劇場で上演中のミュージカル「ラ・カージュ・オ・フォール」(2月28日まで。3月6~8日は梅田芸術劇場)は1985年の日本初演から30周年の区切りの公演だ。
世界初演は1983年8月、ブロードウェイのパレスシアターだった。当方はその年だったか翌年だったかにその初演を見ていた。遠い昔のことで記憶はおぼろ気。覚えているのは、女装のゲイダンサーたちが横一線に並んで振り上げた長い足が顔の後ろまで届いたように見えたこと。驚いたもんだ。そこまで足が上がるのか!
日本初演の1985年2月。確かその年の1月か前年の12月だったか、発表イベントを取材していた。ジョルジュが岡田真澄、アルバン(ザザ)が近藤正臣。会場は六本木にあった以前のテレビ局NET(現テレビ朝日)の別館。近藤が長い時間をかけて化粧を続け、待ちくたびれた頃、美しいドレスを付けて現れた時、見事に美しい顔の近藤ザザになっていた。
何が言いたいかって? ブロードウェイの初演も日本初演にも思い入れが強いミュージカルだということ。
そして30年。市村正親のザザ、鹿賀丈史のジョルジュのコンビは最高だ。ザザへの深い愛を鹿賀は益々深めてきた。本物の母にはなれないザザの市村は、偏見や差別に耐えてきた人生、嘘のつけない本当の自分を愛し、生き続ける悲しみと喜びを歌い込めてきた。
「ありのまま」に生きる人々。
ああ、ありのままを持続する困難さと努力よ!
【写真】鹿賀丈史(左)と市村正親
(平成27年3月2日)
井之上隆志は名優なのだ! 
村田雄浩、青山勝が主役の兄弟を演じてフィーバーする劇団道学先生の公演「あつ苦しい兄弟・港のふたり編」(2月6日~15日、シアターイースト)。熟達した俳優がズラリと顔を出して、さながら個性合戦。
その中でも井之上隆志には舌を巻いた。さすがに故中村勘三郎が仲間に呼んだ達者な芸を見た。
宮崎のさる港町で海運会社の社長。ダンス大会に賞金30万円をポケットマネーでポンと提供し、その賞金を狙って4組の出演者が大騒ぎをする。井之上は釣りをする場面、ダンス大会を見つめる場面などで光る演技を披露したが、吉田拓郎の曲をギターをかき鳴らして歌うシーンがあった。
スナックを経営する役の桑原裕子が プログラムにこう書いていた。
「女はギャップのある男に惹かれます。粗野な男が実は繊細だったり、軽薄そうな人が硬派だったり。井之上さんはギャップがある方です。だから私は井之上さんに惹かれます」。ハゲた頭の老年社長が生ギターで拓郎を歌う。と、どうだ。見た10日、ギターの弦が切れたか外れたか、1本だけブラブラと垂れ下がったのである。すると、どうだ。その時、井之上、少しも騒がずー。邪魔になる1本の弦を弾き飛ばし、ギターを激しくかき鳴らし続けた。その歌声、音色の感動的なことといったらなかった。胸が熱くなった。ハゲ頭の男は実は情熱的で繊細で硬派なのだよ。
村田も山口森広、東てる美、小林美江、かんのひとみも良かった。桑原はもっと良かった。
ところで東が女主人の居酒屋の壁にメニューが下がっていた。むかでのり180円、ごんぐり100円、せせり七味焼280円、まびきの天ぷら230円、とびうお刺身280円、ラムネ30円。1970年後半の宮崎弁が飛び交う港町。「サタデーナイト・フィーバー」で踊る俳優のパワー、カーテンコールで挨拶した青山の姿に、また胸が熱くなった。
(平成27年3月2日)
カトケンのシェイクスピア 
加藤健一事務所の今年の第1弾が「ペリクリーズ」(本多劇場・2月19日~3月10日)。〝カトケン・シェイクスピア劇場〟として事務所の創立35周年記念であり、その記念に当たり大きな挑戦をしたいという加藤が30年ぶりに演じたシェイクスピア作品だった。
長い間、観客は何を求めて同事務所の公演に足を運んできたのか。加藤の演技、これが第1。彼を中心とした俳優と演出と作品によって生み出される笑いが第2。プロデュース公演による上質な演劇の楽しみが第3だろう。
その点、今公演は異色と言える。
加藤は主人公ペリクリーズの若い領主の時代から晩年の老いた姿までを演じた。アンタイオカス王の娘の王女に求婚する青年の時は若々しいとは言えないものの、むしろ実年齢との落差が面白く、吹き出しそうになった。ペアで踊る場面も一人だけギクシャクしたダンスが笑いを誘う。
シェイクスピアのロマンス劇と言われる作品だが、過去の上演では笑いが多くはなかったように、近親相姦や死んだはずのペリクリーズの妻セーザが生き返り、娘のマリーナも生きていたという奇跡はあまりに荒唐無稽だ。それでも随所に笑いが起きるのは鵜山仁の演出による仕掛けのおかげだ。作品に含まれている〝おとぎ話〟の要素、海上での嵐の場面など観客の想像力をかき立てる美術が効果を上げた。
プログラムの中で加藤はこのシェイクスピア作品に「台詞が体を通る」と感じたそうだと話していた。次の挑戦が待たれる。
【写真】加藤健一(右) 撮影:石川純
(平成27年3月2日)
心洗れる音楽劇 
草月ホールで上演された音楽劇「瀧廉太郎の友人、知人とその他の諸々」(1月28日~2月1日)は脳が活性化され、心が洗れる演劇のチカラを示してくれた。
成功の要因は3つある。
音楽の絶対的な浸透が第一。「荒城の月」や「お正月」などが代表的な天才、廉太郎の名曲は日本人なら誰でも思わず口ずさみたくなる。23歳の若さで夭折した彼のドイツ留学時代のエピソード、友人、知人との友情が主な物語だが、作曲した「音」は心に心地良く舞台を包んだ。
その曲を歌う俳優らには感心した。これが第二。廉太郎の友人、岡野貞一を演じた原田優一の歌声には驚かされた。ソフトで伸びやか。抜群の歌唱力だ。演技も際立った。「故郷」を作ったとされる作曲家だが、静かな廉太郎とは対照的な三枚目、道化のような役柄が嵌まっていて、巧い。
廉太郎に恋心を持つ幸田幸を演じた和音美桜の歌声にも拍手を送ろう。凛とした佇まい、良家のお嬢さんになっていた。
そして幸に従うフクの新垣里沙。モーニング娘5期メンバーで、7代目リーダーだったというが、最初に出てきた笑顔の愛くるしいこと。舞台がパッと明るくなった。さらに台詞の間がいい。発声も舞台に合っていた。
板垣恭三の演出が第三の理由だ。
娯楽性も加え、6人の登場人物の個性を明確に描き出した。明治という時代の空気、雰囲気を感じさせた演出力の冴え。ほのぼのとした人間関係と天才作曲家の運命がほどよく出ていた。廉太郎の台詞に「音楽と向き合い、その高見を目指していく、それを語り合えるのが友人」だとある。ただ、坂の上の雲を見つめて歩み続けた明治人の気骨。子供を産み育て、日常的な平凡な生活、人生に女性の幸せを見つけたいという娘。
笑いを取るだけに四苦八苦する芝居が多いのに閉口している中、一服の清涼剤を飲んだ気がして溜飲が下がった。
(平成27年1月30日)
自由自在な加藤健一 
8月にアラン・エイクボーンの戯曲、そして11月がニール・サイモン作品。英国と米国の喜劇の名人が書いた本を上演した加藤健一事務所は今回、腕達者の俳優を寄り集めた。
サイモン33作目の「ブロードウェイから45秒」。日本初演である。
物語は全てコーヒーショップで展開される。オーナーはポーランド系の夫婦、新井康弘のバーニーと田中利花のゼルダ。主役の加藤健一は近くの劇場に出演しているユダヤ系のコメディアンで店の常連、ミッキー・フォックス。
店には南アフリカから来た劇作家志望の青年、劇場帰りの芝居好きな女性、オハイオからやって来た女優の卵などが出入りしている。ミッキーはイギリス人プロデューサーとの出演交渉中だ。
軽口を叩き、駄洒落を飛ばし、芸の一端を披露する加藤は面白く素敵な台詞が満載のサイモン劇で自由自在に演じて愉快である。
出演者がそれぞれ個性的で伸び伸びと演技をしていたのに好感を持った。中でも新井がすっかり舞台俳優として堅実になったのには感心した。
滝田裕介と中村たつという俳優座の2人が長年の舞台経験が滲み出る味。最後にどんでん返しが仕組まれている2人の笑顔に溜飲を下げた。カトケンの芝居では>12人の出演者は多い方だろうが、チームワークがしっかり取れているウエルメイドの喜劇となった。(11月15日まで。新宿・サザンシアター)
【写真】「ブロードウェイから45秒」。撮影:石川純
(平成26年11月20日)
え! 渡辺えりが還暦? 
渡辺えりが来年に還暦を迎えるという。なぬ!あの、えり子さん(前名)が…。5月31日から3日間、3都市で「還暦記念コン-ト」を予定しているが、相変わらず巨大なバストが揺れに揺れる太めの肉体を維持する彼女のエネルギッシュな舞台を見た。
オフィス300公演「天使猫~宮澤賢治の生き方」。東京・三軒茶屋のシアタートラム(千秋楽は11月30日の山形公演)での舞台だった。
2012年の初演も見たが、再演の今回は大沢健、宇梶剛士、谷川昭一郎、大和田美帆が客演している。作品が書かれたのは2011年3月11日の大震災の後。宮澤賢治を主人公にその短い生涯での家族、社会、そして自身との血が吹き出すような闘いと宇宙観を取り込んだ渡辺えりの格闘演劇でもある。
俳優でパワフルなのは大沢、そして賢治に扮した土屋良太だった。日本舞踊の舞踊家でもある健ちゃんは「舞踊華扇会」に度々出演してくれたように、俳優としても情感が伝わる演技を見せてくれる。ウサギの着ぐるみを付けて妻ウサギを廃墟の中で探しまくる。哀しい顔の表情が秀逸だ。近年、腕を上げた土屋は、土くれの臭いが伝わる賢治になっていた。温かい性格も浮かんでいた。
そして何よりエネルギッシュなのが渡辺えり。笑いを取る演技よりも、この作品に思いを寄せる姿勢を見ると観客の体内温度が上がる気がする。
300の公演を本格的に見始めたのは1984年の第13回公演「瞼の女」からだったか。高村光太郎を描いた「月にぬれた手」とこの「天使猫」の初演をした2012年から彼女の作調は変わってきたと思う。社会への問い掛け、問題提起がより深くなっている。
還暦を迎える女傑えりの才能、揺れるバストへの期待が膨らむばかりである。
(平成26年11月20日)
新旧の「ショーガール」 
「ショーガール」と言えば当時の西武劇場、今のパルコ劇場で1974年から15年間上演されたエンターテイメント。木の実ナナ・細川俊之コンビがオトナの魅力を都会的なセンスでふりまいていた。
脚本・構成・演出の福田陽一郎さんが、客席中央にまず陣取り、上手や下手の客席に移動しまくって照明やら音響やらをチェックし、タレント2人に大声でダメ出しをしていたっけ。ハンチングのような帽子をかぶり、タバコは離さない。そんな舞台稽古が思い出される。そんな舞台はノンストップで疾走するスピード感が快感だった。そしてキュートなナナの笑顔、目尻が下がった中年男の色気たっぷりの細川の表情が忘れられない。
で、26年ぶりのシルビアと川平慈英による三谷幸喜・作・演出「ショーガール・こんな出会いも悪くない」が8月21日~9月14日に上演された。
で、独断と偏見の採点(5点満点)。
歌は木の実5点、シルビア5点、細川3点、川平4点。
踊りは木の実5点、シルビア4点、細川4点、川平5点。
芝居は木の実5点、シルビア4点、細川5点、川平4点。
スタイルは木の実4点、シルビア5点、細川5点、川平4点。
総合すれば木の実19点、シルビア18点、細川17点、川平17点。
構成は福田5点、三谷4点。演出は福田5点、三谷4点。福田さんに軍配を上げたが、三谷版には1本のドラマ性が明確に通っていた。
三谷の作・演出「君となら」の終演後に上演されたため、同じセットを使っていた。日本間を共用したのだから都会的という訳にはいかない。次ぎは洋間で願いたい。
【撮影:阿部章仁】
(平成26年9月19日)
カトケンの笑顔 
久しぶりにカーテンコールでカトケンの笑顔を見た気がした。一粒のウソのない喜んでいる笑顔。加藤健一事務所による本多劇場「If I Were You(こっちの身にもなってよ)」(8月24日まで)がそれ。
ここで質問-。
①朝起きて異性になっていたら、どうしますか?
②もし誰かと中身が入れ替われるとしたら、誰になって、何をしたいですか?
③こっちの身にもなってよ、と思ったエピソード?
④15歳くらいの頃の印象的な親との思い出は?
以上は公演プログラムで出演者に出していたものを頂戴した質問。物語の筋に関連しているのはお分かりでしょう。
加藤健一が演じたマル、西山水木のジルは娘と15歳くらいの一人息子サム(松村泰一郎)を持つ中年夫婦。家庭を振り向かない仕事人間の夫に不満がある妻。どこにでもいる普通の夫婦だが、ある朝、突然、2人は入れ替わってしまうとなるとこいつは異常だ。体は同じでも心、性格、経験などマインドが交代してしまった-というお話。
こうなると、妻、つまり女性、夫、つまり男性に入れ替わって演じることになる。俳優の演技力が重要なのである。
加藤も西山も実力派の舞台俳優なのは異論などあるはずもない。カトケンはオネエ系の女性にはならないし、西山もいかにも男であることを無用に強調などしない。戸惑いながらも息子や娘夫婦(加藤忍、石橋徹郎)に感づかれない芝居に徹する。そこに喜劇が生まれる。アラン・エイクボーンの英国喜劇だからエスプリが効いている。
さて、先の質問の答えは?
①大切なところを触って確認する②遠藤になってモンゴル勢を打ち負かす③噛み切れない固い肉を出された時④車の中でゲロを吐いてオヤジに叱られた。
-そんな事を思い出させるホームスイートコメディ。カトケンにぴつたりと合う役柄だったのである。
(平成26年8月25日)
ウオー・ホースに魅了 
シアターオーブで上演された「ウオー・ホース~戦火の馬」に私は完璧に魅了された。素晴らしい。この演劇の上演を見逃した人は残念至極だろう。
馬の動きをつぶさに見つめていた。パペットのジョーイとトップソーンという2頭だ。操り人形の総称をパペットというが、この他、数頭登場する馬たちの動作(つまり演技)は申し分がなかった。
少年アルバートと栗毛(鹿毛にも見える)のジョーイ。馬と少年(人間)の愛情、友情の物語は数多いのだろうが、この「ウオー・ホース」もその世界を描いている。
パペットの馬は基本的に3人遣い。首から上、つまり頭の部分に一人、馬の胴体の中に二人が入る。胴体の中の一人が前足を操り、もう一人が後ろ足(そして尻尾)を動かす。日本の文楽人形からアイデアを得たというが文楽の三人遣いは主遣い(頭と右手)、左遣い、足遣いで、ほとんど同じといえよう。
何が素晴らしいかって?
パペットの馬は本物の馬と同じような動きをするのである。特に驚いたのが四本の足だ。四本の足が別々に、互い違いに歩く。これを操作するパペッターには脱帽した。研究と練習を積み重ねた苦労が偲ばれる。
サラブレッドと農耕馬の血を引くジョーイは第1次世界大戦の最中、軍馬として徴用させる。過酷な戦場で負傷しながらも奇跡的に生還。主人公アルバートと再会する。馬の声もパペッターが出すのだが、彼ら俳優陣の努力は拍手してもし切れない。
馬と人間は最高の友人同士なのである。それをこの作品は実証する。そして、家族愛、戦争の愚かさ、友情…。ドラマがぎっしり詰まった最高級の演劇。日本でこんな舞台が作れないものだろうか。
(平成26年8月25日)
サヨナラ、そして今日は、梅花昇ぼる 
OSK日本歌劇団のトップスター梅花昇ぼるが歌劇団を卒業した。8月1日から3日まで新橋演舞場で行われたレビュー「夏のおどり」がサヨナラ公演だった。
彼女の卒業が残念至極。私は反省している。昨年、日生劇場での公演で初めてその素晴らしい舞台姿を見た。ビックリした。もっと早くから見続けるべきだった。
現在のレビュー界で梅花は最高のスター、実力者だと思える。〝踊りのOSK〟と言われる中、今公演でもどの景も一点の油断がない。百面相の如く、表情、表現が違う。目線の行方、指先一つ揺るぎがない。踊りのソロでもコンビでも鋭く、キレがある。特に魅了されたのがその笑顔。唇の紅が印象に残る人だ。
OSKの第一線からは身を引くかもしれない。しかし、舞台には立ち続けるべきだ。彼女の才能を受け継ぐのが大切だ。
一人、若き才能を見つけた。悠浦あやと。長身で足が長く、面長の美形。1部の和装、2部の洋装も一際目立っていた。〝ポスト梅花〟として育てて欲しい。
(平成26年8月25日)
加藤健一と三田和代 
加藤健一事務所による加藤と三田和代の二人芝居「請願・核なき世界」(本多劇場)は、皮肉を込めれば後味の悪さに酔う1時間45分だった。(6月4日~17日)
夫婦喧嘩、それも犬も食わない痴話喧嘩ならともかく、英国の陸軍大将まで昇りつめた退役軍人と、核兵器反対の請願書の新聞広告に署名した妻との激烈極まる口論が続くのだ。しかしそれだけでは終わらないのが、傑作「この生命は誰のもの?」を書いたブライアン・クラークの仕掛けだった。
妻エリザベスには2年余の不倫と言う過去が暴かれ、現在は子宮癌による余命3か月を宣告されている。その病状を初めて知らされた夫エドムンドは怒り、実は知っていた妻の不倫を初めて口にする。
英国の老夫婦はかくもディベートするものか。信念の相違、愛情の在り方と行方、核兵器に対する決して交差することのない平行線、老年での性生活。米国の元大統領クリントン夫婦、日本の安倍総理夫婦が口論している様子を想像してダブらせたのは当方だけだろうか。
二人には4人の子供、7人の孫、そして間もなく曾孫が出来るという。「軍人に引退はない」と話すエドムンドは1980年代のこの物語の中で敵国から国を守るには核兵器が抑止力になると譲らない。ヒトラー、スターリンの例を引き、核兵器は地球を滅亡させるとエリザベスは主張する。自身の戦場体験を踏まえて、軍人として生きてきた信念を貫く夫、未来の子供たち、さらに地球の未来を憂う妻。
加藤は軍人の抗弁というより一般人としての芝居と言い回しでエドムンドを描き、ウイットに富み、ユーモアのセンスもある堅物を演じた。三田は夫から「魅力的な女性だ」と褒められて泣き尽くす場面がいい。また余命をどう生きるか、この世に生まれてきた証、人間の素晴らしさを説き宇宙感を持つ老年のインテリ女性として夫の3倍の台詞で語り尽くした。
妻の愛人の死を知った日、復讐のように君を抱いたのだと明かす夫。不倫を正当化しようとする妻。この夫婦に好意は持てないが、加藤と三田に二人芝居は物語の後味の悪さと演技のぶつかり合いの醍醐味がいつまでも尾を引いた。
【写真】撮影:石川純
(平成26年6月30日)
立川三貴の実験的な演出 
文学座にアトリエ公演、俳優座に稽古場公演があるように、演劇集団・円にもアンシャンテ公演がある。「俳優・演出家たちの自主企画による小劇場公演」だ。どれも劇団本公演と区別して実験的な上演が身上だろう。
立川三貴が演出・上演台本を担当した「ブレーメンの自由」が田原町(台東区西浅草)のステージ円で上演された(7月5日まで)。
ライナー・ヴェルナー・ファスビンダーの作で〝ゲーシェ・ゴットフリート夫人 ある市民悲劇〟が副題。立川は昨年の「あわれ彼女は娼婦」に続く演出。悲劇には違いないが見方によっては「これは喜劇にも見えるのではないか」と思わせる刺激的な上演だった。
乙倉遙が演じた主人公のヒロイン、ゲーシェ夫人は自由を猛烈に求める。最初の亭主は酒乱で徹底的な暴力主義者。保守的な両親からも男への忠義、追従を強要される。都議会で差別的な暴言を浴びた女性議員がいたが、その数倍の男尊女卑の中にいた。
喜劇的な要素を感じたのは、立川の演出にその部分的な側面が見えたし、登場人物を探ると多面的な性格、考えが内包されていると思えたからだ。
差別や暴力を受け続ける内、「人形の家」のノラとは違うものの、自我や自由への希求がフツフツと沸いてくる夫人。その怒り、または女性の生理的欲望の凄まじさも浮き出る。立川演出の再演が見たい。
(平成26年6月30日)
青年座の高く飛べるを 
劇団青年座の創立60周年記念公演「見よ、飛行機の高く飛べるを」は見るたび、作・永井愛の傑作であり、演出・黒岩亮の傑作だと思う。そして座の財産として長く何回も再演して欲しいとも思う。
上演される時代の状況がどうであれ、いや、むしろその時々が厳しいほど、作品が放つ光の熱量が増して感じられるのが傑作たる由縁だ。
ナイジェリアでは武装勢力が女子生徒の教育の場を奪っている。韓国では大人の無策によって若者の生命が船とともに消えた。日本では若者の職場が狭まり、おバカな少女たちはモバイルにうつつを抜かしている。
質実剛健の思想を植付ける一方、良妻賢母を求める教育を押しつける。明治44年の岡崎。女子師範学校を舞台にした作品は、その学者で反抗した少女たちがいとおしく思えるのだ。
光島延ぶを演じた安藤瞳、杉坂初江の小暮智美、菅沼くら先生の藤夏子、そして生徒たち。それぞれが個性を持ち、その人格を賭けた演技を見せ、今回も統一性をしっかりと見せつけた。我が国に既に「大和撫子」は消えつつある。
結婚しない、子供を産まない、高い志も持たない女性たちに見せたい作品の第一。
青年座に女優が育ってきた。この舞台を上演することで、女優は育つ。
創立60年、還暦を迎えた劇団。老年座になることなく、「見よ、青年座の高く飛べるを」で第2章に向かって欲しい。
(平成26年5月20日)
辻仁成と獅童 
辻仁成・脚本・演出「海峡の光」が読売新聞創刊140周年記念のオープニングシリーズとして「よみうり大手町ホール」で上演された(4月29日まで)。
函館刑務所の受刑者・花井が中村獅童、看守・斉藤がラーメンズの片桐仁。若き日、花井からイジメを受けた斉藤は復讐するのか-。所内での緊迫感ある空気が見どころだが、観劇した17日、、アフタートークで披露した獅童語録を並べる。
「一期一会という言葉を大切にライブ感を大切にしている。生(ナマ)のものはその日、その日のことはその日限り」
「花井はイヤな奴で仕方ないが、普段は心優しい獅童ちゃんです。どうせ好感度は低いからね」
「今日は(自分の)ペットの柴犬の先生が見ていて、やりにくかった(笑い)」
「(稽古場での辻演出について)けっこう細かいよね。上手くいくと、『ロックだね、ロックンロールだね』と言っていた。目の一つ、眉毛の一つ、今のいいね-とか」
「一番印象的なのは『これまでエネルギッシュな役が多かったが、今回は獅童が持っているエネルギーを出さず、前半は押さえて押さえて、緩急を付けてみよう』と序盤に言われた。新しい獅童を引き出してもらって感謝しています」
最後に一言と促されて-。
「生身、演劇、歌舞伎の魅力を知ってもらうのがボクの使命だと思っています。もし他の役をやるなら?ボクはいじめられる斉藤の役です」
笑いを取りながらも、素顔はマジメな獅童ちゃんだった。
【撮影】田中亜紀
(平成26年4月24日)
サブちゃんの最終公演 
ついに北島三郎(77)の大劇場の座長公演にピリオドが打たれる。
その「北島三郎最終公演」の制作発表が4月21日に開かれた。
劇場は9月が東京・明治座(8月31日初日)、11月が大阪・新歌舞伎座、来年1月がが福岡・博多座。演目は芝居が「国定忠治」、ショーはヒットパレード「北島三郎、魂(こころ)の唄を…」の2本立てだ。
芝居では北島が忠治、女房おふじが星由里子、そして実娘の水町レイコが娘お千代、娘婿の北山たけしが子分・板割りの浅太郎で親子共演になる。一方、ショーでは大仕掛けのフィナーレになるという。
北島は昭和43年(1968)、新宿コマ劇場で第1回座長公演(「次郎長水滸伝」と「歌いまくる北島三郎ショー」)を打ち、今回の3都市公演の大千秋楽(1月29日)には通算上演回数が46年間で4578回となる。
劇場別を挙げると①新宿コマ劇場・1790回②梅田コマ劇場・1610回③博多座・555回④御園座・277回⑤新歌舞伎座・152回⑥明治座・115回になる。
北島はこう挨拶した。
「最終公演は自分で決めたこと。気が付けば1か月公演が来年1月で終わるのか-と。丈夫に生んでくれたおやじ、おふくろに感謝している。感無量です」
芸道50年の2011年に考え始めたという。そして昨年の「紅白歌合戦」の引退と座長公演の終了を決めていた。「はっきりさせないのは嫌な性分。義理と人の情け、親子の絆。『国定忠治』を選んだ理由で、体はいたって健康」と話し、大劇場にも1日でも2日でも出させて頂ければ…。1日だけの地方公演(コンサート)は続ける。まだまだヤル気十分です」と意気軒高だった。
(平成26年4月24日)
ケラと女優とかんしゃく玉 
「ナイロン100℃」の「パン屋文六の思案」でのお勧めを書く。
岸田國士の戯曲7作をコラージュ化したケラリーノ・サンドロヴィッチの新作だ。休憩10分を挟んで上演時間3時間10分は年寄りには辛い長さだが、延々と続く台詞劇を猛烈な速度で視覚化したケラの手腕はやはり一級品だ。
新谷真弓。喜劇女優の天才じゃなかろうか。小道具の運び屋みたいに次々と運ぶ芝居に飽きない。文六家の17歳の娘おちか。突然、大声で泣き出す面白さ、ダンスでの尻振り具合。コケティッシュだった。
村岡希美。何と言っても「かんしゃく玉」の妻。夫を支えながらも欲求不満、怒りを夫婦でかんしゃく玉を叩き付ける。その演技は藤山直美さえ負けそうだ。全身を使って踊るように叩き付ける。プッと吹き出す笑い、やがて哀しい気持ちにさせた。
松永玲子。見方によっては彼女ほど色っぽい女優は少ない。和服の着こなしなど、女の色気の見せ方を心得ている。
緒川たまき。「世帯」の妻、「恋愛」の女。おバカなのか、男を惑わすのか、「恋愛」の女は吸いついて噛みつきたいようないい女だ。動く美しいセクシー人形。声もステキ。
テレビドラマ「三匹のおっさん」で光った志賀廣太郎の文六が渋い落ちつき、植本潤の女装は〝本役〟だが、むしろ「恋愛」の男でのシリアスな芝居が収穫。
という訳で、大正から昭和初期の女性たちは現代よりも深く人生を見つめ、苦悩し、明るく生きる努力をしていたのが浮き出た。憂さを晴らす、かんしゃく玉は今、モバイルになってしまった。(青山円形劇場・5月3日まで)。
【写真撮影】引地信彦
(平成26年4月22日)
白井晃への期待と不安 
俳優で演出家の白井晃が4月から神奈川芸術劇場(KAAT)の参与に就任した。3年間、芸術監督を勤めた宮本亜門の任期満了による交代だが、参与の任期は当面2年間。その後、芸術監督に移行するという。
10日の記者会見では参与(アーティスティック・スーパーバイザー)と監督との違いを迫る質問が出たがそれはどうでもよい。
創造型を自認する劇場のテーマが①モノをつくる(芸術の創造)②人をつくる(人材の育成)③まちをつくる(賑わいの創出)としているのだから、その実現のために白井芸術参与と劇場側がどれだけ汗をかくかだ。
独特の演出力に定評を持つ白井だが、実験色が強い。芸術参与としてのテーマとして①時間と空間の共有という同一性②表現形態を探り人々と出会う瞬間を作る③神奈川・横浜にある劇場の立地条件を活用する-を挙げているが、やや難解、抽象的で分かりにくい。
就任第1作「Lost・Memory・Theatle」が合わせて発表された。
出演者の山本耕史、美波、森山開次、江波杏子、白井は魅力的だ。しかし三宅純の音楽を使う発想から出発する作品。会見当日、まだテキストはなく、白井の頭の中だけにあるとされた。芝居でもコンサートでもパフォーマンスでもないような不思議な舞台が出来るらしい。
2011年1月の開場以降、眞野純館長は「到らないものがまだ数多くある。今後の2年間、またその先の5年間を見据え、芸術監督のモデルを作り、提案したい」と話した。
第1期の宮本時代と比べて、送り出される作品は芸術的であり、また大衆的になるのか。蜷川幸雄のさいたま芸術劇場、シアターコクーン、野村萬斎の世田谷ブリックシアターを越える新たな劇場の色に期待したい。
(平成26年4月22日)
流行のアフタートーク 
今、流行のアフタートークを2題。
最初はグループる・ばる「片づけたい女たち」(作・演出・永井愛)。2004年に初演され、今公演がファイナル。朝霞市・ゆめぱれすのプレビュー公演(3月8日)に出かけた。
アフタートークはツンコ役の岡本麗、おチョビの松金よね子、バツミの田岡美也子、そして永井愛も参加した。
初演での立ち上げの思い出について松金は「尊敬する大好きな作家にお願いして、永井さんの家へ集まったね」。永井は「片づけられない女たち」という本が当時出版されていて「頭の中が片づかない-というのがヒントになった」という。50歳になった、と騒いでいた時だったそうな。
岡本は役柄との共通項について「私は落ちこぼれの人間。キャリアウーマンでもないし、若い男に惹かれる、片づけられないのは似ている」。「再演が好き。人生の歩みのように面白いんです」。
松金は「まず、ゴミのお稽古から始まった。恐い初日でした。ゴミは何百回やっても同じ所に置かれているんです。舞台図が表彰されているんですよ」
岐阜、栃木や四国を回って3月29日が大千秋楽だった。通算203回になった50歳女性の三人芝居だった。
それにしても舞台の台詞をオウム返しにするバアさん、バカ笑いのオンナ、帽子を取らないジジイ、モバイルのスイッチを入れたままの輩。「片づけたい連中」が多かったね。
もう一つは、井上ひさしの傑作一人芝居「化粧」。旅芝居の女座長を演じた平淑恵の2011年以来3年ぶりの再演だが、昭和57年の初演前、下調べに協力した梅沢富美男がアフタートークに登場した(3月9日)。
井上ひさし氏の娘さん、井上麻矢・こまつ座代表が司会。
「先生がいらして、兄貴(梅沢武生)と2人でよく話しながら飲みながら食べながらやりましたねえ。兄貴が吸っていたダンヒルの煙草とライターだけがまず決まった」
芝居の中では女座長は夫に逃げられ、残った一人息子を里子に出した話がある。
「当時、女座長さんはたくさんいらしゃって、お父さん、また、お母さんを知らない子供もいっぱいいた。なぜか皆、窓から逃げて行く。子供が出来るとどちらかが消える。ドロンをする。鬘も持って行ってしまうんだ」
役柄に入っていくのはどんな時-という質問には「ボクは鬢(びん)付けの時、スイッチが入る。化粧は習い始めの頃は15分かかった。今は7分で出来ます」。梅沢の話し上手に会場は笑いに満ちていた。(公演は3月21日千秋楽)。
(平成26年4月4日)
若手のホープ、秋元才加 
AKB48を卒業した秋元才加がパルコ劇場「国民の映画」に抜擢されて、エルザ・フェーゼンマイヤーを演じている(3月9日まで。以下、大阪・愛知・福岡と続き4月6日千秋楽)。
三谷幸喜・作・演出「国民の映画」はまぎれのない秀作舞台だ。ナチス政権下、宣伝大臣ヨゼフ・ゲッペルスの別荘に集められた映画関係者がホームパーティの中で踏み絵を迫られる。人間関係が実に面白く、それが秀逸の一つ。
秋元のエルザは、若い魅力的な身体を武器にゲッペルスに取り入る新進女優。この起用は成功していた。
女優陣は吉田羊、シルビア・グラブ、新妻聖子という美形で悩ましい肢体を持った人々。2011年の初演の出演者が大半で、今回の再演では秋元が新たに加入したのだが見劣ることなく、むしろ一番若い役柄が目立っていたのが得をしていた。ゲッペルスに自分から体を寄せて座る芝居の下心、夫人のマグダへの嫉妬といった感情の変化もいい。
「ローマの休日」で舞台女優としての可能性を褒めた事があるが、若手のホープへ向かって欲しい。
男優陣はゲッペルスの小日向文世、ヒムラーの段田安則、執事フリッツの小林隆、老優ヤニングスの風間杜夫が手練の演技。脚本、演出、俳優陣とも揃って何回でも再演して欲しい名作である。
【写真撮影】阿部章仁
(平成26年2月27日)
翼、優馬、朝幸に拍手!
日生劇場でのパフォーマンス「PLAYZONE・IN・NISSAY」で今井翼、中山優馬、屋良朝幸の3人に目を凝らした。正直明かせば、他のグループやタレントはチンプンカンプン(申し訳ない!)だからでして-。
翼君には感心した。何がって? オトナになったなあ-というのが第一の感想。この公演で圧倒的な存在感があった。もっと言えば貫禄、そして座長としての風格さえ見えたものだ。恐らく何か自信のようなものを持ったのだろう。
優馬君には感心した。何がって? アイドルとしての輝きが見えた-というのがその感想。何たって二枚目。その上、スタイルがステキ、そして芝居心がある。恐らく、何か目標があるのだろう。
朝幸君には驚いた。何がって? もちろんお分かりでしょう。そのダンス力ですよ。一つ一つの振りが他と違う。踊りのキレの良さ、スピード。とにかく、しなやかで、大きく踊っても他の人と同じにピタリと合う。プログラムの中で「メッセージ性を持たせる」と書いてあったが、彼の踊りにはある意思を感じる。大したパフォーマーだ。
以上、三人に拍手!
追伸。
今井翼君は今年、アッと驚く公演があるらしい。近い内、分かるでしょう。
(平成26年1月15日)こんな演劇、初めて見た。中屋敷法仁の作・演出「世迷言」(本多劇場・2月4日まで。2月8日・北國新聞赤羽ホール、2月14・15日・サンケイホールブリーゼ)。「柿喰う客」の公演である。
魔術を操る中屋敷の世界は手に負えない。目が眩むような荒唐無稽のストーリー。スローモーション演技による奇怪な動き。耳をつんざく俳優の声。いつしか吸い込まれた音楽の心地良さ。私がどうかしているのか、中屋敷の頭脳がどうかしているのか。面白くて、笑いを堪えるのが大変だった。
人間、鬼、猿、人間の帝(七味まゆ味)は妹に猿と交われと突き放して捨てる。竹から生まれた姫を得るため、猿の王子と取引したためだ。猿は進化するために人間の血が欲しいのだった。鬼(篠井英介)は首を切られ取られても動いてみせる。三つ巴の殺戮、鬼ごっこ、猿芝居、残酷物語。人を喰った魔法のようだ。
歌舞伎の手法が多用された。
人を喰った「柿喰う客」 NEW! 
こんな演劇、初めて見た。中屋敷法仁の作・演出「世迷言」(本多劇場・2月4日まで。2月8日・北國新聞赤羽ホール、2月14・15日・サンケイホールブリーゼ)。「柿喰う客」の公演である。
魔術を操る中屋敷の世界は手に負えない。目が眩むような荒唐無稽のストーリー。スローモーション演技による奇怪な動き。耳をつんざく俳優の声。いつしか吸い込まれた音楽の心地良さ。私がどうかしているのか、中屋敷の頭脳がどうかしているのか。面白くて、笑いを堪えるのが大変だった。
人間、鬼、猿、人間の帝(七味まゆ味)は妹に猿と交われと突き放して捨てる。竹から生まれた姫を得るため、猿の王子と取引したためだ。猿は進化するために人間の血が欲しいのだった。鬼(篠井英介)は首を切られ取られても動いてみせる。三つ巴の殺戮、鬼ごっこ、猿芝居、残酷物語。人を喰った魔法のようだ。
歌舞伎の手法が多用された。
異類婚。歌舞伎には人が動物や植物と交わる演目がある。
見得。くにゃくにゃと動く演技から、ピタリと決まる芝居を全員が見せた。
割り台詞。一つの台詞を二人、三人が割ってしゃべるのも歌舞伎手法の導入か。
異様な動き。これも歌舞伎ではいわば普通の手法だ。
駆け抜けた90分。凄いのが深谷由梨香。猿に嫁ぐ帝の妹。とにかく凄い。複雑に動くから短いスカート、ハイヒールを履いた姿がエロティック。さらに、圧倒的な声。豊かな声量。「私は、サルだあ!」と叫ぶ声質は劇場の奥まで轟く。黒々と塗られた口元から吐き出されたドス黒い怨み、親か神からもらったのか、鍛え上げたのか。歌舞伎で言えば、片岡亀蔵だ。女・亀蔵。吸いつきたいと思った人もいただろう?。
ああ、勘三郎と中屋敷の組み合わせが見たかった。
【写真】撮影:引地信彦
(平成26年1月31日)
大竹しのぶの林芙美子 
今、我々は「アベノミクスは儲かる、幸せになる」という踊り文句の“太鼓たたいて笛ふいて“”の物語にいる。
上演中の井上ひさし・作「太鼓たたいて笛ふいて」にも「物語」が出てくる。「戦争は儲かる」という前半、「それはウソ、作られた幻想」という後半。主人公の林芙美子は前半では日中戦争から太平洋戦争での軍国主義の宣伝ガールを演じ、後半の戦後は反戦小説を書きまくる。我々は自分たちの時代に作られる「物語」を直視しないと、踊る阿呆になりかねない…。
井上ひさしは登場人物6人について公演プログラムで書いている。
「後半生の高揚と沈潜」「重いことがらを軽く演じる」「ひとの情けの温かさと皮肉な言動」「血の通った正義を粘り強く柔らかく]「昭和前期の正直さそのまま」「庶民の小狡さ」-。
この作品は「転向」とその覚悟、市井の一員としての痛烈な反省を見る人に問いかける。芙美子を演じる大竹しのぶのその前半の陽気さ、そして後半のとんがった覚悟となる演技の鋭さを見て欲しい。3月1日の福岡公演までのロングラン(初日は1月16日だった)の4回目の再演。
森光子の「放浪記」、大竹しのぶの「太鼓たたいて笛ふいて」。女優が全身全霊を傾けた演劇の勝利である。
【写真】撮影:谷古宇正彦
(平成26年1月31日)
「わが町」を見よう! 
2011年初演の音楽劇「わが町」を確かその年のミュージカル雑誌のアンケートでベスト10入りにしたのを覚えている。1月8日から俳優座で再演がスタートしたこの公演は4月まで全国各地を回る超ロングランだから、ぜひ見落としてほしくない。初演での評価と遜色ない、それ以上の舞台である。
ソートン・ワイルダーの名作を音楽劇にした知恵者は大したものだ。この作品には、一人一人の人生の意義を確認させる深い宇宙観、世界観が溢れている。太陽、月、星々、そして地球。その中のわが町と自分。
1幕では日常生活、2幕では恋愛と結婚、3幕では死と死後。若者には家族、日々の生活を、青年・壮年には愛情という解けないナゾ、老年には死と向かい合う心構えを問いかける。老若男女、これを見て皆が考えればいい…。
(平成26年1月15日)
甘く苦い「船に乗れ!」 
「食うために腕を上げていく芸術家、俺は好きだなあ」。この台詞に惚れてしまった。まだ17歳の高校生である孫サトル(山崎育三郎)に投げかけた松野理事長(小野武彦)。天才モーツァルトがなぜ次々と名曲を作曲し続けたか?と問いかけて、答えに窮する孫に「それは、食うためさ。次々といい作曲をしないと、注文が来なくなるから」といったニュアンスで話した後の台詞だった。
シアターオーブで上演された交響劇「船に乗れ!」には、とても多くの教訓的な台詞、やり取りが飛び出す。その全部の意味を考察する間もなく物語が進むので、恐らく多くの観客は聞き流してしまった、と思うほどだ。
名門の学校への進学は叶わず、祖父が理事長の三流の音楽科に入ったサトルの専門はチェロ。ニーチェを愛し、学内で一番の演奏実力を持つ一方、やはりニーチェに傾倒する倫社の教師に食いかかりながら、教えを乞う。しかし、その教師に「君は殺されてもいい人間だと言われた」といった嘘を付き、教師は学校を追われる。
この交響劇(音楽劇)には例えばバッハの「ブランデンブルグ協奏曲」やベートーベンの「ヴァイオリン・ソナタ第5番」、ヴィバルディの「チェロソナタ第5番第3楽章」といったクラシック音楽を実際のオーケストラが演奏し、俳優たちの演技演奏に重ねる演出がユニーク。さらに宇宙、人生、恋愛、殺人の是非という答えが出ないと思われる難題が大きな主題になっている。
また、好きだった女子高校生が、サトルのドイツ留学の間に妊娠-というお定まりの物語もある。ニーチェの著作「悦ばしき知識」に出てくる一節の「船に乗れ!」。演歌派の当方としてはクラシック音楽の名曲に戸惑い、哲学の思考に頭を殴られ、でも、甘く、苦い青春時代に引き戻してくれた舞台だった。
【写真撮影】加藤孝
(平成25年12月26日)
風よ、吹き続けろ! 
東京演劇集団風が上演を続けている「Touch~孤独から愛へ」が22年目に入った。今年は九州地区の中・高校を対象に3か月56ステージの巡回公演を経て12月23日から3日間、東中野の拠点劇場で凱旋公演を行った。
孤児である二人の兄弟、その下町のアパートに連れ込んだ中年男の三人芝居。兄トリート(佐野準)は気性が荒い不良少年、弟ハロルド(柳瀬太一)はアレルギーの発作があって外出もしない引き籠もり。謎の男フィリップ(佐藤勇太)が外の風を吹き込んで兄弟を徐々に変えていく-。
「Touch」は象徴的なタイトルだ。アパートの中でお互いがタッチすると鬼の役回りが代わる。別の立場になる。フィリップに触られたハロルドは親の温かみを知る。ハロルドから逃げていたトリートもついに自分から抱きついていく。生きていくため、食っていくために金品を奪ってきた兄。戦争、貧困、独裁によって親を失った子供たちは今も世界中で泣いている。
「星の王子さま』は1500ステージ、「ヘレン・ケラー」は900ステージ、「肝っ玉おっ母とその子供たち」も600ステージを越えているようだ。風のレパートリーシステム、ロングランシステムは演劇による勇気の風を送り続けているのだろう。風のレパートリーシステム、ロングランシステムは演劇による勇気の風を送り続けているのだろう。
(平成25年12月26日)
60歳で恋なんてやり過ぎ? 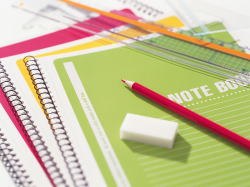
12月12日に開幕した劇団四季のミュージカル「マンマ・ミーア!」のキャッチコピーは「20歳で結婚って早すぎる?」「40歳で恋なんて遅すぎる?」
なれば、追加しよう。初日を見ながら浮かんだのが-。
「60歳で若い恋なんてデキすぎ?やりすぎ?」
さらに「80歳で深い恋なんて不思議?」
樋口麻美が演じた母親ドナは、江畑晶慧演じる一人娘ソフィの結婚を悩んでいる。まだ二十歳。人生は長く、結婚は早いと思うともいう。そう言う本人は2か月もしない間に男性3人と関係を持ち、妊娠した娘がソフィ。シングルマザーとして骨身を惜しまずホテルを経営してきた。
娘ソフィは婚約者スカイ(竹内一樹)を愛し、母親とは違う幸せな人生を送りたい。「この愛をかなえて、お願い」と幕開けで歌うその一言が彼女の一貫して思いであり、作品の主題でもある。夢に向かって20歳での結婚は決して早くはない。
ドナは突然、来島した男性三人に驚き、戸惑う。ソフィが自分の父親を知りたいと願って送った結婚式の招待状。三人の中の一人が実の父親なのだ。「一人が自由でいい」とドナは歌うが、尻軽だった若い頃の恋する思い出は今も忘れていない。40歳でもう一度、恋をする。いいじゃないか。
60歳になったソフィはきっと知るだろう。平凡だが、前向きに生きてきた結婚生活でスカイとの新しい“若い恋”を。それは第2の愛だろう。
80歳になったソフィは知るだろう。愛とは相手の魂、運命、地球に生まれた宇宙の不思議を大切に思う心だと-なんちゃって! そのためには夫となったスカイよ、“ダンシング・キング”になれ。そう想像しながら見る舞台はどうかな。
ところで、男性三人の中のハリーの味方隆司。その地味さを買うねえ。
(平成25年12月26日)
鈴木京香の声と肢体 
女優鈴木京香が大胆にも挑戦した一人芝居「声」に息を飲んだ。シス・カムパニーがスパイラルホールで12月18日から上演した作品はジャン・コクトー作、三谷幸喜演出。一人芝居に目がない当方としては見逃すはずはない(12月26日まで)。
舞台では「双頭の鷲」や「恐るべき親たち」、映画では「美女と野獣」や「オルフェ」で知られる劇詩人コクトー。「声」はフランスでの初演が1930年だから日本では大正5年。83年も前に一人芝居を書いていたのだ。
京香さんは今、45歳。初日は約320人の観客の前で1時間強、黒電話の受話器を左手にしゃべり続けた。相手は別れた、あるいは別れてしまいそうな男。ダブルベッドの上で、さらには受話器を持って移動しながらネグルジェ姿を晒すのだ。
三谷はパンフレットに書いていた。
「鈴木京香さんの、軽やかで伸びやかな演技」「まるで彼女の私生活を覗き見しているような、至極の時間」
その含み気味の声と台詞廻し、その透明感のある悩ましい肢体。時に両の素足が露出するのを見ると、その辺りばかりに目が行ってしまう。
「愛してる、愛してる」と4回も繰り返す女の本心かどうかわからない心情。彼女のような美しい女性に「愛してる」と何回も言われ続ける男って誰? まあ、ジャン・コクトーなのだろうが、怒り、ねだり、狂ったような女を演じた京香さん。待ちかねた電話の鳴る音に鋭く反応して、ちょいと遠い辺りからベッド上の電話機に飛び込んだりさせた三谷演出。男って、こういう場面をやらせたい、そんな初の一人芝居だった。
(平成25年12月26日)
「ええから加減」の再演 
昨年7月に初演されて菊田一夫演劇大賞を受けた「ええから加減」がシアタークリエで再演された(11月26日まで。その後は12月12日まで金沢、名古屋、新潟、札幌などを回る)。
コンビを組んで25年の上方漫才師、藤山直美演じる濱子と、高畑敦子が扮する宇多恵。50歳の濱子は主夫業にいそしむ料理上手の亭主にイライラ、49歳の宇多恵は所属会社の専務と不倫。上のステージを目指して上方演芸大賞に挑戦する、という物語で、見どころは二人の漫才芸だ。
初演でもその漫才は楽しめた。今回は新ネタに入れ替えている。しかし、冒頭の漫才には閉口した。下ネタは面白くない、えげつない。もちろん芸達者な二人の話芸、仕種によってお客は手拍子、大笑い、ばか笑い。2回目の漫才では「勝手に上げるな、消費税」と直美が笑いを取ると大きな拍手。だが、笑っている場合じゃない。「もっと怒れよ、安倍政権に!」と、むしろ観客に腹が立ってきた。
それはそうと、直美は凄い。濱子の自宅へ宇多恵が新ネタの相談に行く1幕の夕食場面。亭主の作ったおでんを食べる演技、話し言葉を飲み込むパントマイムの芝居。絶妙、座布団10枚をあげたいくらいだ。一方、高畑もやるじゃないか。「コケコッコー!」と鶏の鳴き声を真似る。3回もやったが、巧いもんだ。そして、直美は「その玉子、私が産んだ」といい、玉子を産むギャグ。この場面だけでももう一度、菊田一夫演劇大賞を差し上げたいほどだ。
二人に下ネタはいらない。次はブラックユーモアを願いたい。
【写真】「ええから加減」。左より藤山直美、高畑敦子
(平成25年11月25日)
樫山文枝が面白い! 
井伏鱒二の原作を吉永仁郎が脚本化し、高橋清祐が演出した劇団民芸公演「集金旅行」(9月18日~30日)が秀作だった。
職業不詳のコマツランコという女性を演じた樫山文枝が傑作だったからだ。
東京・荻窪のアパートの七号室の住人、七番さんことコマツランコ。アパートの主人が亡くなり、担保に入った安アパートの部屋代を踏み倒した居住者から滞納金を取り立てる旅に出る。小説家の十番さんに同行するのだが、旅を続ける中で正体不明の女性ランコの人生も浮き出る。これが樫山の手柄だ。
岩国ではかつて自分を強引に抱いた名士から三百円を払わせた。料亭の酒席でその一件を思い出させながら、またまた肉体に迫るすけべ名士をかわすところなぞ巧いものだ。福岡では、同行の小説家の邪魔にならない程度に押さえた芝居になる。
男と女の間で泥水を飲んできたしたたかな女性かと思えば、ただひたすらに懸命に生きてきた平凡な女かとも思える。あえてくどい演技をしなくても、フッと笑いが起きる素敵な女性を造形していた。
自然体のコメディエンヌ。コマツランコは樫山文枝の代表作になる、と思った。
(平成25年10月22日)
音尾琢真にしびれた 
しびれた。長く舞台を見続けて、楽しみにする一つが才能の発見だ。
音尾琢真、「おとお・たくま」と読む。その舞台はサム・シェパード作「トゥルー・ウエスト」。内野聖陽が兄リー、音尾が弟オースティン。粗野な兄は砂漠で生活して、こそ泥を働くならず者、一方の弟は一流大学を出て成功した映画の脚本家で妻子もある。
母の家で創作中の弟の前に、5年ぶりにふらりと兄が立っている。愚兄賢弟というけれど、この兄弟は単純にそうも言えないようなのだ。
兄のリーは乱暴で自分勝手で、内野は加えて孤独で寂しがり屋の一面を出していた。
弟のオースティンはどうか。
一幕では、兄からぼろくそに言われ、頭を小突かれたり、金をせがまれたり、やられ放題。二幕になると、しかし、ガラリと別人のようになった。その演じ分けにしびれた。
兄が語るシナリオのストーリー、台詞をタイプで書き取っていく芝居、自分よりも優れた発想を内包していた兄に気付き、嫉妬や不安を浮かび出す演技、自分の中にも暴力的な血が流れていた事を示す殴り合い、そして兄の首をギリギリ締めていく狂気。
音尾琢真という名前を覚えてほしい。
(平成25年10月7日)
新鮮な「かもめ」 
チェホフは「三人姉妹」の中で100年後の人々がどのような生活、人生観を持って生きているかを想像し、後続のその人々のためにより良い世界を作るのがその時代の責務だと書いた。
ケラが演出したシス・カンパニー公演「かもめ」は主に女性四人の登場人物が新鮮に思えた。
大竹しのぶが演じた大女優アルカージナ、蒼井優が演じた女優志望のニーナ、使用人でシャムラーエフの妻ポリーナ、これは梅沢昌代の役柄、そして西尾まりの役がポリーナの娘マーシャである。この女性たちに限り、100年後の人々のために生きていたとはとても思えない。少なくとも夢や欲望のため、つまり自分自身のためにがむしゃらに生きた女性だ。しかしそこが面白いし、それこそ人間というものだと思わせるのだった。
女優の役を演じた大竹は愛人へのむき出しの独占欲を隠さない。母親として一人息子トレープレフへの愛情はせいぜい人並みで、それが大女優たる由縁だと思わせる。
蒼井のニーナは都会に憧れ、田舎からの脱出に人生を賭ける。恋人トレープレフは幼く見えるし、乗り換えたトリゴーリンへの恋心も女優への道の打算とも思える。
梅沢のポリーナは性欲と不倫願望の塊かと思えて、このようなポリーナは初めて見た。
西尾のマーシャにしても自分の環境を嘆くだけではなく、人生を変えようというしたたかさを出していた。
男たちは女性の欲の渦に巻き込まれている。そこにケラの演出の喜劇が生まれる。
演劇青年であり作家となるトレープレフは流行作家トリゴーリンの文章力に嫉妬するが、トリゴーリンさえ自分は偉大な先人作家の足元にも及ばないと嘆く。「かもめ」でいつも面白く思えるのがこの関係。巧みな表現はないか、常にそれを模索しながらメモを欠かさないトリゴーリンは、今の私と重なる。
【写真】(左から)大竹しのぶ、生田斗真、野村萬斎。撮影:谷古宇正彦
(平成25年9月20日)
モリー教授の遺言 
「死ぬというのは悲しいことだ。だが、不幸せに生きているってのは、もっともっと悲しいことだ」。老教授モリーが教え子のミッチへ語る。目の前に老人が立っているのに席を譲ろうともせずに携帯電話依存症になっている電車内の人を見ると、この言葉を自分と重ねてしまう年齢になってしまった。
加藤健一事務所「モリー先生との日曜日」は、見方によっては押し付けがましい教訓的な台詞が鼻に付くかもしれない。しかし一方で、モリーとミッチだけの二人芝居。その台詞に耳を傾ければいい。
加藤健一が演じるモリー教授は社会学を教えている。一幕冒頭。4種類のダンスを踊る。難病である筋萎縮性側索硬化症によってわずかな余命しか残されていない。このダンス場面が後々、悲しい対比となる。
加藤義宗が演じるミッチは人気スポーツライターとして大成功している。恩師の病気を知って16年ぶりに再会し、以来、火曜日には無理を押してでも教授の自宅を訪ねて“名言”を録音していく。
一番最初に紹介した言葉だけでなく、社会学の先生らしい教訓がふんだんに吐かれる。
「人は誰でもコーチが必要だ」
「人の心の痛みを知らなきゃいけない」
「人間、さぼれるうちにさぼっておいた方がいいよ」
「どう死ぬかを学べば、どう生きるかはおのずと見えてくる」
生徒は先生から学び、また、先生は生徒から学ぶーとは古今東西の教え。素晴らしい恩師を持てた人の幸福はこの上ないだろう。この舞台はそれを教えてくれる。
杖を付いてゆっくり歩む加藤健一の後ろ姿、苦しい呼吸の中、数字を18まで数える演技。大好物のエッグサラダを食べられず、スプーンを落としてしまった後の間(ま)。情けない、哀しいー。その芝居と演出。それを見つめるミッチの義宗の芝居がいい。
だが、何と言っても胸を打つのは、人は必ず死ぬのだ、という厳然として事実に早く気付き、それを意識して生きて来なかったのが悔やまれると演じる場面。モリー教授は早くに母を亡くしていたのだ。モリー教授のその“遺言”をどう聞くか。この舞台の真骨頂である。
【写真】左より加藤健一、加藤義宗。撮影:石川純
(平成25年8月19日)
「父よ!」の再演を! 
既に終演となったが、田村孝裕・作・演出「父よ!」に触れたい。アル☆カンパニーほかの企画制作だが、再演、あるいは他の作品でも良質の演劇公演をアル☆カンパニーに挑戦して欲しいからだ。
見たのはシアタートラム。豊橋、神奈川を回っての東京公演だった。
出演者が嬉しい。つかこうへい事務所で鍛えられた平田満、井上加奈子夫妻、井上ひさしさんが「名優だ」と書いた花王おさむは東京ヴォードヴィルショー出身、ベンガルは自由劇場・東京乾電池、徳井優も自転車キンクリートの舞台でお馴染みだ。皆が芝居好きの連中だろう。個人的には「熱海殺人事件」の婦人警官がステキだった若き日の姿が重なる井上加奈子が今でも見落とせないのでして。
作者の田村は手練のストーリーテラーである。
母が亡くなり、残された85歳の父親を息子4人の誰が面倒を見るのか。長男が花王、次男がベンガル、三男が平田、四男は徳井。父親の世話をしてくれているらしい近所のおばちゃんが井上だ。
息子どもは借金を抱えていたり、生活能力に不足していたり、それぞれの事情をボヤいて、逃げてしまうー。まあ、良くある話だ。四男が五十過ぎだから、中年を通過して人生に疲れが見える兄弟たち。俳優陣は自分の個性を確実に現しながら、軽妙な間(ま)、不思議な台詞の言い回しによって良質の“喜劇”を作り上げていった。
劇中劇のようにいくつかの回想場面が出てきた。そこでは息子たちのそれぞれが後ろ向きで父親と電話で会話をするが、その手法が面白い。亡き母が生前言っていた「相撲で決着を付ける」をやってみせる終幕近くの場面。また、燕尾服の男性(父?)が手品を披露する幕切れ。腕のある俳優によって昭和の男たちへの挽歌になった。
それにしても、だ。下ネタや長男のハゲ頭に触れる場面など必ず大笑いした中年男やデリカシーがない高笑いの女性客にはうんざりさせられた。何とかならないものか。まあ、どうにもならない兄貴の女房か!
(平成25年7月23日)
「香華」、雑感 
新橋演舞場「香華」(7月22日まで)を見て、つくづくと思い到ったのが母と娘の愛情と絆だった。
有吉佐和子・原作のこの舞台化では山田五十鈴の母・郁代が絶品中の絶品。自ら十種の一つに加えたように、自由奔放に生き、突然死する主人公は女性にとって理想像であり、嫉妬の対象であり、自分を客観視できる生き方にも思える。腹を痛めた我が子とはいえ、人生観が全く違う一人の女性として娘を見る母親。ベルさんの郁代だった。
池畑慎之介☆(この☆を新たに加えたのが芸名)の郁代、娘は高橋惠子。
この高橋の芝居によって、娘の目から見た母親、そして母と自分との相違、娘はいくつになっても母親を慕い続けるーという一人の不運な女を思ったのだった。
その時、郁代間もなく64歳、朋子48歳。自動車事故で母が急死する。お腹の激痛を訴えた娘を助けるため救急車を呼ぶのに外へ出たのだった。朋子は退院した日、母の遺骨にすがり付いて号泣する。ここが泣ける。「お母さん!何回も何回も呼びかける。
四度も結婚して、自分を捨てた母。芸者に売られ、一度も結婚出来なかった自分。それでも自分の身代わりとなって命を助けてくれたのだーと思う娘。
世の中には母親を許せないと公言する娘もいる。「香華」を見た女性の観客は笑い、泣き、溜め息を付く。そんな芝居である。
(平成25年7月23日)
王様と猫の欲と勇気 
この夏、劇団四季のファミリーミュージカルを2本見た。
「はだかの王様」(日生劇場)と「人間になりたがった猫」(自由劇場)だった。ファミリーミュージカルで最初の1964年に上演された作品が「はだかの王様」。「人間になりたがった猫」は1727回という最多上演回数を重ねてきた作品だ。
2本に共通するのは「欲」。自慢できそうな最高の衣服を着たいと求めるのが「はだかの王様」の王様の欲望。動物の中で一番賢いと思えた人間になりたいと願うのが「人間になりたがった猫」で白と黒のブチ猫・ライオネルの欲。
「はだかの王様」のテーマは、生きる上で大切なこととは何か。勇気、愛、友情、生命の尊重ー。これはファミリーミュージカル全体に共通している。子供たちに気付いて欲しいテーマだが、中でも今回、ふと気付いたのが「勇気」だった。
「人間になりたがった猫」のライオネルは猫から人間に変化したいという。町の人々から毛虫のように嫌われる衛兵隊長スワガードに立ち向かい、しかし、スワガードが火を付けたホテルから彼を救い出す。「はだかの王様」では、権力者の王様に誰も意見や忠告を言えない周辺に対し、敢然と「王様、あなたは、はだかです」と真実を告げる。これも勇気。「欲」に対抗する一つは勇気!
四季のファミリーミュージカル、なかなかやるわい。
(平成25年7月23日)
ドレッサーの醍醐味 
三谷幸喜さん、さすがですなあ。橋爪功さん、もう名優の域ですねえ。大泉洋さん、驚くべき才能に見惚れましたよ。
シス・カンパニー公演「ドレッサー」は間違いなく、今のところ、№1の舞台。いつ見るか。今でしょ!(と、つい流行りを使ってしまった)
ロナルド・ハーウッドの傑作である。いわゆる幕内ものだが、ただの楽屋内ものではない。これは、俳優の、いや、人の持っている執着、矜持を描いて飽きない。
橋爪は地方を巡るシェイクスピア劇団の老座長を的確に、また、衒いなく演じる。この日の演目「リア王」の最初の台詞が思い出せない、楽屋の外で3度回って正常に戻る、妻に叱られる、付き人ノーマンを怒り散らす。笑いを取ろうとはしないのだが、座長が置かれた苦しい立場や近づいてきた死期を予感する老いの恐怖を演じていくと、自然と可笑しく見えてくる。芸である。
大泉は、身勝手な座長に尽くしに尽くすノーマン。座長が光りながら影法師。汚れた服を着替えさせ、忘れた台詞を伝え、励まし、座長の言い回しを演じて見せる。遺言のような座長の感謝の気持ちの中に自分の名前がない。奥様以上に尽くしたはずなのに、自分の半生は何だったのか。先代の勘三郎は「自分の棺桶に小山三を入れておくれ」と大切な影法師を忘れてはいなかった。ノーマンは、しかし、消えてしまった光を前に泣き崩れるのだ。大泉はそんな全ての演技に冴え、技術の限りを披露し、台詞の歓急にも抜かりがない。「ベッジ・バードン」で舞台俳優としての才気を示したが、魅力的な舞台俳優としてまた一段、成長した実力を示した、と思う。
三國連太郎、加藤健一、渡辺えり子のトリオ、三國連太郎、柄本明、三田和代のトリオ、そして平幹二朗、西村雅彦、、松田美由紀の組み合わせ。「ドレッサー」を見たのは今回が4回目。一番楽しめた。それは、三谷の演出の賜物である。自作ではない、翻訳劇の傑作を冷静に、さらに深く、客観的に施しながら作り上げた。俳優の演技を引き出し、関係性を練り上げ、装置を多様化した。喜劇であり不条理劇であり、悲喜劇であり、正統演劇であり、つまり、演劇。劇場でしか出会えない醍醐味だった。
【写真】橋爪功(右)と大泉洋(左)。撮影:古谷宇正彦
(平成25年7月1日)
堤真一の「断色」 
「時には母のない子のように」と歌ったのは誰だったか。青木豪・作「断色」(青山円形劇場。7月7日まで)で、時に流れる「カントリーロード」を耳にしながら「時には~母の」が心の中に聞こえたような混沌とした気分に浸っていた。
エロ、グロ、ナンセンス、もう一つ、グロテスク。「断色」は吐き気がする食材が詰まった野菜炒めに似て、また、異なるものだった。
たとえ、クローン人間の母でもいい。もう一度、会いたい。短期間でも生活をやり直したい。母親に限らず、亡くなった肉親と会いたいと願う人は少なくないと思う。製造したクローン人間を使って、それが商売になる時代はすぐ近くに迫っているのかもしれない。
堤真一が演じた小杉保は息子、麻生久美子の朝子、夕子は母であり一人の女性であり、田中哲司の刈谷基はクローンを商売とする男。この三人芝居が野菜炒めの食材を食べ尽くす。
親に愛されない子ほど悲しいものはない。子供を愛せない親ほど哀しいものはない。「断色」には、吐き気がしても呑み込むべき苦い味がした。
【写真】撮影:田中亜紀
(平成25年7月1日)
「鹿鳴館」もう一つの見方 
劇団四季が上演中の三島由紀夫・作「鹿鳴館」は、作者が「筋立ては全くのメロドラマ」とした傑作戯曲なのは知られている。しかし見方によっては別の世界が浮かんでくる。劇団の7年ぶりの再演では、一人の女性を愛する二人の男の対立だけではなく、政治家の対決という視点がくっきりと見えたのが新しい発見だった。
舞台は明治19年。鹿鳴館で催される舞踏会に向かって筋立ては仕掛けられている。
時の内閣の大臣、影山悠敏伯爵。その政敵で反政府派のリーダー清原永之輔。権力者と反権力者は主義主張は当然違う。西洋に短期間で追い付こうとした維新後の時代だ。物真似上手な黄色い猿と西洋からバカにされる日本人は、それでも頭髪を変え、和服から洋服へ、物真似は止めない。
清原は舞踏会へ自由党の残党を斬り込ませて鹿鳴館の存在を無力化させる意図だ。影山は清原の息子を使って政敵の暗殺を企む。いつの時代も政治の裏、闇の世界では何でも起きるのは歴史の常識だろう。
三島は自衛隊の変革、憲法の改正を叫んで自決した。現在を見据えれば、自民党という権力は憲法改正、自衛隊の軍隊化を目論んでいる。その政敵と言える民主党、生活の党、あるいは日本維新の会はもろくも自滅の道を進んでいるようだ。
そんな時代背景、影山を演じる平幹二朗の朗々たる台詞術、スケールは小さいが清原を演じる山口嘉三の精一杯の反骨心。二人の台詞の応酬に限って見る観劇のやり方もお勧めする。
それにしても、だ。三島には政治家の言葉が軽くなった現在の政治状況を踏まえた戯曲、新しくなった歌舞伎座で上演される新作歌舞伎を書いてほしかった。「鹿鳴館」はその事を思い起こされる舞台でもあった。
【写真】撮影:上原タカシ
(平成25年6月11日)
さようなら、ル・テアトル 
黒柳徹子と大森博史の二人芝居「ステラとジョーイ」をもってル・テアトル銀座が上演26年の歴史の幕を降ろした。
海外コメディシリーズを1989年から上演し続けた黒柳の涙もさりながら、演劇関係者にとっては違った形で格別の惜別感があったことを記そう。
5月29日から31日までたった3日間の公演の初日、隣合わせたシェイクスピア学者で評論家の小田島雄志さんと開演前、その話になった。
話とは、大河内豪さんの思い出である。
大河内さんは演劇界では知る人ぞ知る演劇人だった。東宝に勤務し、前の東京宝塚劇場、帝国劇場の支配人を歴任して、銀座セゾン劇場準備室長として汗を流していた。セゾン劇場はル・テアトル銀座の前名だ。
大河内さんは昭和60年12月19日、急逝した。鉄道に身を投げたのだった。夢と理想を掲げて奔走した新たな劇場のスタートを見ることなく、51歳で命を断った。
その前日は小田島さんの55歳の誕生日。自宅で開くパーティの常連だった大河内さんも参加したのだという。参加者は上等のワインで祝杯を上げた。その時の様子を語ってくれた小田島さんは、無念の思いで亡くなった友人の闘いを静かな口調で話していた。
東京宝塚劇場の支配人の時、“ベルばら”ブームの真っ最中。大河内さんにはその取材、あるいは宝塚劇場の象徴である大階段を新調した詳細などを聞いた。小田島さんの話を聞きながら思い出していたのだった。
劇場には多くの思いが詰まっているものだ。「こんなにいい劇場はなかった。思い出は尽きません」と千秋楽で黒柳は泣いた。
セゾン劇場-ル・テアトル銀座。大東京の銀座の一つの劇場が消える。しかし、一人の演劇人が賭けた演劇への情熱は忘れられない。
(平成25年6月11日)
二人芝居2本 
“二人芝居”を立て続けに2本見た。それも、ともに女優による舞台だ。
5月15日に下北沢・OFF・OFFシアターで村岡希美と池谷のぶえの演劇ユニット「酒とつまみ」の公演「もうひとり」。16日は赤坂・レッド・シアターで真野響子と眞野あずさ姉妹によるトム・プロジェクトプロデュース「完全姉妹」。
「もうひとり」は遠心力に圧倒された。もう若くはない独身女性がぶつかり合う。村岡の部屋へ住み込んだ池谷。親友のようで、性格が合わないようで、恋人が訪れてくるという村岡は貧乏な池谷を追い出したくもあり、引き止めたくもあり…。
その部屋におせっかいな隣人女性とかがやって来るのだが、その人物は登場せず、二人は実際に居るように会話し、演技をする。ここが腕の見せ所。パチンパチンと台詞がぶつかり、見る側は弾かれそうなパワー全開の芝居だ。村岡も池谷も小劇場などでは存在感たっぷりの脇役で知る人ぞ知る実力派。狭いセットが壊れるかとハラハラした。
「完全姉妹」は求心力に浸った。
姉の静子が真野。娘が一人いるが、夫の三回忌を迎えたコンサルタント経営の金持ち。勝ち組だ。
妹の風子が眞野。介護の会社に勤め、管理職になった独身。姉に金銭を頼る負け組だ。
1幕では両親の思い出話やら、それぞれの性格分析といったとりとめのない話が続く。
2幕になると様変わり。実は同じ一人の男性を巡って恋愛をしていたのだ。
姉はその男に振られ、妹が結婚していた。勝ち負けが逆転してしまった-。
台詞はあくまで押さえ気味。激高などしない。静かな、穏やかに進む姉妹である。美人姉妹で知られる女優二人。不倫でもいい、お付き合いしたくなるように思わせる魅力を振りまくので、引きつけられる。
昔々、その昔。真野が女優デビューしたNHK「出逢い」で、演出の和田勉さんからインタビューしてくれと頼まれたのを想い出した。彼女のインタビュー第1号だったっけ。相変わらずお美しいですな。
(平成25年6月2日)
名優のパイの味 
“いっちゃん”と“しのぶちゃん”はやはり並みの俳優ではないのかしらん?
青山劇場で上演中のミュージカル「スウィニー・トッド」で共演の市村正親と大竹しのぶは2007、2011年に続く再々演の舞台。演出の宮本亜門がプログラムで「舞台のシーンが夢に出るか」と水を向けていた。ところが「うなされない」と二人ともにキッパリ否定。気分転換が早く、図抜けて太い神経を持っているようだ。
美しい妻を奪われ、無実の罪で流刑となった理髪師ベンジャミン・バーローが市村の役。復讐の鬼となって、鋭利なカミソリで次々と首を切り裂く冷血鬼だ。
パイ屋の主人ミセス・ラヴェットが大竹しのぶ。パイにはミンチにした死体の肉を入れて金儲けをする守銭奴だ。
吹き出す血液、手は血みどろ。殺人を楽しむような悪人を演じて3回目なのに、二人は一向に「うなされない」のだという。
ところが、我が方は唸った。
ソンドハイムが作曲した歌はどれもこれも難曲ばかりだ。「世界一のパイ」とか「パーラーソング」も歌手泣かせ。「牧師はいかが?」では、いろんな職業の人の人肉を加えたパイについて歌い並べる。「役者は?」と、しのぶ。「臭い!」と、市村。こんな具合の難曲を二人は演技としての歌に変えていく。
初演では復讐の鬼となった市村一人が浮き上がって見えたが、上演を重ねて徐々に復讐の頂点へ向かっていく過程が深まっていた。
最高のミュージカル俳優の一人“いっちゃん”と最高の舞台女優の一人の“しのぶちゃん”の共演。二人をミンチにしたパイはどんな味かしらん?
(平成25年5月31日)
沢村一樹の惚けた味 
畠中恵・原作の時代劇「しゃばけ」は東京公演が終わり、5月7日から大阪・新歌舞伎座に舞台を移す。
奇想天外な物語、鄭義信の脚本・演出なので大いに期待したが、途中から俳優を中心に見ることにした。
主役・一太郎の沢村一樹、母おたえ、祖母おぎん2役の麻美れい、手代・仁吉の山内圭哉、おみねの阿知波悟美、おしまの池田有希子、父の久保酎吉。妖怪変化といった役をやらせれば腕達者の中で、沢村一樹が不思議に浮いていなかった。それが驚き。
まず、麻美れい。彼女に何が起きたのかと思うくらい、弾けていた。はしゃいでいた。今や演技派だと見ているが、恐らく、これでいいのだ。役柄を広げるー。白石加代子に負けない怪優へ!
山内圭哉のかつら顔も笑うねえ。それだけじゃない。相手役の芝居の時でも、ちゃんと自分の役を細かく演じていた。
美空ひばりの物真似をさせたら一流の阿知波悟美。この舞台ではよくまあ動き回っていたこと。
池田有希子、あなたは凄い。「リトル・ショップ・オブ・ホラーズ」でも個性が光ったが、暴れたら誰にも止められない演技をしますねえ。
久保酎吉。早替わりの連続、ご苦労さんでした。喜劇俳優でもあったとは!
さて、沢村一樹。ちょんまげが似合うのが意外でした。二枚目の浅見光彦シリーズと比べて、癒し系というのか少し惚けた味の若旦那役。周囲の俳優たちが騒ぎに騒ぐと、余計に目立つのが面白い。舞台は2度目らしいのだが、ファッションモデル出身だからか板に付いていたのは褒められる。浅見光彦のミステリー現代劇もいけるでしょう。
【写真】撮影:川並京介
(平成25年5月3日)
アニーを見て、泣こう 
「ミュージカル「アニー」が青山劇場で上演されている。思い出すなあ~。
日本初演が1986年。その制作発表の時、まだ現役記者だった。内容、意図を説明する関係者にある大新聞の記者が質問した。
「今の日本に孤児が主役のストーリーなんて理解されるんでしょうか?」。
唖然とした表情の関係者、他の記者。今年が上演28年目。ロングランを続けるヒットとなったのが答えになっている。
初演のアニー役が猪木寛子ちゃん、菅野志桜里ちゃんのダブルキャスト。寛子ちゃんはアントニオ猪木と倍賞美津子の娘さん。志桜里ちゃんはその後、政治家になった。
翌年1987年の再演に当たり、アニー役の志桜里ちゃん、西部里菜ちゃん、グレース役の鳥居かほりが舞台のニューヨークへ渡った。キャンペーンだった。市内ド真ん中の摩天楼を見物し、名物の馬車に乗り、いよいよ当時のコッチ・ニューヨーク市長の部屋に招かれた。
作品の中盤、ワシントンのホワイトハウスでルーズベルト大統領の前でアニーが歌う場面がある。「トゥモロー」だ。子役の二人はその名曲をコッチ市長の前で歌った。当時、「アイラブ・ニューヨーク」キャンペーンの真っ最中。恥じることなく、明るく歌う二人を見ながら市長は満面の笑み。まるで舞台の場面と同じような光景だった。
9代目ウォーバックスの目黒祐樹は8年目で歌も上達し、役を手の内に入れた。グレース役は岩崎良美が9年続け、今回の彩輝なおは3年目になった。品があるのがいい。ルーズベルト大統領の嶋崎伸夫は12年連続。貫禄が付いた。幕開け冒頭の孤児院の場は、何回見ても泣ける。是非、何回でも子供に見せて欲しいミュージカルだ。
【写真】Annie2013 c NTV
(平成25年5月3日)
宮沢りえの不思議 
新国立劇場でのシス・カンパニー公演「今ひとたびの修羅」(4月5日~同29日)は尾崎士郎の原作小説「人生劇場」を宮本研が脚本化している。
「人生劇場」と言えば村田英雄の歌。14回映画化された中では1963年の沢島忠監督作品、東映「人生劇場・飛車角シリーズ」が強烈な印象を残す。飛車角が鶴田浩二、吉良常が月形龍之介、宮川が高倉健、青成瓢吉が梅宮辰夫、そしておとよが佐久間良子。「残侠編」であり、任侠のニオイがプンプンとスクリーンを覆う作品だった。
昭和初年の晩春から始まる。義理と人情を金科玉条に生きる任侠の男ども。恩義、兄弟の契りには命を懸けて闘う。そんな男を愛してしまった女も命懸けで純愛を貫く。
で、配役である。
飛車角が堤真一、吉良常が風間杜夫、宮川が岡本健一、瓢吉が小出恵介、おとよが宮沢りえ。これに黒馬先生の浅野和之、お袖の小池栄子、横井に鈴木浩介。さすがはシス・カンパニーの北村明子プロデューサー。顔ぶれといい、役回りといい、いのうえひでのりを演出に起用した手腕といい、お国の劇場での任侠物の上演といい、恐れを知らない敏腕である。
「残侠編」ではあるが、むしろ「愛欲編」に軸足を置いた舞台だった。
一に、りえ、二に堤、三に浅野、鈴木、岡本、そして別格が風間。
一の、りえ。飛車角に体ごとぶつかり、胸にしがみつくおとよ。抱き寄せられるのではなく、飛び込んでいく。飛車角の3年間の刑期の間に弟分の宮川に乗り替えてしまう尻の軽さ。布団の中で宮川ににじり寄る色情の女である。「心の中に虫がいる」と言われ、男の肌が恋しくなる虫を飼う女だ。「寂しい」という。性愛を求める業といえばそれまでだが、ご都合主義の女とさえ思える。しかし、おとよのりえは、それさえ許される心境になる。不思議だ。彼女の芝居が持つ不思議。
風間、堤、岡本は任侠の味は薄いものの、その反面では平成の世、義理と人情の世界は遠くなりにけりと思わせるのである。
(平成25年5月3日)
おのれ三谷幸喜、野田秀樹 
「チェックメイト」とはチェスの用語で「詰み」を意味するという。キングが詰まされる、つまり勝敗が決着する「終わり」だ。
「チェックメイト」といえばアメリカの連続ドラマ「コンバット」でサンダース軍曹が「チェックメイト、キング2、こちらホワイトロック」と司令部に連絡する場面が印象的だった(古~い!)。
さて、新作「おのれナポレオン」(東京芸術劇場、4月9日~5月12日)で三谷幸喜は何ともしたたかな仕掛けを施していた。
詰ませるキングは、ナポレオンである。病死か暗殺(毒殺)か、あるいは自殺か。大西洋の孤島セントヘレナ島へ幽閉され、最晩年の日々を送ったこの流刑地で死んだナポレオンの死因とは?。今だに謎が残る英雄の最期を歴史ミステリーという手法で詰めていった。ナポレオンを演じたのが野田秀樹。鬼才同士の決闘の火花が散った。
俳優野田は持てる限りの演技術を次々と繰り出す。走る、踊る、とぼける、作り阿呆になる。小柄な身体を精一杯に動かせ、奇声、罵声、幼児声、その他エトセトラ…エトセトラ。短気で傲慢で小心者といった英雄を対照化させてしまう。1日の生活ぶりを再現する場面。希代の戦略家で軍人のナポレオンである。“早飯、早糞、芸の内”と父から私は怒られたものだが、ナポレオンは飲み込むように早く食べ、ジョギング、ストレッチに明け暮れ、それを何回も繰り返す演技が笑える。
島に同行した副官シャルルは山本耕史。その妻でありながらナポレオンの愛人となるアルヴィーヌは天海祐希。この二人が殺害をもくろむ。首を締められ、鈍器で頭を殴打される。ところが七転び八起き。不死身なのか、ナポレオンは蘇生してくる。天海がコメディエンヌの資質を充分に発揮し、山本が復讐の炎を燃やす二枚目ぶり。スタイル抜群で長身の二人の間に入った小柄な野田との不釣り合いがまた笑いを起こす。
主治医アントンマルキの今井朋彦が達者で堅実な芝居。セントヘレナ総督ハドソンの内野聖陽がナポレオンとのチェスの対決場面など硬軟自在の演技である。
そして、謎の死因とは?
ミステリーで結末を明かすのは反則だ。ナポレオンは登場人物(侍従のマルシャン=浅利陽介を含む)5人を動かせて仕上げの計画を実行する。三谷幸喜は俳優5人をチェスの駒のように動かせて詰めていく。
おのれ三谷、野田! 次ぎは野田の戯曲、三谷の主役という立場の逆転で「チェックメイト」だ。
【写真】おのれナポレオン(東京芸術劇場プレイハウス)撮影:石川純
(平成25年4月23日)
父と娘のリトルマーメイド 
劇団四季のロングランミュージカル「リトルマーメイド」が4月7日に開幕した(大井町・四季劇場・夏)。
劇団のディズニー・ミュージカル4作目だ。ヒロインの人魚姫アリエルが、憧れる海の上の世界へ、そして地上の王国の王子エリツクと結ばれるハッピーエンド。
テーマはいくつかある。
父と娘の愛情と絆、困難を乗り越えて勝ち取る愛、自分の居るべき家・場所を探る事。子供から大人までに伝えたいメッセージは「美女と野獣」、「ライオンキング」、「アイーダ」という先行した3作品とも共通している。
6層の額の中で描かれるが、楽しめるまず第1点はやっぱり1幕9場の「アンダー・ザ・シー」。海の中の王国は「誰もが輝くのさ」と歌われる。人魚たち、蟹やたつのおとしご、多くの魚たちが溢れる元気さで泳ぎ、踊る。まるで竜宮城である。
次ぎが末娘のアリエルが海の底から一気に上昇するフライング。そのスピード感、爽快感、美的なスリル感。さらに尾ひれを動かせて泳いでいく人魚や海の世界の王トリトルのフライングも観客は海の中にいる気分に浸れる。
カモメのタップダンスとか「魔法より強いものは思春期のホルモン」といった台詞も感心させられたし、蟹がアリエルの、侍従がエリックの教育係として対照的な存在なのも巧く描かれていた。
初日の7日の終演後に開かれたパーティーでは作曲したアラン・メンケン氏が「父と娘との愛情、成人していく娘への父の気持ちがテーマの一つです」と、自身の娘さんを例にして挨拶していた。創立60周年となった劇団四季の力量がロングラン公演で試される。
(平成25年4月23日)
栗原小巻の退団と女優たち 
劇団俳優座による三軒茶屋のシアタートラムでの公演「とりつくしま」(4月13日~24日)のプログラムを見て、「おや?」と気付いた。劇団の連名を裏表紙の内側に載せているのだが、2月26日に他界した劇団代表だった大塚道子さんの名前がない事を寂しく眺めていた。さらに女優陣の連名を目で追ったところ、栗原小巻の名前も消えていた。
彼女は恩師、千田是也さんが1994年に亡くなって以降、劇団公演の舞台をほとんど踏んでいなかった。しかし、連盟には必ずその名が記されていたのだが、この4月公演でその名は消えた。退団したのだった。
俳優座養成所の“花の15期生”出身として1963年に入団して50年。今後は完全フリーの女優で活動するのだろう。
さて、「とりつくしま」である。
東直子さんの小説を舞台化したこの作品。SF風の要素が濃い一風変わった芝居だった。死んでしまっても心残りがある人は一度だけこの世にある何かの「モノ」に取りついて、この世に戻ることが出来るのが「とりつくしま」だという。
野球少年だった長男を亡くした母は、投手が投球前などに使うロージンにとりつく。書家の先生の弟子である16歳の女性は先生の扇子にとりつく、という具合に6組のケースがオムニバス形式で進んでいく。「モノ」に取りつくのは、取りついた人への思いが残るからだ。一切、話すことができない「モノ」に取りつかれた人が感じるのは「気配」のみらしい。
母親を演じた清水直子、母親に支配され続ける娘に扮した佐藤あかり、弟子を演じた若井なおみ。俳優座には有望な女優たちが育ってきた。このほか安藤みどり、森尾舞、小澤英恵や福原まゆみもいる。“ポスト小巻”へ、さらに舞台へ取りつけ!
(平成25年4月22日)
思い浮かばなければ“沈黙” 
「第57回岸田國士戯曲賞」の授賞式が4月8日に行われました。新人・若手劇作家の登竜門とされる賞。候補作8本から選ばれたのが赤掘雅秋(41)の「一丁目ぞめき」と岩井秀人(38)の「ある女」の2作だった。
劇団THE・ SHAMPOO・HATの旗揚げから27回目の公演だった赤掘の受賞作。挨拶を書く-。
「よくもここまて継続できたと思う。自分は芸能人になれればいいと思っていました。当時25歳。演劇へは偏見の極致だったが、受け入れてくれる場所がそこ(演劇)しかなかった。三谷幸喜の『罠』というビデオを見せられ、そのパクリから我々は始まった」
さらに当時の面白いエピソードを披露した。「17年前、公演は渋谷がいいと、パルコ劇場に(スタッフが)“劇団を作ったんだけど上演させてくれないか”と電話したら2秒で断られた」
一方、俳優であり劇作家の岩井は劇団青年団の演出家。候補4回目の受賞だった。4枚にわたる挨拶文を読み上げた。
岩松了には、しゃべる言葉の演劇を教えてくれた人と話し、台詞が思い浮かばない時は“沈黙”と書くという岩松を習っているそうだ。また、平田オリザには「毎年1本書けば(岸田賞受賞の)可能性はある」と励まされたことを感謝していた。
選考委員の一人、岩松が挨拶した。
「今回は受賞作なし-と臨んだ選考でしたが途中(今回の)二人に獲ってほしいとなぜか思い始めた。休憩のトイレで野田(秀樹)と並んでしながら“赤掘君、獲ってほしいねえ”と話した。後半の、恋人から(主人公の女性が)お金を貰い始めてからつまらなくなったが、とにかく面白かったです」
また選考委員の松田正隆は「今、ポストドラマと言われるが、ドラマとは何なのかを考えさせられた二作品でした。何よりダイアローグに起点を置いて書かれているのに気付かされた」
今回のダブル受賞がドラマの復権となるか。とにもかくにも、劇作家の挨拶は面白い。ちなみに、俳優では久保酎吉、峯村リエ、鈴木砂羽らが祝福に姿を見せていた。
(平成25年4月10日)
僕はウエスカーのことを話しているのだ 
目の前の家庭劇に、ただただ懐かしさがこみ上げてきた。地人会新社による赤坂レッドシアターでの公演「根っこ」(4月4日~28日)だ。
何が懐かしいかって?
作者のアーノルド・ウエスカー。1950年代、その名は「怒れる若者たち」と呼ばれた世代のトップランナーだった。1970年代、学生だった団塊世代は口角泡を飛ばして議論の渦の中に居たものだ。町へ出て、自己主張したものだ。ウエスカー作品は晶文社という出版社、武井昭夫、小野次郎といった新日本文学グループという発信元から青年たちに受信されていた。当方といえば、“文化総反乱”という論文を投稿したのを思い出す。
さて、舞台の登場人物も懐かしい。
英国は田舎町ノーフォークで農業を営む夫婦。主人公ビーティの両親だ。働き者の太っちょの母はじゃがいもの皮を剥き包丁で切り分け、スープを作る。重いバケツのお湯を運んでタライに移す。渡辺えりが何とも上手な包丁さばきを見せたのには感心しきり。
娘を愛している父は、妻に文句ばかりを言い、喧嘩が絶えない。安給料に負い目を持っているのにそれを口に出せない。朴訥な金内喜久男である。隣人の老人スタンは「もはや昔は戻って来ない」と良き若き日を口にするばかりだ。スタンを演じた松熊信義といえば地人会新社の前身、地人会の公演の常連だったけ。
ロンドンに出てホテルのウエートレスをする次女ビーティは実家に帰って来た。同じホテルの調理人である恋人とは婚約して3年になる。2週間後にやってくるのを家族と待つのだが、話すのは恋人の口真似ばかり。両親の日常生活を非難するわ、社会主義者の彼の考えを押しつけるわ。
親と子供、都市と農村、インテリと労働階級の対立や不理解。「自己否定」とか「造反有理」という論理を思い出した。
主人公ビーティを演じた占部房子は熱弁に次ぐ熱弁。確かに1950年代では熱く語った時代だったろう。1970年代も熱気に満ちていた。
「目がくらむようなボクたちの時代」。目の前のウエスカー劇を、ただ、冷めて見つめる自分が居た。
(平成25年4月10日)
うぶな雲は空で迷う 
どうやら近未来のお話のようだった。
土田英生が作・演出の劇団MONOの第40回公演。大阪、北九州を回って東京は赤坂レッドシアターで上演された「うぶな雲は空で迷う」(3月28日~31日)。
司馬遼太郎先生は「坂の上の雲」で、一点を見据えながら突き進む明治人の気概を描いてくれた。平成の世、迷える子羊たちの我々はブーメランのように同じ地点に戻ってしまうのだろうか。
登場人物は男性5人。上演時間はジャスト90分。赤坂の地下の空間で、土田はある小島に不時着した飛行船の乗員を出した。この5人、窃盗団のメンバーなのだ。3人のグループと2人のグループが合体する。何を盗むのか、盗んできたのか、はっきりと分からない。しかし、分かってきたのは何か大きな事をしたい、どでかい事をやって、地球に自分たちの痕跡を残したいようだ。
故障を修復し、再び空中へ。ところが目的地とは違う方向へ行ってしまう。自分たちの位置さえ確認出来なくなってしまう。
責任のなすり合いが始まり、嘘を付く、暴力的になる、怒りが笑いに変わり、遊び感覚のゲームごっこで時間を費やす。ついには元の場所に向かって飛んで行くのだった。
同じ台詞を何度も繰り返す。似た場面を何回か繰り返す。そこに笑いが起きる。学習をしない人間ども。人類は地球を捨てて月に向かってロケットに乗るのだろうか。未来の事は未来人に任せよう。そんな見方をしながら「キサラ」を演じていた金替康博の天然ボケのような癒す演技になぜかホッと息を付いたのだった。
(平成25年4月2日)
魔性の女・とよた真帆 
ちょいと古いが、マリリン・モンローか加賀まりこか。「魔性の女」と呼ばれた女優の代表格だ。
とよた真帆を見に行った。東池袋の劇場・あうるすぽっとで上演された「私のなかの悪魔」(3月25日~31日)。主に三人芝居の妻を演じていた。共演は教員・佐戸井けん太、画家・高橋洋。教員は前の夫、画家は現在の夫。ストリンドベリ・作「債鬼」を翻案し、演出したのが青山真治。とよたの現在の夫である。
17歳でモデルデビューし、22歳で女優に転身したという彼女は今41歳。脂が乗った女優であり、演技術を手に入れてきた女優であろう。
スタイルは抜群だった。一度だけ披露した黒の下着姿、長い手足、妖しげに動く目付き。厚めの唇から吐かれる声、台詞には甘い香りが含まれているようだ。つまり、セクシーである。女の武器を揃えている。流行作家の妻も、とよたもそれを自覚している。
悪魔、あるいは魔性が棲んでいるのは女性に限らない。男にだって悪魔は棲みついている。決してなくならない戦争、犯罪、嘘ー。悪魔はなんでもやる。
「私のなかの悪魔」の妻は犯罪者ではないし、“小悪魔”といったものだろう。私は好きなように生きるー。前の夫にも今の夫にもわがまま、自由酢奔放な生き方を通して、蝶々のようにフワフワと空中を飛んでいるような女性を演じていた。嘘を付かずに、ただ正直に行動している。とよたを見ていると、演技をしているのではなく、自然のまま舞台に立っていたように映った。画家の夫が僕(しもべ)に似た愛の奉仕、奴隷になり下がり、前の夫にしても罠を仕掛けて妻を誘う。とよたの妻は、しかし、男を愛する女であり、今の夫を愛している。愛と自由と正直。青山夫妻は「悪魔という名の正義」、「坂の上の幻影」を描いていた。
(平成25年4月1日)
ハムレットは現代の悩み 
劇団四季による浅利慶太・演出の自由劇場「ハムレット」(3月17日~4月4日)。
「権力を摑んだ男」…兄を殺した新王クローディアスは、保守に走り、罪の意識に苛まされて疑心暗鬼となり、国を滅ぼして自らも死に至る。現代の独裁国家を見るようだ。
「復讐の連鎖」…尊敬する父を殺されたハムレツトは宰相ポローニアスを殺害。その息子・レアティーズは最愛の妹・オフィーリアの死と父の死の復讐へ、ハムレツトと闘う。ハムレツト、レアティーズは死んでいく。王家と一つの家庭が滅んでしまう。目には目を。被害者は加害者を裁けないのか。死刑制度に反対するのは是か非か。
「領土問題」…ポーランドに進軍するノルウェー軍の王子フォーティンブラスは、僅かな領土を奪うため多くの人命を注ぐ。わが国と韓国、中国、ロシア。竹島、尖閣諸島、北方領土。北朝鮮は核ミサイルを準備した。
浅利慶太・演出の劇団四季「ハムレット」は総公演数が650回を越えるという。「最も正統的なハムレット」という。黒を基調にした舞台装置、衣装。物語の核心を抉り、人間関係の構造が見えてくる。
今公演はまさに現代、今に繋がるドラマとしてクッキリと描かれていた。
(平成25年4月1日)
加藤健一と戸田恵子が激突 
男は言う。「なんて女だ!」
女は言う。「なんて人なの!」
男にとって身勝手な女くらい扱いにくいものはない。女にとって自分を理解しない男くらい神経にさわるものはない。加藤健一に「審判」、戸田恵子に「なにわバタフライ」という一人芝居の傑作を持つ俳優が二人芝居の「八月のラブソング」で18年ぶりに激突した。見逃す手はない。(本多劇場。3月8日~同24日)
新聞を読んでいた療養所の外科の主任医師ロディオンの前に女性患者リディアが現れる。全9場の冒頭であるこの第1場、続く小さなカフェの第2場が快調で抜群に面白い。台詞の応酬、罵声で言い放題。まるで仲が悪い夫婦漫才のようなやりとりで、加藤と戸田は舞台俳優としての実力発揮だ。
いわば老いの入り口に立った“恋物語”である。人間、60歳の坂を転がり落ちれば、意地悪になるか諦めの境地になるか、初めての出会いなんぞクソ食らえ-といったところだ。ところが芝居が進むにつれて人間、男も女も、厄介で不思議な生き物だと思えてくる。
リディアの戸田はロディオンの加藤よりも2~3倍はありそうな台詞の量を速射砲のようにまくしたてる。場面ごとに全て衣装を変える。その姿が全て素敵だから、ロディオンの台詞の中にある「度し難い女」も許せる気になってくる。加藤は重い口の医師。ゆっくり話すかと思えば、突如、怒鳴り声を吐く。後半に入ると二人は穏やかな会話に移って行く。そのメリハリが効いていた。
無理がなく自然な翻訳(小田島恒志)、チャールストンを踊る二人の場面も楽しめる。いくつものパターンを変えた第2場の照明は表情を持っているかと思えた。性格も考え方も違う男女がひかれ合っていく。ロディオンは最愛の妻が、リディアは最愛の一人息子が戦死してしまった戦争体験が背後にある。「八月のラブソング」は平和を願う反戦の物語でもある。
(平成25年3月14日)
目指せ!ポスト奈良岡朋子 
新宿・紀伊国屋サザンシアターで見た劇団民芸公演「真夜中の太陽」(2月13日~24日)。上演時間1時間25分。太平洋戦争末期と現代が交差しながら、防空壕で亡くなった級友との交流が描かれた。
劇団の若手女優ばかりを抜擢していて、注目株を二人挙げる。アキを演じた望月香奈と、同級生ユキ、また主人公ハツエ(日色ともゑ)の孫の二人を演じた八木橋里紗だ。
望月は2008年入団。小さめの顔、細身の肢体。知的でハキハキとした女学生になった。
八木橋は2011年入団。まだ研究生。良かったのは作り過ぎない表情が多彩だった。存在感も出せた。
樫山文枝、日色ともゑ、その上の一枚看板となった奈良岡朋子が健在なうちに芸を盗み、劇団の一翼を担う女優となれ! そんなエールを送りたい。
(平成25年3月11日)
異邦人はぐるぐる回転する 
刺激を受けた、あるいは目を見張ったと書こう。言えるのは今年見た中のベストワンに挙げる秀作だった。
アルベール・カミュの原作「異邦人」を舞台化、表現を変えると視覚化したカンパニーデラシネラの公演、小野寺修二の演出「異邦人」だ。世田谷・パブリックシアターで2月14日~同17日の千秋楽に足を運んだ。
異才と断言する小野寺が書いていたパンフレットにキーワード二つを見留めた。
「「ぐるぐる回転する癖」と「真実は大きな声で言わない方が良さそうだ」。初演は2010年の高知県立美術館(私は見ていない)で、ワードの後者はその2年半の間に変化してきた考え方の一つだという。
「今朝、ママンが死んだ」。原作を読んだのはいつだったか。何十年も前のことだ。主人公ムルソーは母の遺体を安置する養老院へ長距離バスで向かう。殺人事件を起こし、裁判を受け、死刑判決となる。
片桐はいりが私、養老院院長、弁護士、ママン、そして司祭を演じた。ムルソーは森川弘和。大駱駝艦の田村一行はレエモン、門衛、弁護士になり、他の俳優もいくつかの役を演じ分けた。片桐の「私」はムルソーのことで、片桐がしゃべり、森川が演技、パントマイム、ダンスといったパフォーマーとなる。その重なり、交代などを小野寺演出は即時に進める。水際立った仕掛けに酔いしれるようだった。俳優たちは器械体操の如く、または床運動の如き動きで、時に繋がり、入れ代わって隙間がない芝居。「ぐるぐる回転する癖」は誰にでもあるが、この重複動作が実に楽しいのである。
「真実は大きな声で言わない方が良さそうだ」。我が国の政治家が大声で論じる弁は疑った方が良さそうだ-と置き換えてみると納得し易い。ムルソーは沈黙し、反論せず、短く答える人物である。「異邦人」。小野寺は「異脳人」ではなかろうか。
(平成25年3月11日)
読売演劇大賞の“お笑い賞”2人 
「第20回読売演劇大賞」の贈賞式が2月27日に行われました。1994年の第1回から私は投票委員の一人として係わっていて、思い入れがある賞です。誰に投票したかって?
それはご想像にお任せするとして、今回、スピーチで笑わせたのが2人。
まず最優秀女優賞の高畑淳子。
「ええから加減」と「組曲虐殺」の演技が評価された。「朝から何も食べてません』と切り出し、選考委員特別賞を受けた第9回のスピーチが15分間と長かったのを反省して短めにしゃべると言った。最後に「まだ走ります。もう1回もらいたい」と、パワフル女優らしい迫力だった。
次ぎが大賞・最優秀演出家賞の蜷川幸雄。「実は先月26日に狭心症になりました。バイパス3本を手術した。3回目です」と驚かせたが、「もっともっと頑張って演出したい。賞は貰います。大勢の人に見つめられるのは嬉しい」。入院中にお見舞いに行った時、移植した右足の痛々しい傷痕まで見せてくれた蜷川さん。ハラハラする周囲をよそに長時間、会場から去らず対象作9本も挙がった巨匠の意欲は一向に衰えていませんでした。
(平成25年3月11日)
「熱海殺人事件」外伝
やはり、野に置けレンゲ草というが、やはり紀伊国屋ホールだ「熱海殺人事件」ということになる。
劇作家つかこうへいさんが世を去って3年。思い出される事ばかりだ。
稽古場で速射砲の口立てで台詞を俳優に渡す頭の早い回転、俳優との食事会に招き入れられて食べたお母さんのお手製のキムチが旨かったこと、幻冬舎の見城徹社長が確か、まだ「野生時代」の駆け出し編集マンだった頃、彼を紹介してくれたこと、偶然、下り新幹線の車中で何年ぶりかに再会した時、体調が悪いと話してくれたこと、さらに書けば、なんと私めを悪徳新聞記者のモデルに仕立てて小説に登場させたこと-ただただ懐かしい。
2月2日に開幕した「熱海殺人事件・40YEARS'NEW」は4人の出演者が一新された若い世代による上演だった。
郷ひろみの「よろしく哀愁」が随所に効果的に流れる。木村伝兵衛部長刑事のデスクに置かれたのがダイヤル式黒電話。伝兵衛が「オレが点数を数えられないのをバカにしてんじゃねえか」の台詞も懐かしい。麻雀好きだったてつかさんは公演後、風間杜夫ら出演者と囲む麻雀が楽しみだったから、当方には笑える台詞だったのだ。
台詞と言えば「ブスに権利はあるか!」と出てきたが、確か以前は「ブスに生きる権利は」ではなかったかな。「幸せとは何だ? 掴み取るものだ」、「人としてやってはいけないことが二つある。親より先に死んではいけない。人を殺してはいけない」。つか語録のオンパレードも懐かしい。
24歳という歴代最年少の部長刑事役となった馬場徹、富山県警から来た熊田留吉刑事の牧田哲也、婦人警官水野朋子の大谷英子、そして犯人大山金太郎のNAOKI。三浦洋一、平田満、井上加奈子、加藤健一という豪華決定版(皆、エネルギッシュだったなあ!)と重ねるつもりはないが、今回のフレッシュな“熱海”にウキウキとした気分になった。
そして、カーテンコール。
4人が指し示した机の上には灰皿と煙草の煙。灰皿は、つかさんが使用した一品だそうだが、椅子にはつかさんが座っていた。「おい!しっかりと書けよな」という声が聞こえたようであった。つかさん、「熱海殺人事件」はやはり、紀伊国屋ホールが似合う。
(平成25年2月10日)
松山ケンイチの初舞台 
デビューが2002年だから俳優生活11年目で初舞台の主演を果たした松山ケンイチ君。赤坂・ACTシアターでの「遠い夏のゴッホ」(2月3日~同24日)を見たぜ。
カン違いから、1年早く羽化してしまった蟬(ユウダチゼミ)の若者ゴッホという役。昨年度のNHK大河ドラマ「平清盛」は全て見ましたよ。清盛入道の生まれ変わりが蟬だなんて。大変身には目が回るようでしたな。
虫が大好きだという西田シャトナーの作・演出。出るわ出るわ、ムシムシ大行進。カマキリ、カブトムシ、トカゲ…。二十匹の虫たちが同じ台詞を同時に発する群唱からの幕開け。その中央に居たケンイチ君は、この役が大いに気に入っているのが読み取れる笑顔だった。
演技についてはともかく、映像分野で成功している青年がなぜ、辛い舞台を踏むのかがまず疑問だった。長い稽古、長い公演期間、映像と舞台での演技(特に発声)の違いなどは、慣れない俳優には辛い経験になる。
初舞台への決意に踏み切ったのは、西田の舞台作品「破壊ランナー」を見たからだという。また、人間以外の役柄を演じてみたいとかねてから希望したからだという。そこが彼の感性なのだろう。感心したのは、多分、早い段階から舞台進出に興味を抱いていたのだろうという点。「平清盛」に出演するかなり以前からだと思える。
①笑顔が可愛い②身体能力が高い③多彩な表情を出せる④ハンサムボーイ⑤舞台での発声がしっかりとしていた。ハードな役だった平清盛に対して、ゴッホは癒し系のソフトな役。「アリで~す。アリもやります」などと言って出て来た雰囲気はアイドル系か。いやいや、先輩にはカフカの「変身」で虫を演じて絶賛された森山未来という実力者がいる。舞台は面白いぞ。ケンイチ君、ドンドン舞台に出てくれ。
【写真撮影:田中亜紀】
(平成25年2月10日)
井上ひさし氏の神通力 
つくづく、井上ひさしさんの不在を思い知らされた。
それは、第47回を迎えた「紀伊国屋演劇賞」の授賞式だった。
主に新劇の公演を対象に選ばれる歴史ある賞。今回は団体賞が劇団こまつ座。「井上ひさし生誕77フェスティバル2012」における年間の優れた舞台成果に対して-が理由。
個人賞が劇作家で演出家の東憲司、女優の那須佐代子、神野三鈴、男優の佐々木蔵之介、浜田信也。
こまつ座の井上真矢代表がまず挨拶した。井上さんの愛娘である。
「父は亡くなる前、君もこのペースで頑張っていれば、いずれ(この賞の)候補になれるんじゃないか。しかし、あと10年はやらないとね。私が死んだ後、3年間が勝負だぞ、一日たりとも怠けるんじゃないぞ、と言われました」。フェスティバルでは井上芝居七作連続上演。どれも水準が高く、井上戯曲の素晴らしさを再認識させたのだから当然の団体賞だった。
神野三鈴の挨拶が興味深かった。
こまつ座&ホリプロ公演「組曲虐殺」における伊藤ふじ子、同時にパルコ・プロデュース公演「三谷版桜の園」におけるワーニアの演技に対して-。
生前の井上さんからはこう言われていたという。
「賞のシーズンになると、井上先生から『ことし、惜しかったね。あなたはボクの次点女優。でも、これで、この役で賞を獲って取って下さい』と言われました」。その作品と役柄で初の受賞となったが、「もっと欲を持って、神野三鈴という看板を背負って-と思いました。『それなら、ボクが引き受けましょう』と三谷さんが言って下さった」。
井上作品と三谷作品による受賞に感無量となったのは、至極、当たり前の笑顔だった。
(平成25年1月31日)
愛のオデンダ 
結論から書けば、げに恐ろしき生き物かな、悲しきもの、その名は女優-となろうか。
小山明子の18年ぶりの舞台出演「女のほむら」(1月16日~20日)を見た。
東京芸術劇場シアターウエストでの上演、ピープルシアターの公演だった。小山のご主人、大島渚監督が15日に他界し、初日の16日に会見をして心情を話したその翌日の観劇だった。
「高橋お伝、切なき愛のものがたり」と副題が付いたように、主役・小山の役は高橋お伝。夫や複数の男を殺し、斬首刑となった明治期、“毒婦”と呼ばれた罪深い女として知られている。
16歳の少女期から29歳の春に生涯を終えるまでの短い半生を描いたが、お伝を女優3人で演じたのが異色。小山は主に語り部のように舞台中央に座る場面が多く、若い二人の女優が交代で演じていく演出。
婿に取った最初の男、難病の亭主の薬を都合する医師、行きずりの男らと交わっていくお伝。「夜の営み」という台詞が多用され、肉欲の場面も激しく、性と愛にまみれたエロティックな芝居である。無論、小山がその場面を演じる訳もない。
大きく言って、演技の場面が三か所ある。難病の夫の首を絞めて安楽死させる、次に腹違いの姉を殺した男の首をカミソリで切る、そして斬首される場面だ。18年ぶりの舞台だから、そして、小劇場の舞台でもあり、難儀しただろうと推察される小山。しかし、三人でお伝を演じる手法が望外に効果的だった。
「男の正体を知った」「私は鬼になる」「女は覚悟すれば何でもやれる」、そして「夫婦だから、女房が亭主の面倒を見るのは当たり前じゃないか」といった台詞を小山が語ると、身につまされる思いになった。芝居らしい芝居は少なく、台詞中心の演技ではあったが、目の前で演じられる二人の女優を座って見つめているだけで、小山の存在感は大したものだ。これほど実生活とフィクションの芝居がリアルタイムで重なった演劇を初めて見た。
それにしても観客を眺めれば、すでに男も女も卒業したような老人たちが圧倒的。平均60歳は越えていただろう。前日、向田邦子の原作「阿修羅のごとく」を見たばかり。女の執念の恐ろしさに二日続きで、うなされてしまった。大島監督の代表作「愛のコリーダ」をもじって、「愛のオデンダ」とはこれいかに?
(平成25年1月31日)
「片づけたい女たち」 
片づけたい女たち」に発見と刺激があった。作・演出が永井愛。東京芸術劇場シアターイーストの初日(20日まで)。この後、4月4日まで旅公演が続く、グループる・ばるの公演だ。
グループる・ばるは岡本麗、松金よね子、田岡美也子という女優3人だけの集団。岡本が演じるツンコのマンションに高校時代からの親友、松金のおチョビ、田岡のバツミがやって来る。入った途端、2人は立ち尽くす。これが幕開け。部屋の中は散らかし放題。足の踏み場もない惨憺たる状態なのだった。
片づけない理由が後半になると明らかになるが、まずは発見。
女優3人は喜劇女優・コメディエンヌと呼んでもいいが、演技が確かな舞台女優だ。岡本が、なかでも巧くなった、と思う。50歳代で独身のツンコは「シロー」という30代の男と別れたばかり。会社では総務の仕事をしているが、ようやく前年、課長に昇進した。ここに謎と秘密が隠されていた。
部屋は荒れ放題だが、上手の書棚だけはキチンと整理されていた。仕事、性格はむしろA型人間なのかも知れない。キチンとしたくとも出来ない苛立ち、焦り。台詞にメリハリをはっきりと付けて、怒鳴るようにしゃべったり、体全体で表見したり、ツンコという女性の生きてきた、また、今の状況を的確に演じた。出来れば、一緒に酒でも酌んでみたい女になった。ただし、本音は「こんなにうるさい女性とはどう付き合うのか、それが問題だ」。
東京も大雪となった14日、アフタートークもあった。岡本はそこでこう話した。
「今度の稽古では、これまで誤魔化してきたものが浮き出た」。2004年が初演。今回が3回目の再演。何を誤魔化してきたかは本人のみぞ知る。しかし、喜劇を演じるのではなく、演じたツンコという女が必死に生きているのが分かるのである。
次が刺激。
三人が生きた青春時代はベトナム戦争の真っ盛りだった。戦争反対。時々、その回想を話す。永井が込めた主題の一つが「傍観者の責任と罪」ではなかろうか。いや、一番のテーマと思えた。口では反対と叫んでも、何もしなかった。片づけない-のではなく、片づけなくてはいけない。
永井には「見よ、飛行機の高く飛べるを」や「こんにちは、母さん」、「ら抜きの殺意」といった秀作が多い。「ダブルアルバム」以降、家族の話を書いて、世界に繋がる作品にしようと考えた、とアフタートークで語った。女のおしゃべりで一夜を描いた「片づけたい女たち」。「傍観者の責任と罪」を問い詰めた、そこに刺激があった。
【付録】「片づけられない」は、病気と言えるらしい。注意欠陥多動性障害(ADHD)や注意欠陥障害(ADD)。落ち着きがない、衝動的に発言してしまう。14日、この症状かと思えるご婦人が多いこと。「あ、出て来た」とか俳優と同じ台詞をしゃべる。芝居見物のマナーを責める訳ではないが、どうやら、世に「片づけたい女たち」はウヨウヨいる?
(平成25年1月15日)
新派125年。頑張れ三本柱 
新派が今年125年目を迎えた。この1年、記念の興行が続くが、三越劇場で「新春新派公演」が上演されている(23日まで)。
その「口上」。水谷八重子、波乃久里子、安井昌二の劇団新派の三本柱が三人三様の挨拶をした。
八重子がまず1年間の公演日程を話した。3月にひとり芝居「花影の花」、6月に「金色夜叉」、暑い夏は巡業、その巡業の作品「三婆」を12月の新橋演舞場で上演すること-など。125年の意気込みを伝えた。
心配だった久里子は元気そうだった。
昨年12月5日に弟の勘三郎が急逝し、自分の心境などを語る機会を避けていたからだ。「口上」では「この後とも新派を愛して下さりますようお願い申し上げます」と、舞台に打ち込む決意に見えた。
安井はこう述べた。
「私は初代八重子さんに誘われて45年。早いものでございます。今年8月、85歳になります」。男優陣の大黒柱。映画界から舞台に移った老優だが、すっかり新派の風情になっているのが身に付いた芸というのだろう。
芝居は木下惠介監督の喜劇風の代表作「お嬢さん乾杯!」。この3人が実に渋く、巧く、頼もしい。
八重子は木下作品の映画では村瀬幸子が演じたバーのマダム、久里子は東山千栄子が扮した泰子の母、安井は青山杉作だった祖父。3人が3人、脇に回って主役の市川月乃助、瀬戸摩純を見守り、支え、芝居を固める役回りに徹していた。130年へあと5年。この間にしっかりと後継者を育成してほしい。それが使命だ。
(平成25年1月10日)
頑張れ、スタス!踊り子たち 
東京レビューの灯を消すな-。この合言葉で踊り続ける女性だけのレビュー集団をご存じか。
その名をスタス(STAS)。千羽ちどり、高城美輝、明石薫、銀ひ乃で4人の頭文字から名付け、結成が平成4年(1992)。そして苦節20年。その創立20周年の記念公演が11月9日から3日間開かれた。場所はもちろん東京は浅草公会堂。この4人、はっきり言ってオバさん。かつて、西の宝塚歌劇団、東のNDT(日劇ダンシングチーム)と研を競ったSKD(松竹歌劇団)のスターたちだった。
懐かしいねえ、SKD。今やホテルと変貌した浅草の名物、国際劇場を本拠地にブンブン鳴らしていたお嬢さんたちだっけ。その国際劇場も1982年に閉館され、路頭に迷ったダンサーは散り散りとなったが、この4人は結束。SKDレビューの灯を守ってきたド根性の持ち主だ。
1部では口上で4人が20周年のお礼などを述べて始まった。最後の11景「クンパルシータ」では、高城がタンゴの女。手を高く掲げて目一杯に体を反って下手に入っていく姿に思わずグッときてしまった。その心意気。テクニックと色気が売り物だったエイトピーチェスのリーダーだった高城は健在だ。
2部は若手20人のラインダンス。宝塚歌劇に負けない多彩な振り付けとテクニック。そして星里くらら、初音ひかり、芹なづな…。皆、元気に踊っていた。ダンサーというより「踊り子」という表現で呼びたいSKDのメンバーたち。今回の浅草公演も「昭和」の空気、残影を見る思いだった。
(平成24年11月12日)
B作座長を、またヨイショ 
今回もまた、佐藤B作座長をヨイショとござい!
さて、創立40周年記念興行の東京ヴォードヴィルショー。第2弾が三谷幸喜・作「竜馬の妻とその夫と愛人」(10月18日~30日)。坂本竜馬が暗殺され、残された妻おりょうに13回忌の法要に出てくれと懇願する菅野覚兵衛がB作の役どころ。初演が2000年、再演が2005年、そして翌年にニューヨーク公演。その米国公演での収録ビデオを開演前に流した。装置をザ・スズナリに合わせて客席が舞台を三方向から囲む形。また、ギター、アコーディオンなどの生演奏。出演者は4人だけで、B作は出ずっぱり、膨大な台詞。汗ダクの芝居でして-。
おりょうの妹を嫁にしながら、腹の底には師である竜馬の妻にも恋心を抱いてきた覚兵衛。その底位をおりょうの夫・松兵衛(綾田俊樹)、おりょうにも見抜かれての狼狽が愉快だ。おりょうを押し倒して「1回だけ!」などと迫れば、松兵衛を叱り、励まし、浮気なおりょうの愛人・虎蔵(佐渡稔)との決闘に向かわせる-。
そして恒例のカーテンコール。
実は、おりょう役あめくみちこが台詞のきっかけを間違えた場面に遭遇(25日)した。その時、B作は台詞が出ない彼女に対して、言葉にならないような、咳のような、合図のような音と動作。ハッと気付いた当人がようやく台詞を言ったのだった。
B作座長、怒ったのなんの。
カーテンコールの1度目が「こらっ!」という感じで彼女の手を引っ張って登場。「毎回いろんな事が起きます。もう皆さん、お気付きでしょうが…」と挨拶し、手拍子に促された2度目のカーテンコール。今度は三人は引っ込んだのに、あめくだけを押し出すように残してしまった。きまりが悪いあめく。正座して「申し訳ありませんでした。本日はありがとうございました」と平伏したのでした。もちろん喜劇の集団なので、観客も鷹揚で大笑いの大拍手。とちった場面では俳優たちは吹き出すのを堪えていた芝居が面白いのなんの。しかし、B作座長は厳しい姿勢を貫いたのだった。B作座長、あんたは偉い。
ところで、B作と角野卓造のプログラムでの対談が、また面白い。
劇団の稽古場ビルを建てた時、角野が立つほど分厚いご祝儀を持って来たこと、文学座の野球部チームと試合をした以前、山崎努は人が変わったようなヤジを飛ばしていたこと、両親に俳優になる宣言をして勘当されたB作は青年座も自由劇場も試験に落ちたこと、また、芝居を始める前は商社マンになる気で津田塾で英語を習い、「外交学会」というサークルに入っていたこと。エピソード満載でした。ちなみに角野は2015年春上演予定の第5弾(三谷幸喜の新作書き下ろし)に出演するという。
(平成24年10月30日)
富美男座長、大いに奮戦す 
新座長の富美男座長が大いに奮戦、心意気に舌を巻いたね。10月の東京・明治座は大衆演劇の梅沢劇団の公演。昭和61年、同劇場に初進出して以来26年目。それが3代目座長の誕生、襲名公演だった。観劇した6日夜の会、第2部「夢のステージ」でハプニングが起きたのでした。その場面ー
大ヒット曲(150万枚も売れたとか)の「夢芝居」から歌い始め、6曲目が十八番の「勝手にしやがれ」。例によって観客に手拍子と両手の振りをお願いして、また、例によってハットを放り投げて、さあ、次がラストの歌「劇場ーエンディング」に入る時。確か2階席の女性ファンから「アンコール!」というひと声。これに反応したお客も、もう一度やってくれという要望の声の嵐。
これにはさすがの富美男座長も、こう答えたねえ。
「かんべんしてよ。もうへとへと(へろへろだったかしらん)。それに自分の曲じゃあないのに、かんべんしてよ」といった意味合いで、腰が引けていた。ところがお客さんは許してくれない。「分かった、分かった。分かったけどこれがラスト。『劇場』はやらないよ」。バックのバンドにも了解を得て、ついに「勝手にしやがれ」をそっくり同じように歌い抜いたのでしたよ。
これこそ旅回り劇団、大衆演劇の神髄だと思うねえ。お客さんあっての芝居、サービスこそ命、新座長の心意気を見せたのであ~ります(と、劇団口調)。
公演の第1部は芝居で「ひと粒の奇跡」。富美男は主役伊達の新三に加えて、作・演出もやっていた。第3部「時雨月舞踊絵巻」も構成・演出を受け持つ大奮闘。父の梅沢清、長兄の2代目座長・梅沢武生、そして3代目と昭和13年(1938)から74年も守り続いてきた旅回り劇団だ。
第1部の芝居は、以前の三枚目や汚れ役ではなく、二枚目男役。旅回り芝居の臭いやり過ぎは薄れ、やや商業演劇のニオイがしたのは、役者として別の一面を見せる狙いもあるのだろうけど、これは本人が希望したのだそうな。
先代座長の武生は後見役に回った。座内では武生を「座長」、富美男を「看板」と呼んでいるらしいが、還暦を迎えて新座長に落ち着いた“下町の玉三郎”。来年の明治座公演は7月と決定。次の一手を見守りたい。
(平成24年10月12日)
切なく、懐かしい舞台
劇団俳優座が8月12日から同14日まで上演(俳優座劇場)した「樫の木坂四姉妹」(作・堀江安夫、演出・袋正)の感想を書けと言うなら、最初に「切ない」、次は「懐かしい」という表現になる。また、今や流行り言葉になったが「絆」の重さになる。
葦葉家は皆が長崎港を望む樫の木坂の中腹に住まいを置いてきた。大塚道子が演じた長女しを、岩崎加根子が扮した次女ひかる、川口敦子が四女ゆめ、父(河原崎次郎)、母(平田朝音)、また、洲崎(武正忠明)というカメラマンが絡み、被爆者である一家が戦前・戦後を生きてきた足跡と意味を問い掛ける。
姉妹は皆が重荷を背負ってきた。恋人を戦争で失った長女は病身を四女に頼っている。次女はアメリカに残してきた夫、また難病によって早世した娘との辛い経験によって生活と性格が荒れてしまう。そして四女。被爆した日、双子の姉の三女を救えなかった後悔をなおも引きずっていて、独身を貫く。
同居している三姉妹が些細な揉め事で口論する。炊事に追われる四女が作った粗末な料理を分け合う。まだ少女時代の姉妹が両親に甘え、戦地に散ってしまう兄と戯れ、父と長男が酒を酌み交わす回想場面。かつて、どの家庭にも見られた家族団欒は懐かしく描かれた。
葦葉家の庭先に、いつの間にか咲いたコスモス。花を見つけた妹たちは、大好きだった長兄の化身のように「お兄さんだ」と叫ぶ。この回想場面で最も切ないのが、そのコスモスの前で祈り、言葉を掛けて息子に呼びかける場面だ。母の愛情が静かに伝わってきた。そして、幕切れ。車椅子に座った長女は長崎が受けた現実、原爆の悲惨さを客席に問うように話し、四女は無言のまま背後で聞いている。2010年9月、シアターXで初演されたが、昨年の3月11日、大震災と福島の原発事故が起きた。俳優座では近年にない上質の舞台だ。どしどしと、地方を回って上演を続けて欲しい作品である。
ユーミンの催眠術
8月16日、帝国ホテルで開かれた制作発表で「あの」ユーミンがオーラを放っていた。
発表されたのは帝国劇場10月公演「8月31日・夏休み最後の日」。演劇公演、といっても「ただの芝居じゃない、ミュージカルでもない、コンサートでもない」という不思議で摑みどころがなさそうなもの。「あの」と書き出したのは、ユーミンこと松任谷由美がどのようなパフォーマンスを意図しているか。帝劇初出演の意味と、ユーミンの立ち位置が不明だったからだ。
脚本・演出のご主人、松任谷正隆は愉快な人だ。「個人的には芝居を見て、性格的に突っ込みたくなる。ボクならこうするとか。30年位、コンサートは演出しているが、芝居はこれが初めて。はっきり言って自信はありません。多分、1か月後ならマシなことが言える」。誠に正直な挨拶だった。
これを受けたユーミンは違う。さすが、天下一の大スターである。
「演出家は自信ないと言ってるが、私はまだ練習に参加していない。音楽と合体。私自身はもう勝ったようなもの。何に勝つのか。それは時の流れに勝つ。役者と音楽の力を合体させ、素敵な純愛という催眠術をかけた」と、一気呵成に言った。凡人の当方には宇宙人みたいな内容に思える。だが、正反対に思えるこのカップルだからこそ時代の先頭を突っ走って来たのかも知れない。
歌手である彼女だが観劇が大好きだった母親に連れられて小学校の高学年の時に初めて見たのがミュージカル「風と共に去りぬ」。「スペクタクルで、屋台崩しや本当の馬が出てきたり」。当時、資生堂のCMの影響から全盛の人気があった前田美波里をひと目見たいがために楽屋前で出待ちをしたそうな。「屋根の上のヴァイオリン弾き」、また宝塚歌劇、新派の公演も観劇していた。「それが今の糧になっていると思う」。
夫君によれば「女ヒチコックをやらせたかった」という舞台。映像の見えないような所に、ヒチコック監督自身が野張り観て、孝シス・カンパニーといえば、業界で知らな映っていた「ヒチコック劇場」。ユーミンは「女優デビューとスポーツ紙に書かれたけど、残念ながら演じはしません。舞台に沿って歌います。演出家と同居しているのでいろんな会話をしている。例えば病院の待合室の人に混じってとか」
しかし、以下がユーミン語録となる。
「ケレンの舞台とか、右肩上がりの見せ方は世界中で当たり前になっている。けど、胸のスクリーンに映ったもの、それを見た人の数だけ映像、思い出が広がる。5次元、7次元に広がったもの。世界が目指しているものが出来ます」。ライブ公演で今、照明や音響や装置などが肥大化している時、夫君の感性にどう着地するか。現状に対抗するそれが見えているらしいのだ。会見でまさにユーミンは催眠術をかけた。
浅野和之に主役を
シス・カンパニーといえば、業界で知らない人はいない恵比寿の女傑プロデューサー北村明子さんの腕力が頼もしい組織。企画力抜群のその才能が初めて再演公演を敢行した。
選んだのが「叔母との旅」。出演者が段田安則、浅野和之、高橋克実、鈴木浩介の男優4人だけ。初演が2010年8月。浅野和之はこの公演の成果によって読売新聞演劇大賞最優秀男優賞を受けている。
今回、青山円形劇場で8月2日開幕。その初日を見た。
主役の独身男ヘンリー・プリングを4人が演じるだけでなく、それぞれが何役も演じ分ける趣向。アイデア満載の松村武の演出力によって初演の時は芝居全体に目が向いたが、再演になると演技にも力点が置ける。
特に、浅野の演技力がさすがだった。その変わり身。男から女へ、少女から男へ。「君、いくつ?」。詩が大好きな少女になった浅野が答える。「14歳」。答える前のちょっとした間(ま)が絶妙なので、思わず吹き出てしまう笑い声。実年齢58歳の浅野は、世代、階層が違う女性を次々と演じ分けた。白髪まじりの頭など一向、気にならない。
それにしても巧いのが動物。首に輪を巻かれて数歩、歩くだけの馬の役。思い出すのが2011年6月の「ペッジ・パードン」。確か、子犬だったか、馬も犬も、その場面のみでも料金に見合うような芝居だった。
そろそろ、いや、もう主役の座に立てる実力者。「叔母との旅」では金メダルでした。
「ひばり」は舞い上がったか
劇団四季の「ひばり」には劇団、さらに演出・浅利慶太氏の志に思いが至るのだった。
初日が7月14日だった。劇団の創立記念日である。来年が創立60周年。その前年にジャン・アヌイである。「ひばり」である。自由劇場での上演である。
これは未来に向けた宣言ではないか。
ジャン・ジロドウ、ジャン・アヌイから立ち上げた初心忘れるべからず。台詞劇であり、また詩劇の名作である。ミュージカル中心の劇団という世間の評価は的外れではないが、しかし正確でもない。台詞劇の上演を断固として継続し、世界的にも上演が限られている詩劇の価値をしっかりと提示してきた。俳優集団であり、制作集団としていくら大きくなっても、演劇は台詞劇だとする原点を見据えているのだろう。
2004年以来の「ひばり」。異端審判の場でオルレアンの乙女は裁かれる。13歳の時に神の声を聞き、19歳で火あぶりに処せられる。芝居は、だが、驚きの結末を最後に用意している。ジャンヌの野村玲子が透き通るようで硬質の演技、劇場の隅々まで染み通る台詞術を見せた。シャルル七世の加藤敬二がご都合主義の王の喜劇味が面白い。ジャンヌの母の羽永共子はお久しぶりの舞台を見た。なんと言っても「コーラスライン」のキャシーだ。赤い衣装で舞台狭しと踊り回った若き日の甘美さ。少ない台詞だったが、ストレートプレイで今後もやれる。
裁判の冒頭、裁判長はジャンヌに自分の一生を演じてもらう-と命じる。人は何者かを演じているとすれば、ジャンヌは二重構造の中で演技者となる。一問一答、過去の再現、神の声について意見の応酬。「全く、フランス人って奴は付き合いにくい」というウォーリック伯の台詞には納得。妥協することの安易さと困難さ、妥協しないことの潔さ、苦しさ。天高く「ひばり」は舞い上がった。
猛烈女優直美、淳子の激突
間もなく開幕する喜劇に注目、期待している。
期待の第一は藤山直美と高畑淳子の舞台初共演。いわゆるガチンコ勝負の行方。6月4日に開かれた制作発表で燃える闘志を見た。穏やかで静かではあるが、確実な決闘場面であった、と思う。
公演は東京・日比谷のシアタークリエで7月1日~同29日に上演される「ええから加減」。原作・永田俊也、脚本・演出が田村孝裕。ひとクセもふたクセもある女優二人が漫才コンビを組み、悪い仲を克服して漫才大賞を目指す、という物語。
会見で多弁だったのが高畑。
「え~と(と、長い間の後)胸が一杯で、稽古の初日も立ち稽古もアップアップしています。いつも短パンとスッピンで走り回っている私が藤山直美さんといっしょの舞台。(彼女は)すごい人、かなわない人ですから、へばり付いていきます」
最初に挨拶したのは直美だが、相撲で言えば、横綱が三役(いや大関かしらん)に胸を貸すような勝負だろう。冒頭、「昨年の三月十一日以降、人の気持ちも少し変わってきたように思います」と切り出し、そのような中、何とか楽しく面白い芝居でお客様に喜んでほしいーという内容の発言をする顔は厳しい表情に見えた。
へばり付いていくという高畑、座長としての自覚を持つ直美。見えない火花が散っていた。
役柄は直美がツッコミ、高畑がボケという設定。一瞬で観客の目を奪い、心を鷲つかみにして笑いを巻き起こす女優直美。高畑は役を正確に掘り下げ、輪郭が分かるように演じる。育ってきた環境がまるで違う二人がしゃべりまくる漫才の場面が何より期待させる訳だ。
次に注目点。
これは主に直美の問題だろう。本拠地の松竹から初めての東宝へ。公演形態が彼女にとって冒険と言えるもの。
「おじいちゃんから100年、お世話になっている松竹。その松竹の役員さんから後押しされて(東宝に)行かせていだだこうと思い、喜んでいます」
観客からすれば松竹でも東宝でも興味は薄いのだろうが、俳優の身にすればこれは決断が必要なのだ。特に東宝系の劇場に立つ訳だから制作スタッフなど全く新たな体験になる。仁義に厚い藤山家にすれば、迷いもあったに違いない。この奇抜な女優同士の組み合わせ、興行の成否。注目されるのである。
早めの再演を期待、「間奏曲」
時に笑い声が湧いた。女性である。男は違った。台詞に集中していた。劇団四季による音楽劇「間奏曲」を私が見た日(4月25日)の観客のその反応の受け取り方は私だけだろうか。格別に面白かった。
この劇は「感性」で女は観て、男は「理性」を働かせると、思えた。なぜだろう。その問いを投げかけるのに充分なジャン・ジロドウの傑作である。
主人公のイザベルは若い教師。自然を愛し、人間らしく生きることを願い、生徒にも自由で個性を大切にさせるのだが、幽霊に憧れてもいる女性だ。その幽霊とは「死」の国からの旅人、彷徨う夢遊病者のような存在と思える。人間界ではない「あるもの」に異常な興味を抱くイザベルは「死」の世界から「この世」、「現実の世界」を逆照射して「生」を見つめたいのである。劇中の人物たちは変人扱いするが、しかし、必ずしも異常だと思えないと考える人は我々の周辺にも多い。
後半が特に面白く、また、考えさせられる。ジロドウが自身と重ね合わせたのは幽霊であり、薬屋の男であり、そしてイザベルでもあろう。劇詩人と言えるジロドウは、詩的な台詞を満載し、哲学的、思考を強制させる構図、超自然界の事象などで劇作したため、難解であるのは間違いない。それでも、例えば感性とか、理性の力、想像力によって正視すれば大いに楽しめる。
イザベル役の坂本里咲は三代目だという。劇団四季がこの作品を初演したのは1954年12月だった。その時のイザベルは藤野節子で水島弘が検査官、日下武史が視学官、井関一が町長といった創立メンバーが顔を揃え、また首斬役人Ⅰで菅原文太が出ていた。2代目のイザベルは1967年6月、日生劇場での公演の加賀まりこ。幽霊には石坂浩二が扮していた。そして三代目の坂本里咲は1990年(平成2年)2月の東京グローブ座公演から演じてきた。
今回は7年ぶりの上演。美しく、知的な女優だった藤野、妖精のような加賀、そして藤野と同じようなタイプの坂本だが、若い娘という役柄はそろそろ困難になってきたと、思う。若い観客にぜひ見せたい作品だ。早い時期に再演して欲しいが、その時は新たに四代目の誕生も期待したいものだ。
ところで、検査官の台詞、「マダム・ランベールはわが町の春であります」がやけに気に入った。どこかで使いたい表現だなあ。
「ラ・マンチャの男」を待ちわびる

今からドキドキと動悸がするほど待ちわびている。ミュージカル「ラ・マンチャの男」だ。東京・帝国劇場では8月3日~8月25日に上演されるが、すでに福岡・博多座では5月5日から公演は始まっている。
この作品、我がミュージカル・ベスト1。個人的な、独断的な、好きな作品なのだから仕方ない。蛇足ながらついでに書くと第2位は「ファンタスティックス」。以下、第3位となれば「ウエスト・サイド・ストーリー」とか「オペラ座の怪人」やら「キャッツ」とか「レ・ミゼラブル」とか横並び。異論反論は受け付けません。
ちょいと前になるが、今公演の制作発表会見が開かれた。主演・松本幸四郎が70歳の古希を迎える8月19日に通算1200回を達成するので、また共演する長女松本紀保、次女松たか子が同席したため、会場は多数のマスコミが集まった。
「役者冥利に尽きる」。まだ市川染五郎を名乗っていた幸四郎が初めて演じたのが1969年、26歳の時だった。2012年の今年が古来稀とされる古希。9代目高麗屋のかねがねの持論。「役者はどんな役でもやる必要はない。ただし、なんでも演じられなければならない」。歌舞伎では「勧進帳」の弁慶、翻訳劇では「アマデウス」、そしてミュージカル「ラ・マンチャの男」。代表作だけを挙げても、何でも演じられるこんな俳優はどこにもいない。会見では俳優という存在について「勇気、感動を与える仕事」と話し、また「夢、希望を与えたい」とも語った。
「ラ・マンチャの男」はその全部を含んでいる作品だ、と思う。70歳で演じることが出来るドン・キホーテ、セルバンテス。まさに役者冥利に尽きる、と思う。
さらに、ちょいと前だが、思い出すのが次の発言。「そろそろ自分もまとめる時期に入ってきたと思って」。今年1月に上演された国立劇場公演での制作発表。爆弾発言は続いてこうだった。「10年前から考えていたのですが、歌舞伎への同じ志の人と実現できたらと思う夢があります」。この時、秋の頃にはと語っていた夢。8月の「ラ・マンチャの男」が終わってから明らかになるのかも知れない。2012年は高麗屋にとってエポックとなる年だろう。待ち遠しい「ラ・マンチャの男」であります。
B作座長、あんたは偉い!

東京ヴォードヴィルショーが創立40周年を迎えた。その記念興行第1弾「トノに降る雨」が東京は三軒茶屋のシアタートラムで上演され、4月22日に千秋楽となったが、ある日、舞台を観て思った。「佐藤B作座長、あんたは偉い!」。
B作座長をヨイショする理由が2つある。最初はカーテンコールの風景だった。出演者全員の前に一人立ち、それぞれを紹介し終わると客席に三礼する。上手客席へ、次に下手、そして中央。その時、「ハイッ!」(と聞こえたが)と、大声で声を掛けて上手に左手を、下手に右手を差し出す。その声の調子、気合、間の良さ、それがステキなのだ。
カーテンコールのやり方は千差万別。かつて「夢の遊眠社」を率いた野田秀樹は、舞台中央にたった一人正座し、平伏した。これにはビックリしたものだ。
ヴォードヴィルショーはVAN99ホールの頃から観てきたが、B作座長のこの間の良い「ハイ!」がいい。一座を率いる親分の人知れない腹のくくり方を感じるのは私だけだろうか。従って座員、ゲストが結束しているのが分かる。創立40周年。その重みに思いをやるのだった。
二番目は、プログラムを読んだ感想だった。柄本明との対談が、すこぶる付きに面白い。勉強をさせてもらった。
面白いというか、なるほどと感心したのが次の部分。一部を引用させてもらう。
B作「(中略)確かに芝居は俳優が不安だから良いんだ。自信を持った芝居なんか観たくないと思うよ」
柄本「フフフフフ、ようやくついて来れたな」
B作「本番に入ってちょっとウケたらすぐ芝居が変わるような奴はダメ、不安で居続けないといけないんだよな。それは俳優を続ける限り、忘れちゃいけないことだと思うよ」
これは喜劇に限らないが、特に観客という人間に笑う衝動・行為を引き出す演劇俳優の本質だ。
ところで記念興行は第5弾まで続く。B作座長はその区切りで5本やり切ったら新しい座長に引き継ぐと話している。最後の第5弾は2015年春。その時、彼は66歳。参考までに、天才藤山寛美座長が亡くなったのは60歳。厳しい喜劇の世界で頑張るB作座長は、偉い。
第2弾は三谷幸喜・作「竜馬の妻とその夫と愛人」(2012年10月18日~30日。ザ・スズナリ)。第3弾は永井愛・作「パパのデモクラシー」(2013年4月上演予定。座・高円寺Ⅰ)。第4弾は三谷幸喜・作「その場しのぎの男たち」(2013年秋上演予定。本多劇場)。第5弾は三谷幸喜の新作(2015年春上演予定)。原稿取材中
PROFILE
■大島幸久メモ
東京生まれ、団塊の世代。ジャイアンツ情報満載のスポーツ報知で演劇を長く取材。演劇ジャーナリストに。現代演劇、新劇、宝塚歌劇、ミュージカル、歌舞伎、日本舞踊。何でも見ます。著書には「名優の食卓」「新・東海道五十三次」「それでも俳優になりたい」。鶴屋南北戯曲賞、芸術祭などの選考委員を歴任。毎日が劇場通い。